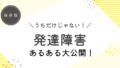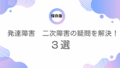こんにちは!おかーちゃんです。
突然始まる癇癪(かんしゃく)やパニックに、どう向き合えば良いか悩む保護者さまは多いものです。
本記事では「発達障害 癇癪 対応」の最新知見をもとに、5分で実践できる落ち着かせ方と、なるべく同じ状況を招かない予防策をわかりやすく解説いたします。
発達障害 癇癪が起きる理由を知ろう
感覚過敏・認知の特性が影響
ポイント:まず原因を理解することが最速の対策です。
発達障害のある子どもは音・光・触覚などに敏感で、刺激が限界を超えると爆発的に感情があふれます。
国立障害者リハビリテーションセンターは「環境を整えるだけで問題行動が軽減する」と示しています。
まずは“何が苦手か”を一緒に探しましょう。
環境ストレスとルーティン崩れ
急な予定変更や混雑した場は、大人以上に大きなストレスになります。
前もって絵カードや写真で流れを示せば、先が見えずに抱える不安を減らせます。
発達障害 癇癪・パニックの安全対応5分法
ステップ1 安全確保
ポイント:最優先はけがの防止です。
とがった家具や飛び出しを防がないと大事故につながります。静かなコーナーに移動し、家具の角をガードすると多くの家庭で効果が報告されています。
「周囲を安全に保つ」ことを合言葉に動きましょう。
ステップ2 共感と安心ワード
- 低い声でゆっくり「怖かったね」と気持ちを代弁
- 急な指示は避け 「大丈夫、一緒にいるよ」で安心を提示
- 視線を合わせすぎず、背中や肩をそっと支える
ステップ3 落ち着く呼吸とアイテム
深呼吸を「一緒に3回ゆっくり数えよう」と促すと、酸素が脳に届き冷静さが戻ります。
ぬいぐるみ・重みブランケットなどお気に入りグッズを手渡す方法も有効です。
発達障害 癇癪を減らす予防ルーティン
見通し支援で不安を削減
ポイント:子どもは「次に何をするのか」がわかると安心します。
不安が小さいほど癇癪の発生率は低下します。「あと5分」タイマー・スケジュールボードは視覚的で効果が高いと専門家が推奨します。
ルーティンは掲示して家族全員で共有しましょう。
感覚刺激のカスタマイズ
- 大音量が苦手 → イヤーマフやノイズキャンセリング
- 服のチクチク → タグを取る・綿100%を選ぶ
- まぶしさが負担 → サングラスやカーテンで調光
簡単な工夫ですが、刺激総量を減らすと爆発的な癇癪は激減します。
発達障害 癇癪後のフォローと肯定感アップ
感情の言語化を手伝う
落ち着いた後に「悔しかったんだね」「怖かったんだね」と気持ちを言葉で示すと、子どもは自分の感情を整理できます。
感情カードや絵文字を使うと、小学生でも楽しく取り組めるでしょう。
小さな成功体験を積む
- 玄関まで行けた → シールを貼って祝福
- 深呼吸ができた → ハイタッチで共有
- 自分から言葉で助けを求めた → 好きなおやつを一つ増量
成功を見える化すると自信が育ち、癇癪の頻度がさらに下がります。
発達障害 癇癪支援に役立つ相談窓口
医療機関と専門外来
国立成育医療研究センターこころの診療科は感情面の困りごとにチームで対応しています。
地域の小児精神科外来でも発達検査や薬物療法を相談できます。
家族が使えるオンライン相談
発達障害情報・支援センターはLINE相談やチャット受付を拡充中です。夜間・休日でも専門家とつながれ、孤立を防ぐ支えになります。
まとめ:5分の“神対応”で癇癪は鎮まる
癇癪は危険を減らす動き→共感→深呼吸の3ステップで多くの場合5分以内に落ち着きます。
さらに、見通し支援・刺激調整・成功体験の予防セットを家庭で続ければ、発生頻度は確実に減少します。
「困ったら早めに相談」を忘れず、家庭・学校・専門機関の力を借りながら、子どもが安心して過ごせる環境を整えていきましょう。
最後までご覧いただきありがとうございます。
次回からは『二次障害』の内容をご紹介していきます。ぜひご覧ください。

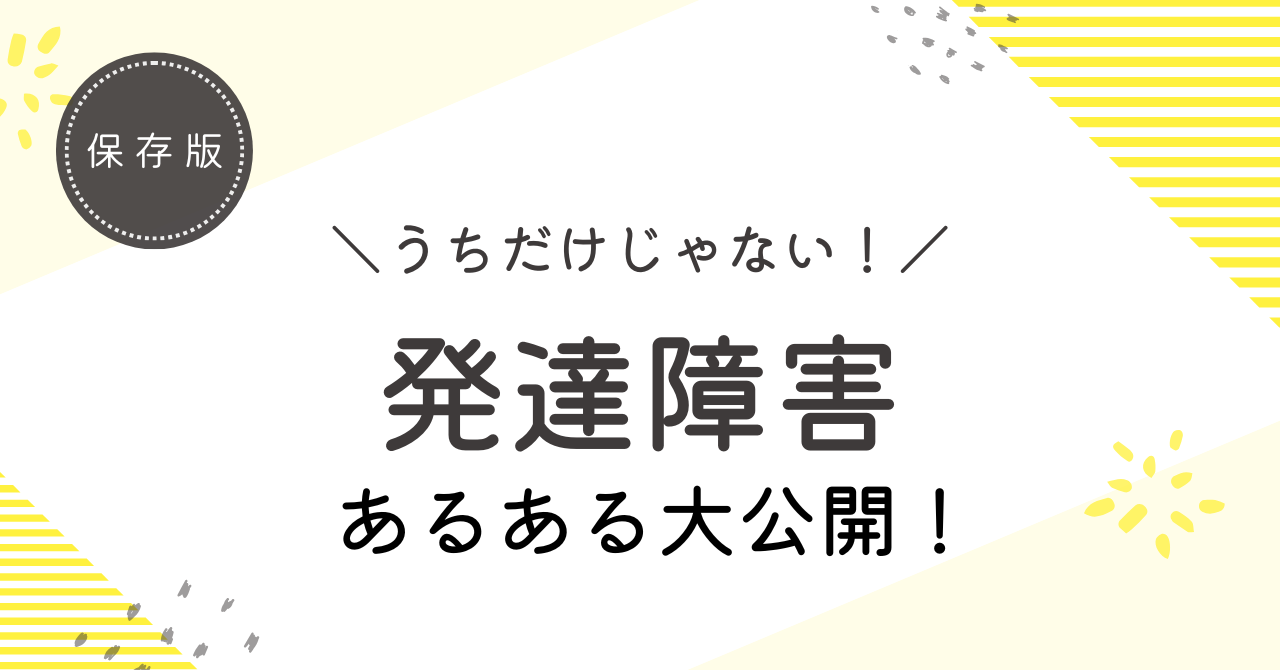
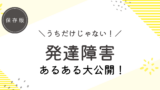

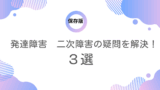
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4734a63a.e6829a88.4734a63b.c0e7bd3f/?me_id=1380587&item_id=10000001&pc=https%3A%2F%2Fimage.rakuten.co.jp%2Fregalo-online-shop%2Fcabinet%2F006.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)