こんにちは!おかーちゃんです。
5歳児健診で「要観察」「指摘あり」と言われたら、その後どうすればいい?
本記事では、健診後に利用できる支援・療育サービス、自治体のフォロー、手続きのポイントを2025年最新情報でまとめます。
親が“今すぐできること”と“自治体ごとの違い”もわかるので、焦らずステップを踏んでください。
5歳児健診後の選択肢|どう行動する?
POINT! 健診結果は「親がサービス利用を拒否」することも自由。必要に応じて相談・見送りも選択OK!
【図解】健診後に利用できる主な支援・療育サービス一覧
| サービス名 | 内容 | 申込・利用方法 |
|---|---|---|
| 療育センター | 発達検査・個別訓練・親子教室・ペアレントトレーニングなど | 市区町村または医師・保健師の紹介で申請(相談は無料が多い) |
| 発達支援センター | 生活・学習・行動の困りごとを総合的にサポート | 自治体・支援センターに電話や窓口で直接相談OK |
| 医療機関(小児科・専門外来) | 発達検査・診断・必要な指導や薬の処方など | 紹介状や予約が必要な場合も/自治体経由は費用補助も |
| 親の会・ピアサポート | 同じ立場の親同士で情報交換・悩み相談・勉強会など | 自治体や支援団体、ネットで検索して参加 |
自治体ごとに違う支援サービス|比較ポイント
【公式ページ】
千代田区 5歳児健診・発達支援
市町村ごとに違う!発達支援・療育サービスの具体例
5歳児健診後のサポートは「自治体によって大きな差」があります。 ここでは主な都市&地方自治体の実例を紹介します(※2025年最新情報)。
| 自治体名 | 健診後の主な支援・サービス | 特徴・ポイント |
|---|---|---|
| 東京都千代田区 | 療育センター・親子教室・発達相談・就学相談 | 区の発達支援室が窓口、無料相談・定期フォロー、Web申込可能 |
| 大阪市 | 発達支援センター・巡回相談・親の会紹介・二次健診 | 各区で専門員が定期相談、グループ療育あり |
| 横浜市 | こども家庭支援センター・個別相談・ペアレントトレーニング | 健診後に担当支援員がつき、長期的な伴走支援が受けられる |
| 長野県松本市 | 発達支援センター・地域療育教室・訪問型サポート | 地方都市でも早期介入に積極的、移動教室・訪問支援が手厚い |
| 札幌市 | 発達障害児相談センター・専門医紹介・親の会連携 | 健診後に「療育案内パンフレット」配布、兄弟も一緒に相談可能 |
★あなたの自治体でも公式HPの「5歳児健診」「発達支援」「療育」のページを要チェック! 公式窓口リンクも必ず貼っておこう!
なぜ自治体ごとに違いが?利用時の注意点
同じ「5歳児健診後の発達支援」でも、都市部と地方、自治体によって案内・相談窓口・利用できるサービスに違いがあります。
公式ページで最新情報を必ず確認+迷ったら直接問い合わせが安心!
療育・発達支援を受けるまでの手続きフロー
- 健診会場や自治体から紹介を受ける/自分から窓口へ相談もOK
- 面談や必要書類の記入、本人・家族のヒアリング
- 利用先・開始日が決まったら、実際の通所やプログラム開始
- 数ヶ月ごとに振り返りや進路の相談もできる
【コツ】 “迷ったらとりあえず相談”でOK! 必ずしも継続利用しなくても大丈夫です。
まとめ|5歳児健診後は「支援につなげる一歩」が大切
5歳児健診後に「要観察」「指摘あり」と言われても、そこで終わりではありません。
自治体ごとに整備されている発達支援・療育サービスを利用することで、子どもの得意を伸ばし、苦手をサポートする環境を早めに整えることができます。
今回の記事では、都市部と地方でのサービスの違いや、療育センター・発達支援センター・親の会・医療機関など幅広い支援先を紹介しました。
実際に利用した家庭の声からも、「一歩踏み出して相談して良かった」という声が多数寄せられています。
迷ったときは「まず相談」から。自治体窓口や専門家とのつながりを活用し、お子さんに合った支援を見つけていきましょう。
関連記事として、5歳児健診の基本と最新情報や、就学進路選びのポイントもあわせて参考にしてください。
最後までご覧いただきありがとうございます。
【外部リンク・公式窓口】
関連記事・就学準備・合理的配慮記事リンク
- 合理的配慮とは?学校で受けられる支援と対象・申請のポイント
- 就学前がカギ!合理的配慮の意味と今すぐできる支援・チェックリスト
- 支援級・通級・通常級を決める就学相談Q&A
- 発達障害児の就学前準備完全マニュアル/発達障害児の小学校進路選び完全ガイド
- IEP(個別支援計画)とは?意味・目的・作り方&チェックリスト完全ガイド
- 5歳児健診で「発達が気になる」と言われたら?グレーゾーンと親のための全対策

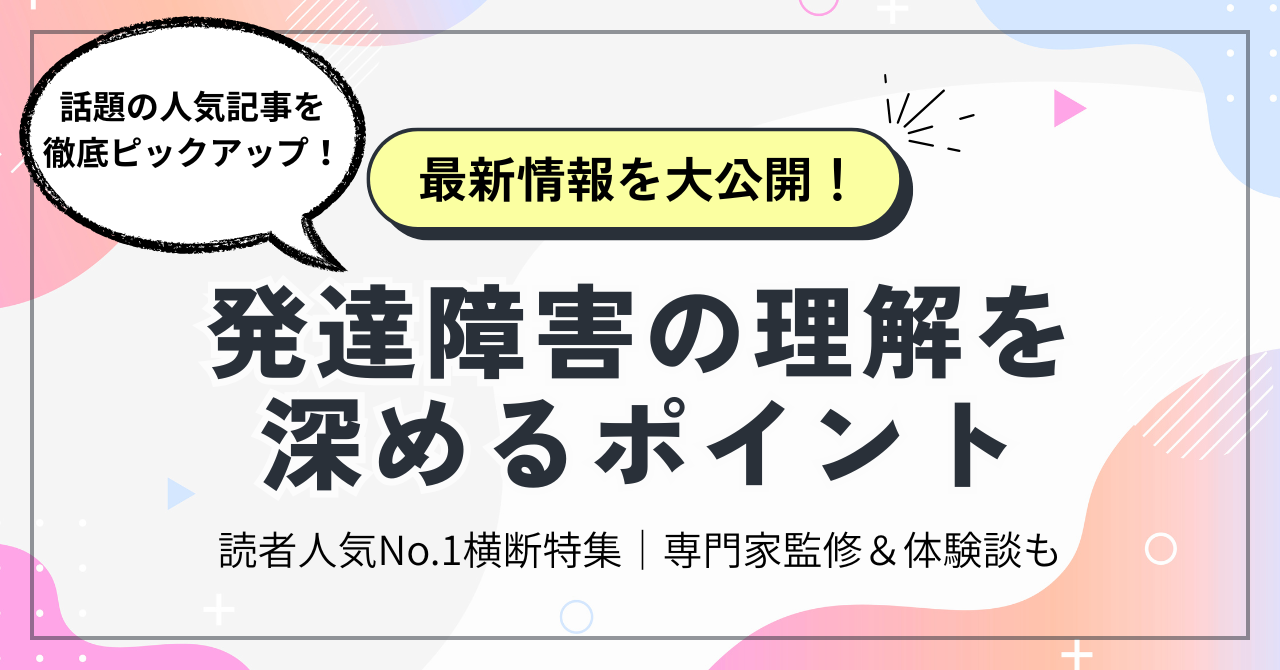
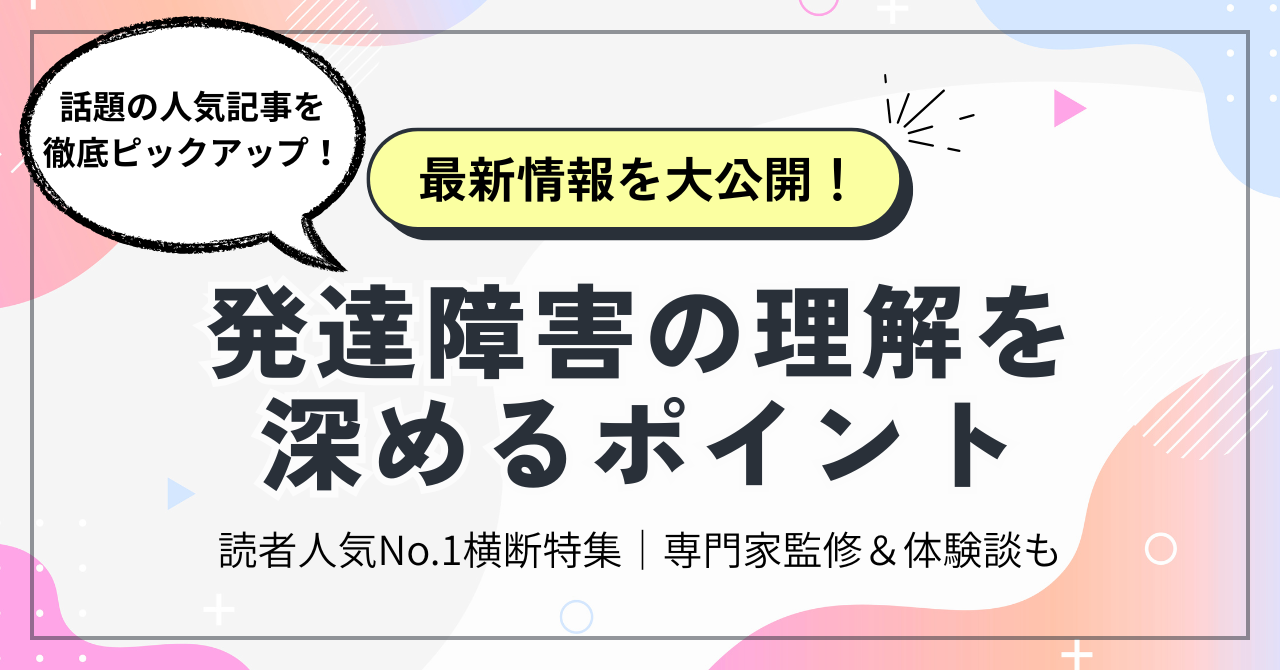

【体験談】
「健診で発達支援センターを紹介され、初めて相談したことで“ひとりじゃない”と感じられた」
「療育教室で子どもも楽しみながら通える場所が見つかりました」