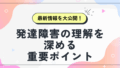こんにちは!おかーちゃんです。
「明日もまた行きたくないって言うかな…」
発達グレーゾーンの子どもを育てる中で、登園しぶりや拒否は避けて通れない壁のひとつです。わが家でも、ある時から息子が突然「保育園に行きたくない」と言い出し、毎朝がまるで戦いのようになりました。
このブログでは、そんな日々の中で見えてきた登園拒否の理由や対応法、声かけの工夫をまとめています。
同じように悩む方のヒントになればうれしいです。
幼稚園へ行きたくない発達障害グレーの原因
感覚過敏・こだわりが強い子どもの背景
まず原因を理解することが対策の出発点となります。
登園拒否の多くは「音が大きい」「服がちくちくする」などの感覚過敏や、予定の変化が苦手という特性が関係します。
たとえばバスのエンジン音が怖くて玄関から動けないケースでは、イヤーマフで刺激を減らすだけで気持ちが落ち着く例が報告されています。
原因がわかれば対処の方向性が見えてきます。
モチ男が行きたくない理由は最初全然わからなかったです。ただ行動や嫌がるポイントをじっくり観察してみたら、いつもと朝の準備が違う所があると拒否がありました。
園生活そのものへの「不安」
友達関係や先生とのコミュニケーションがうまく取れない場合、幼児は「行きたくない」と身体で示します。
このとき大人が「甘え」と決めつけてしまうと、自己肯定感が下がり二次障害につながるおそれがあります。
丁寧な理由の聞き取りが欠かせません。
登園拒否対策の基本ステップ
ステップ① 安心できる朝のルーティン作成
「何をするか」が毎日同じ流れだと子どもは落ち着きます。
見通しが立つと不安が小さくなるためです。
支度ボードに「起床→着替え→朝食→トイレ→出発」を並べ、終わったらマグネットを裏返す方法が効果的とされています。
視覚支援は家庭で今すぐ導入できます。
▶Amazon お支度ボード
ステップ② 成功体験を毎日積み重ねる
玄関の一歩手前、制服を着るだけ、など小さな目標を設定し、達成したらハイタッチやシールで褒めてください。
「できた!」の実感が続くと、次第に園まで行けるようになります。
朝の支度を楽しくする具体策
視覚支援ツールでワクワク感を演出
キャラクター付きタイムタイマーや色分けハンガーを使って、「あと何分で出発」「今日はこの服」と一目で分かるしくみを作りましょう。
遊び感覚が生まれ、支度がゲームになります。
▶Amazon タイムタイマー
感覚刺激をプラスしてスムーズに着替え
五感を満たすと切り替えが円滑に進む場合が多いです。
園と家庭が連携する相談方法
連絡ノートは「困った場面→対応→結果」で共有
情報共有がスムーズになると対応が統一され、子どもの混乱が減ります。
大人同士が同じ対応をすると、子どもは安心感を得るためです。
「お着替え拒否→タオルケットで包む→5分後完了」のように書くと園も家庭も同じ手立てを取れます。
やり取りは簡潔・具体的を心がけてください。
実際、我が家でも園との情報共有はこまめにしており行動の統一が取れた事でモチ男の安心に繋がったケースは多くありました。
あわせて読みたい▶合理的配慮とは?学校で受けられる支援と対象・申請のポイント
専門機関のアセスメントを活用
発達障害かどうか気になる時は、発達外来や療育センターで評価を受けると支援の幅が広がります。
外部リンク例:
国立成育医療研究センター
発達障害情報・支援センター
発達障害グレー幼児の心を守る支援制度
通園等助成・相談支援の最新情報
2025年4月改正により、通園等助成の対象が拡大見込みと報じられています。
申請には自治体の窓口で医師の意見書が必要となりますので、早めの準備が安心です。
保護者が利用できる地域子育て支援拠点
市区町村の「親子教室」「ペアレントトレーニング」は無料または低価格で参加できます。
同じ悩みを抱えた保護者同士の交流は心の支えになり、長期的なモチベーションを保てるでしょう。
困ったときに頼れる専門機関
医療・福祉・教育の相談窓口まとめ
- 発達外来(小児科・児童精神科)
- 児童発達支援センター
- 臨床心理士によるカウンセリング
- 教育相談室・スクールカウンセラー
各機関の役割を知ることで、「どこに」「何を」相談すれば良いかが明確になります。
まとめ:一歩ずつ進めば登園はきっとラクになる
登園拒否は子どもからの大切なサインです。
原因を知り、家庭と園が同じ方向を向いて小さな成功体験を積み重ねれば、子どもは少しずつ自信を取り戻します。
ご家庭に合った方法を選び、無理のないペースで取り組んでくださいね。
最後までご覧いただきありがとうございます。
参考リンク あわせて読みたい関連記事
- 家庭でできる療育【実体験】① 視覚支援
- 家庭でできる療育【実体験】②スケジュール管理
- 【保存版】発達障害かも?受診すべきサイン5選+相談先まとめ
- 発達障害の地域連携型支援体制を徹底解説|親子で安心できるサポート&相談窓口まとめ
- こども誰でも通園制度を徹底解説|保育園の新しい選択肢を全保護者に!

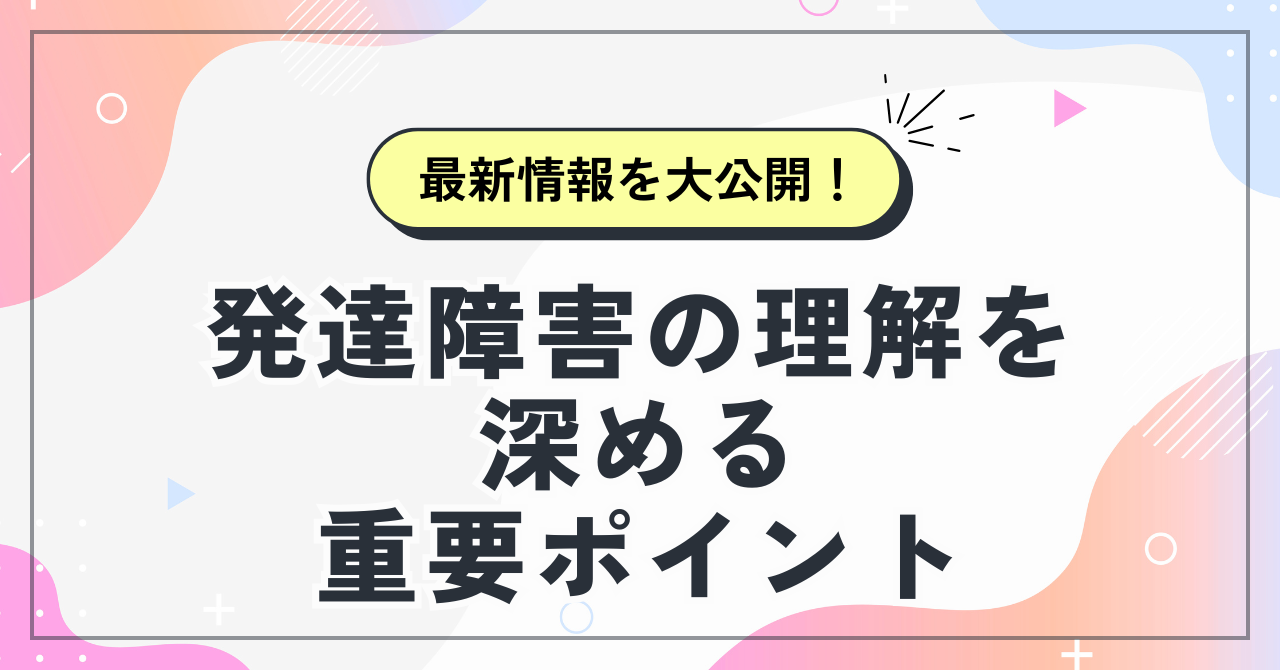
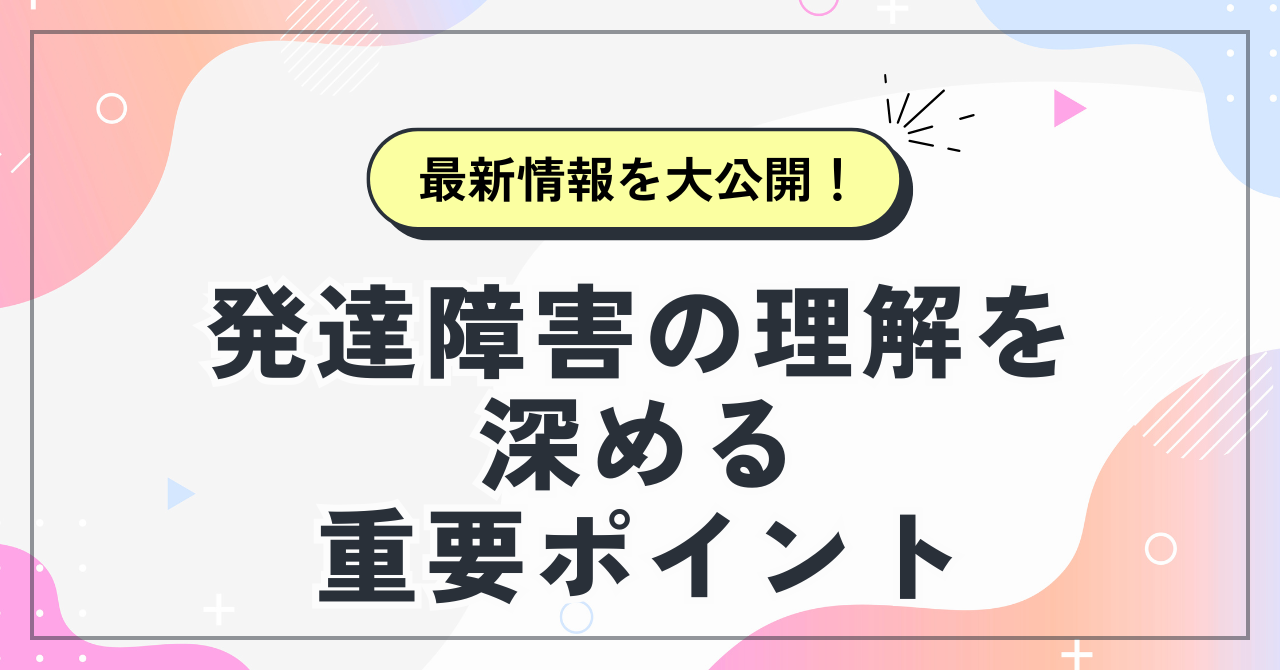
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/47acc075.b3a5211c.47acc076.a0e6cd7d/?me_id=1264967&item_id=10007747&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fauc-armadillo%2Fcabinet%2Fstationery%2Flv-7156-8.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)