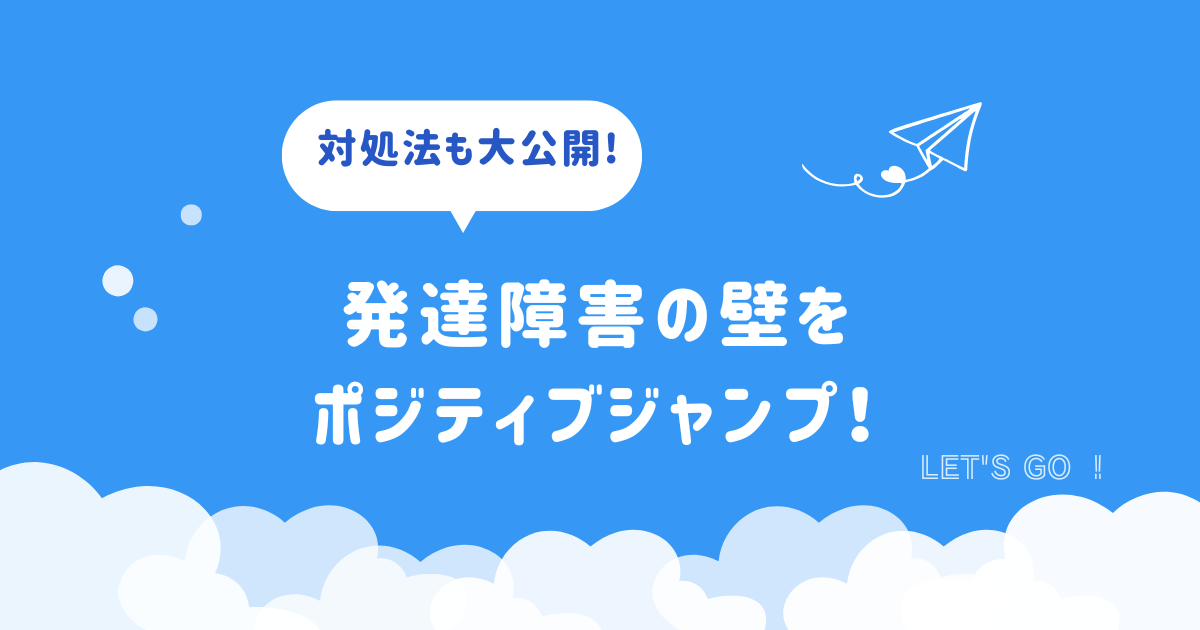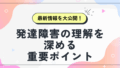こんにちは!おかーちゃんです。
前記事までは、発達障害についての知識や理解を一緒に深めてきました。でも知識が増えるほど「これからどう向き合えばいいんだろう?」「もし悩んだときはどうしたら…」と、不安や戸惑いがわいてくることもあるかもしれません。
そんな時こそ、ちょっとだけ視点を変えてネガティブな気持ちに寄り添いながら「少しずつ前向きになれるコツ」を見つけていきませんか?
今回からは、実際の困りごとや心が揺れる瞬間に「みんなどうしてるの?」というリアルな声も交えながら、一緒に考えていけたらと思っています。
あなたが少しでも「大丈夫」と思えるよう、ここでお手伝いできたらうれしいです。
実際に私が現場でやってみて効果を感じたポイントや、日々の子育て経験もシェアしますね。
はじめに:発達障害の人にとって「生きやすい環境」とは?
学校や職場で「なんとなく居心地が悪い」「なんで自分だけこんなに苦しいんだろう」と感じたことはありませんか?
発達障害(ADHD、ASD、LDなど)の人は、環境とのミスマッチによってストレスを抱えやすい傾向があります。
でも、ちょっとした工夫で「過ごしやすい場所」に変えることができるんです!
今回は学校や職場でできる「発達障害の人に優しい環境づくり」について、具体的なアイデアを紹介します。
発達障害の人が苦手に感じやすい環境は?
発達障害の人が「生きづらさ」を感じる原因の多くは、「周りとのズレ」や「環境のミスマッチ」にあります。
例えば、こんな場面で困ったことはありませんか?
| 場面 | よくある困りごと | 配慮できる工夫 |
|---|---|---|
| 学校 | ・黒板の文字が読みにくい(LD) ・グループ活動が苦手(ASD) ・集中が続かない(ADHD) | ・プリント配布&文字を大きく ・個人作業を選べる ・静かなクールダウンスペース |
| 職場 | ・指示があいまい(ASD) ・騒がしいと集中できない(ADHD) ・急な予定変更で混乱(ASD) | ・口頭+テキスト指示 ・静かな作業スペース/イヤホンOK ・スケジュール固定&変更時は事前連絡 |
学校での困りごと
職場での困りごと
こんなふうに、発達障害の特性に合わない環境だと、日々の生活がとてもストレスフルになります。
でも、少しの工夫で改善できることもたくさんあるんです!
学校でできる!安心できる環境づくりアイデア
- プリント・板書の工夫:文字大きめ、重要ポイントを色分け、事前配布やデジタル共有も◎
- グループワークの配慮:一人作業もOKに、役割分担を明確に、休憩も柔軟に
- 静かなスペースの設置:図書室や別室・パーテーションで「ちょっと休める」場づくり
①板書やプリントの工夫
黒板の文字を大きく書く&プリントを配る
②グループワークの配慮
1人作業も選べるようにする
ASDの人は、集団よりも1人で集中できる作業の方が得意な場合も。
③休憩スペースを設ける
静かに過ごせる「クールダウンスペース」を作る
人混みや騒がしい環境が苦手な人のために、「一時的にリフレッシュできる場所」があると◎。
職場でできる!安心できる環境づくりアイデア
- 指示はシンプル&具体的に:口頭+チャットやメモで補足、「いつまでに・何を」明確に伝える
- 静かな作業環境:イヤホンOK、個室やパーテーション、集中スペース
- 予定変更は早めに:できるだけルーチン化、変更があれば事前に伝える
①指示をわかりやすく伝える
口頭指示だけでなく、テキストでも共有する
口頭の指示をすぐに忘れてしまうADHDの人や、あいまいな表現が苦手なASDの人に効果的!
② 静かに作業できる環境を用意する
イヤホンOK&静かな作業スペースを確保
ADHDの人は、周囲の雑音で集中力が途切れやすい!
③突然の予定変更を減らす
スケジュールをできるだけ固定する
ASDの人は、「急な予定変更」にストレスを感じやすい。
【実体験MEMO】現場で感じた「本人も周りもラクになる工夫」
私の会社にも発達障害の方がいました。本人が勇気を出して私に打ち明けてくれました。
上司・育成の立場として大切にしていたのは――
モチ男の子育て経験も活きて、前より“余裕をもって”対応できるようになりました。
現場の工夫は、誰か一人のためじゃなく、みんなの「生きやすさ」につながると実感しています!
まとめ:小さな配慮が「みんなの安心」を作る!
「発達障害の人にやさしい職場・学校」は、実は“誰にとっても快適な場所”。
明日からできる工夫、ぜひ取り入れてみてください!
最後までご覧いただきありがとうございます。
役立つ!信頼できる情報・相談先リンク
- 発達障害情報・支援センター(国リハ DDIS)
- LITALICO発達ナビ
- NHK すくすく子育て
- 家庭でできる療育【実体験】②スケジュール管理
- 【発達障害とは?】特徴・症状を3分で理解!学べる基礎ガイド①基礎編
- 家庭でできる療育【実体験】④環境調整
- 夏休み明けから使える!先生に伝わる配慮依頼テンプレ
- 発達グレーとは?子ども・大人に多い特徴とサイン|困りごと・診断・接し方まで完全ガイド