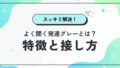こんにちは!おかーちゃんです。
小学生のグレーゾーンは見えにくいことが多いですが、「あれ?」と感じるサインは意外と身近にあります。
本記事では、発達障害グレーゾーンの見過ごしがちな特徴・サイン・家庭でできるサポート・実体験まで、分かりやすくまとめました。
発達障害グレーゾーンとは?診断がつかないのに困りごとがある子
発達障害グレーゾーンとは、医師の診断がつかないけれど、学校や家庭で日常的に困りごとがある子どものこと。
このため「助けてもらいにくい」のがグレーゾーンの難しさ。大人が気づき・理解することが重要です。
グレーゾーン小学生の特徴と行動例
| 特徴・傾向 | 具体例 |
|---|---|
| 集団行動が苦手/一人遊びが多い | グループ活動で孤立、休み時間も一人 |
| 空気を読むのが苦手 | 冗談が通じない、会話がズレがち |
| 感覚過敏 | 音・におい・光に敏感、パニック |
| 好きなことにだけ集中/過集中 | 特定分野の勉強だけ得意/ほかは苦手 |
| 得意と苦手の差が大きい | 計算は得意だが漢字は苦手など |
本人は「なぜうまくいかないのか」分からず苦しんでいることが多いです。
見過ごしやすい5つのサイン
- 友だちとのトラブルが多い
- 冗談や空気が読めずケンカになる
- 言葉のやりとりがチグハグ
- 相手の気持ちを読み取るのが苦手
- 忘れ物がとても多い
- 毎日のように何かを忘れる・片付けが苦手
- 連絡帳が正しく書けない、持ち物の定位置が分からない
- じっとしていられない
- 授業中に立ち歩く/手遊びが多い
- 興味のないことに集中できず落ち着きがない
- 音やにおいに敏感すぎる
- 給食のにおいや教室の音でパニック
- 耳をふさぐ、顔をしかめる
- 得意と苦手の差が大きい
- 得意分野は突出しているが、他の部分は極端に苦手
- 周りから「できる子」と誤解されやすい
【実体験エピソード】モチ男のグレーゾーン子育て
実際に我が家での工夫・サポート例
その結果、少しずつ自分で解決策を考えられるようになり、焦りやパニックが減ってきています。
サインに気づいたときの対応策・相談先
- 学校の先生・保健室・スクールカウンセラーに早めに相談
- 地域の発達支援センターや児童相談所
- 困りごとや忘れ物の記録をつけて具体的に相談する
- 家庭でも「できたこと」をしっかり褒める&自己肯定感を育てる
まとめ|子どもの「小さなサイン」に気づいてあげよう
「変だな」「困っているな」と思った時こそ、親や先生のサポートが伸びるチャンス。お子さんの生きやすさと笑顔のために、小さな変化に気づいて一緒に成長を応援しましょう!
最後までご覧いただきありがとうございます。
参考リンク・あわせて読みたい記事
- 厚生労働省|発達障害情報・支援センター
- 【年齢別】グレーゾーンの発達目安/合理的配慮・インクルーシブ教育よくあるQ&A
- 【学校見学の持ち物・服装・マナー完全版】就学前に親子で失敗しない準備リスト
- 家庭で実践!ペアレントトレーニングのやり方と子どもが伸びる声かけ例【小学校編】
- 落ち着きがない・忘れ物が多い小学生の困りごと/小学校入学準備で本当に役立った!子ども向けグッズ5選/勉強嫌いな小学生が変わった!親子で試したモチベーションアップ方法とアイテム/勉強しない小学生が前向きに!やる気を引き出す声かけと環境づくりのコツ
- 合理的配慮とは?就学前支援が重要な理由/インクルーシブ教育とは?
- 家庭でできる療育【実体験】③コミュニケーション支援

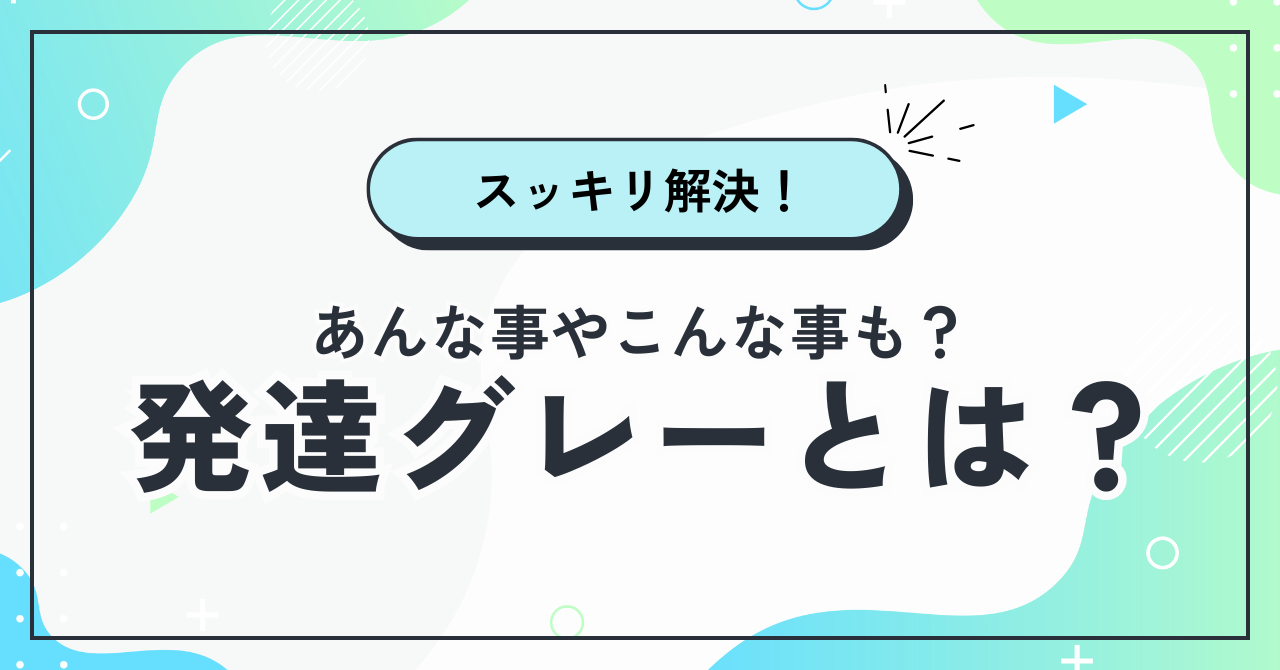
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/47166ecb.0649b34c.47166ecc.86db4aeb/?me_id=1406417&item_id=10000512&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fchakasho-dina%2Fcabinet%2F11363259%2Fimgrc0116503782.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)