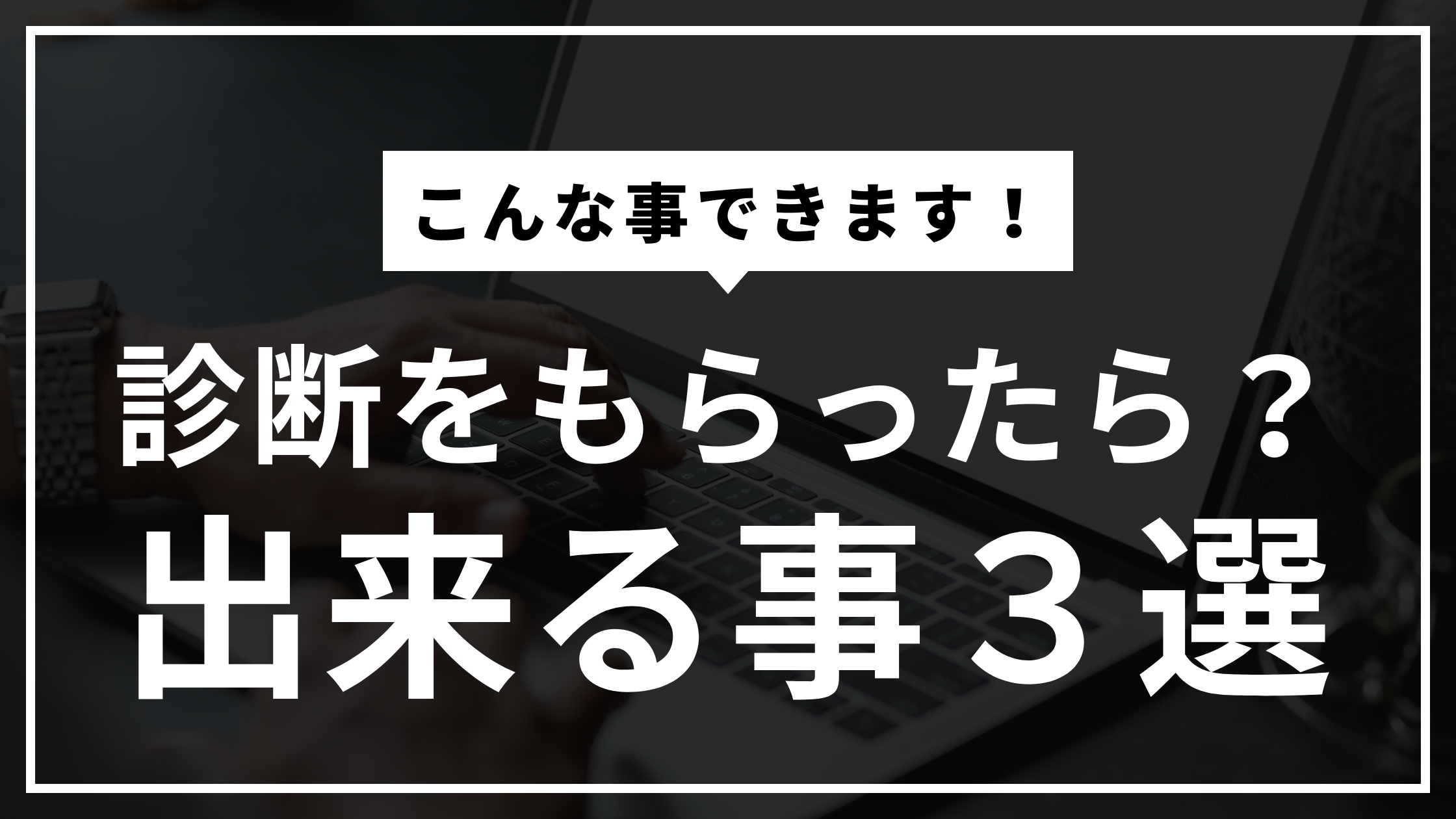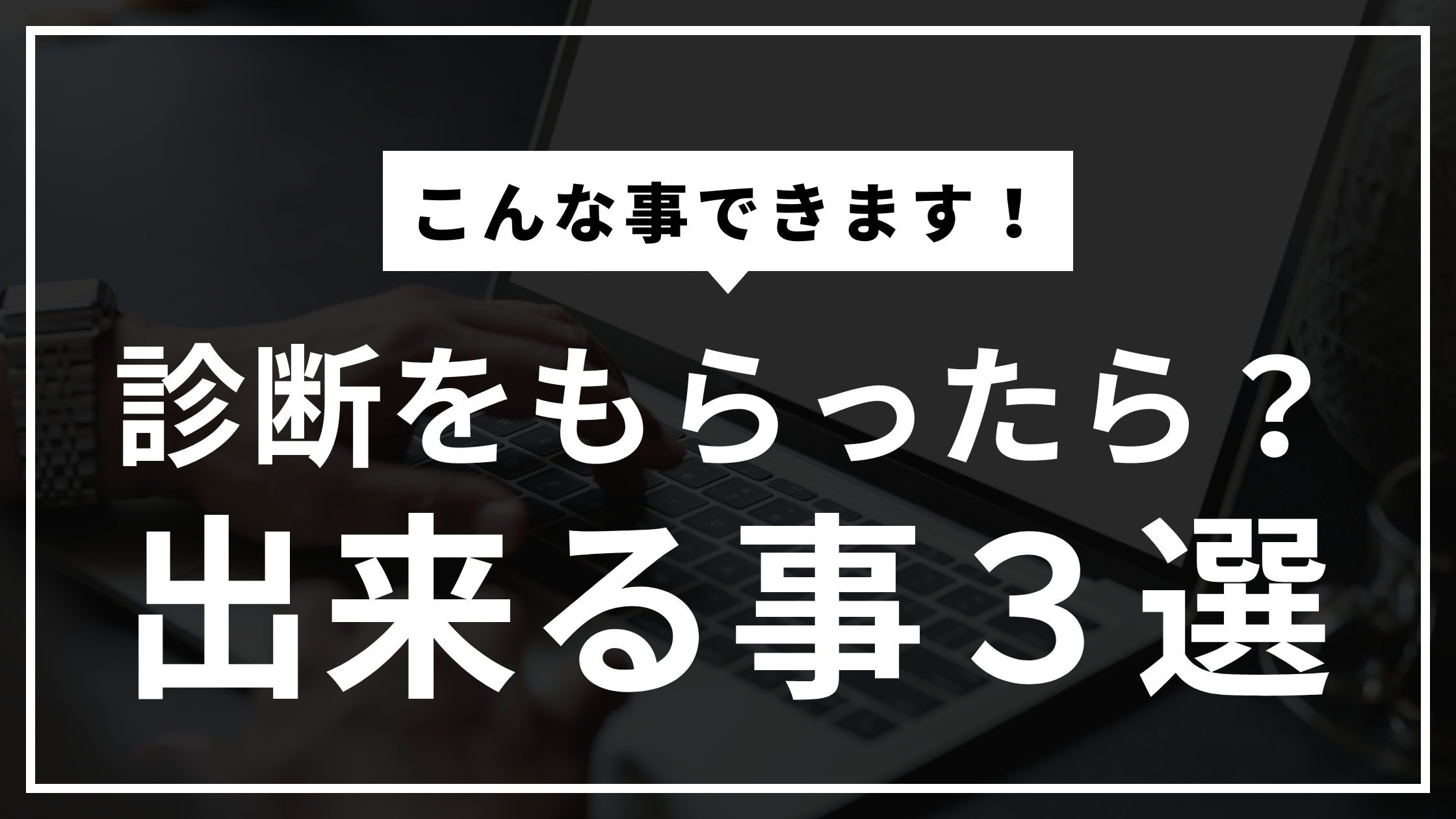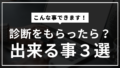こんにちは!おかーちゃんです。
「発達障害と診断されたけど、どんな行政の支援や手当が受けられるの?」
そう迷っているご家庭も多いはずです。
療育手帳の取得方法、児童手当・福祉サービス・支援制度など、行政で受けられるサポートを分かりやすく解説!
これを読めば「何をすればいい?どこに相談?」がスッキリ解決します。
ぜひご覧ください。
発達障害の診断を受けたら
以前のパートでも紹介していますが再度ご紹介します。
診断書があると出来る事
行政サービスを受ける事が出来でき、今後の療育や就学に向けて必要な物が手続きできます。
児童発達支援受給者証の取得方法(申請手順)
受給者証を取得するには、自治体の窓口で申請が必要です。
申請の流れ(一般的な手順)
- 自治体(市役所・区役所)に相談
- 住んでいる地域の「障害福祉課」「子ども家庭課」などの窓口で相談
- 必要書類を提出して申請
- → 申請時に以下の書類を提出します。
- 自治体の審査・面談を受ける
- 子どもの発達状況について聞き取り調査(自治体によっては面談なしのケースも)
- この時担当の相談員さんが決定します。相談員さん・役所の方・親子で発達状況や診断書を元に受給者証が必要か?それに伴って療育サービスがどういうのが必要か面談・相談する時間があります(1時間ほど)
- 受給者証の発行(約1〜2か月)
- 療育の「利用できる回数(週◯回)」が記載されている
申請から発行まで1〜2か月かかるため、早めの申請がおすすめです!
申請時に必要なもの
相談員さんとは?
相談支援専門員
障害福祉サービスを利用するための計画(サービス等利用計画)を作成し、継続的にサポートしてくれる。市区町村の指定を受けた事業所に所属。
発達障害者支援センターの相談員
発達障害に関する専門的な相談を受け付け、必要な支援や機関を紹介してくれる。各都道府県に設置されている。
市区町村の福祉相談員
福祉サービスの申請や地域の支援制度について案内してくれる。役所の障害福祉課などに所属。
相談員さんは通っている園に定期的に訪問し、普段の活動や生活の様子なども見に来てくれます。
「受給者証」と「療育手帳」の違い
受給者証と療育手帳の違いを簡単に説明します。
受給者証(児童発達支援受給者証)
「児童発達支援受給者証(じどうはったつしえん じゅきゅうしゃしょう)」とは、児童発達支援や放課後等デイサービスを利用する際に必要な証明書です。
この受給者証があると、自治体の補助を受けながら、療育や発達支援を低負担で受けることができます。
療育手帳
知的障害があることを証明する手帳で、障害の程度に応じて交付される。
税の控除や公共料金の割引など、さまざまな支援を受けられる。発達障害のみでは取得できず、知的障害がある場合に発行される。
簡単に言うと、「受給者証」は福祉サービス(例:児童発達支援、放課後等デイサービス等)を利用するための証明書です。
「療育手帳」は、知的障害があることを公的に証明し、さまざまな支援や割引などを受けるための手帳です(発達障害のみの場合は対象外です)。
これらは本人や家族が提示しない限り、周囲に知られることはありません。また、必要がなくなった場合はご自身のタイミングで返納することもできます。
児童発達支援受給者証の注意点
福祉サービス・支援制度の利用
相談員さんが決まったら支援・療育サービスを検討していきます。言葉やコミュニケーション、運動、社会性などの発達を促す支援を受けられます。
療育(児童発達支援・放課後等デイサービス)の利用
このような支援を受ける事が出来ます。
関連記事▶放課後等デイサービス(放デイ)とは?
児童発達支援とは?
児童発達支援(療育)を簡単に説明すると以下の内容の福祉サービスです。
- 対象:発達の遅れや特性に合わせたサポートが必要な未就学児(0~6歳)。
- 内容:
- 言葉や運動のトレーニング(言語療法・作業療法)
- コミュニケーションの練習(ソーシャルスキルトレーニング)
- 費用:自己負担は無料~少額(自治体負担あり)。
障害福祉サービス(自治体の支援)
- 移動支援(外出時の付き添い支援)

- 居宅介護(自宅での支援)
- 送迎サービス(園から療育施設への送迎)→これは地域によってサービス内容が違うので必ず確認しましょう!
医療費助成制度(自立支援医療)
精神科や発達障害関連の医療費負担が軽減される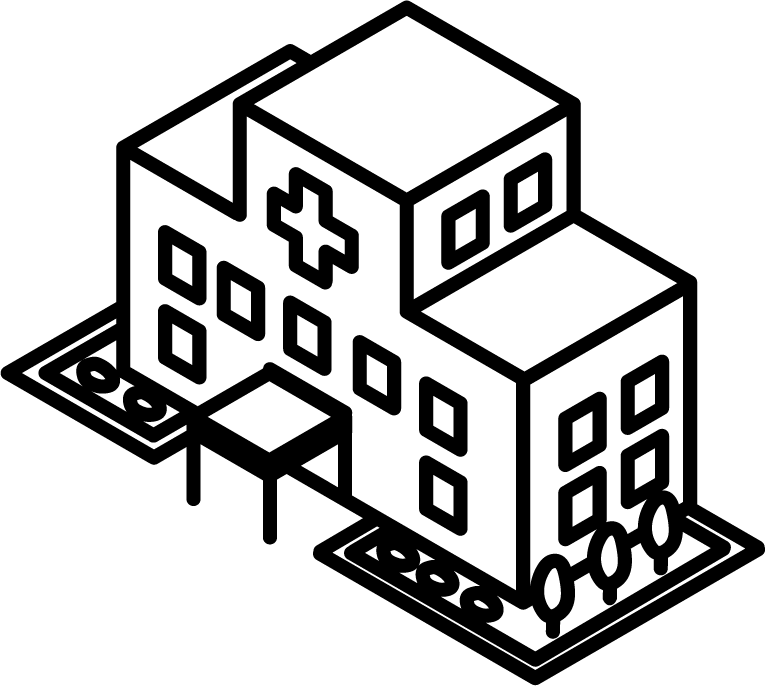
- 対象:発達障害で心療内科や精神科に通院する場合。
- 内容:診察や薬代の自己負担が1割になる。
相談・支援機関
- 市町村の福祉窓口
- 加配保育や療育の相談
- 発達障害者支援センター
- 生活全般の支援
- 児童相談所・子ども家庭支援センター
- 生活や育児の相談
- 保健センター(乳幼児健診)
- 発達相談、療育の紹介
まとめ
診断書が発行されたあとの行政手続きは、正直とても手間も時間もかかります。
でも、その一歩を踏み出すことで、お子さんにもご家族にも必要な支援やサポートが届きやすくなります。
「自分だけが大変なんじゃないか…」と感じている方も、同じ経験をした私がここにいます。
大変な時期こそ、一つひとつの手続きを一緒に乗り越えていきましょう。
この記事が少しでも不安や疑問を解消するきっかけになれば嬉しいです。
最後までご覧いただき、本当にありがとうございました。
あわせて読みたい関連記事
- 2025年スタート!最新の子育て支援制度まとめ【保存版】
- 発達障害の二次障害を防ぐ!改正支援法2025に備える最新サポート術
- 【発達障害診断後】保育園・幼稚園で受けられる支援と手続き徹底ガイド①
- 【保存版】療育とは?意味・種類・メリット・受け方まで体験談で徹底解説!
- 放課後等デイサービス(放デイ)とは?基礎知識と仕組み・メリット/デメリット
- 発達障害ペアレントトレーニングやり方完全ガイド|効果・無料オンライン講座・成功事例
- 5歳児健診で再検査・発達指摘…どうする?親がやるべき5つのステップ徹底解説
- インクルーシブ教育とは?日本と世界の最前線・最新制度を徹底解説