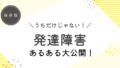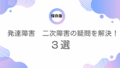こんにちは!おかーちゃんです。
「学校では大人しいらしい。でも家では何も話さないし、ずっと泣いてばかり…」
発達障害のある子どもは、周囲の理解が得られないまま生活することで、メンタル不調や不登校など“二次障害”を引き起こすことがあります。
わが家でも、息子の笑顔が見えなくなったとき「これは普通じゃない」と思いました。
この記事では、発達障害の子どもに多い二次障害のサインや、家庭でできる予防法・声かけをわかりやすくまとめています。
小さな変化に気づける親になるために、知っておきたいことを詰め込みました。
発達障害の二次障害とは?
「発達障害の二次障害」という言葉を聞いたことがありますか?
発達障害そのものが問題なのではなく、それによって引き起こされるストレスや環境とのミスマッチが原因で、うつ病や不安障害などの精神的な不調が起こることを「二次障害」といいます。
「生きづらい…」と感じる背景には、二次障害が関係していることも。
次では図を使って説明します。
二次障害とは?発達障害との関係
一次障害と二次障害の違い
まず、一次障害と二次障害の違いを整理しましょう。
| 一次障害 | 二次障害 |
|---|---|
| 発達障害そのものの特性(ADHD、ASDなど) | それによって引き起こされる精神的・身体的な不調 |
| 例:注意が散漫、こだわりが強い、人との距離感がわからない | 例:うつ病、不安障害、自己肯定感の低下、適応障害 |
発達障害自体は「脳の特性」ですが、二次障害は「環境や周囲の影響」で起こります。
つまり、周りの理解や適切なサポートがあれば、二次障害を防げる可能性があるのです!
二次障害が起こる原因
周囲からの否定や叱責
発達障害の特性を理解されず、怒られたり否定されることが続くと、自己肯定感が低下し、ストレスがたまります。正直、私の気持ちが余裕がなく、いっぱいの時モチ男への関わり方(間違った怒り方をしたり、モチ男の困りごとを解決しないまま一方的に怒ったり)が悪くモチ男のストレスが悪化してしまったことがありました。
環境のミスマッチ
自分に合わない環境にいることで、ストレスが積み重なり、二次障害につながります。
周囲との比較や自己否定
無理に周りに合わせようと頑張りすぎると、心が折れてしまいます。
二次障害を防ぐためにできること
自分の特性を理解する
発達障害の特性は人それぞれ。まずは自分の「得意」と「苦手」を知ることが大切です。
📌 チェックリストで自己分析
自分に合った対策を取ることで、ストレスを減らせます!
周囲に理解を求める
周りの人に「発達障害の特性」を伝えるだけで、対応が変わることも。
例えば…
発達障害を理解してもらうことは、二次障害の予防につながります!
無理に「普通」になろうとしない
「普通にしなきゃ」「みんなと同じようにしなきゃ」と頑張りすぎると、自分を追い込んでしまいます。
大事なのは「自分らしいやり方」を見つけること。
「普通」ではなく「自分に合った方法」を見つけることが大切です。
まとめ:二次障害を防ぐために
発達障害があっても、工夫次第で生きやすくすることは可能です。
「どうすれば自分が楽に生きられるか」を大切にしながら、無理のない生活を目指しましょう!
最後までご覧いただきありがとうございます。
参考リンク あわせて読みたい関連記事
- 【早期発見】発達障害の子供に見られる特徴と親が気づくポイント
- 発達障害の二次障害を防ぐ!改正支援法2025に備える最新サポート術
- “できない”から“できた!”へ ペアレントトレーニング成功のコツと親のサポート例
- 家庭でできる療育【実体験】④環境調整
- 合理的配慮・インクルーシブ教育よくあるQ&A
- 合理的配慮とは?学校で受けられる支援と対象・申請のポイント
- 【発達障害とは?】特徴・症状を3分で理解!/【発達障害×子育て】ペアレントトレーニング
- うちの子が“やる気になる”ABA的ごほうびリスト|発達障害・グレーゾーンにも効果的

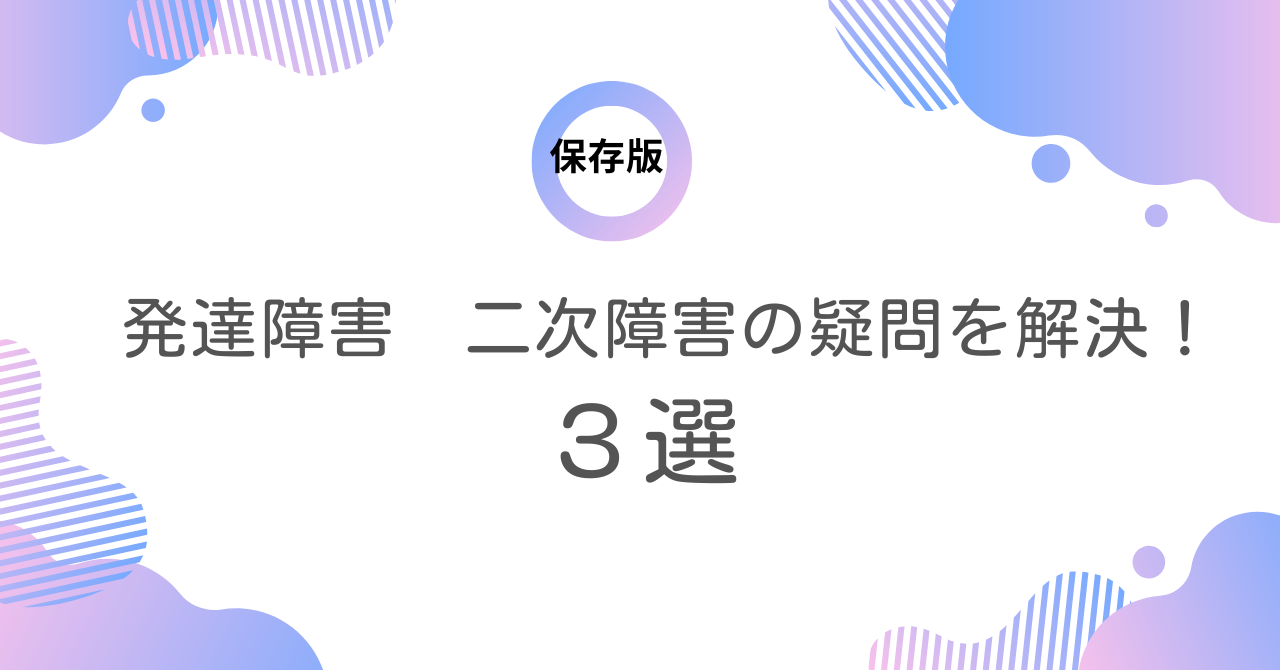
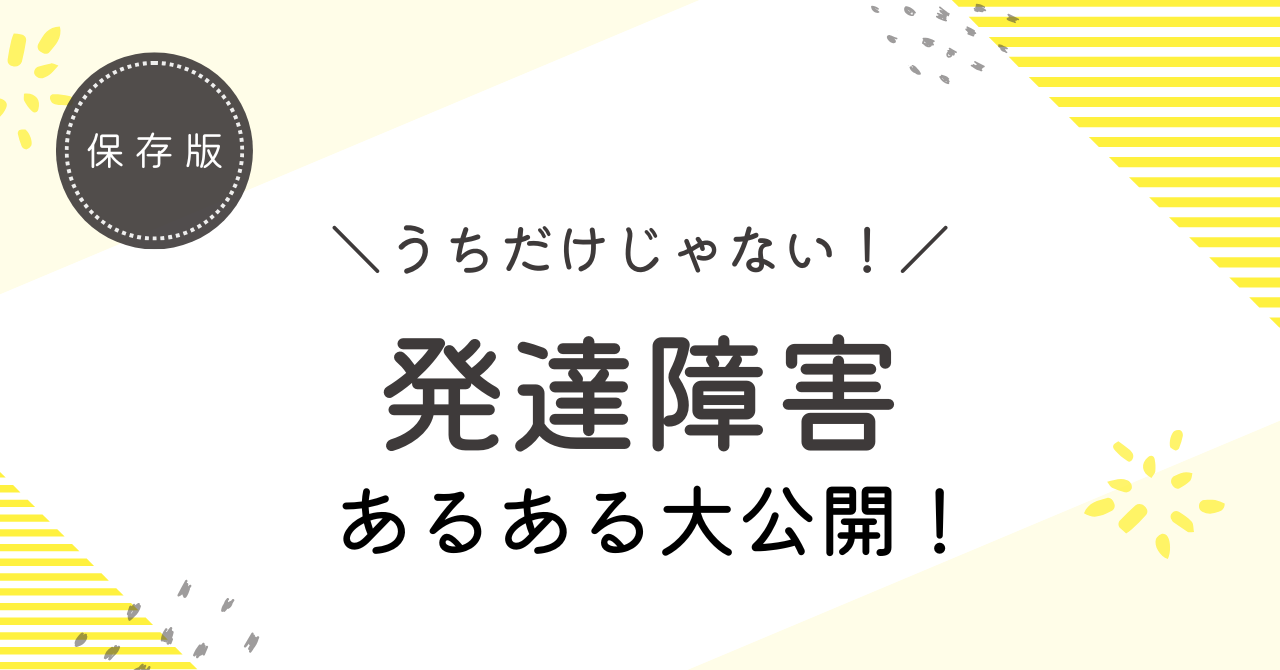
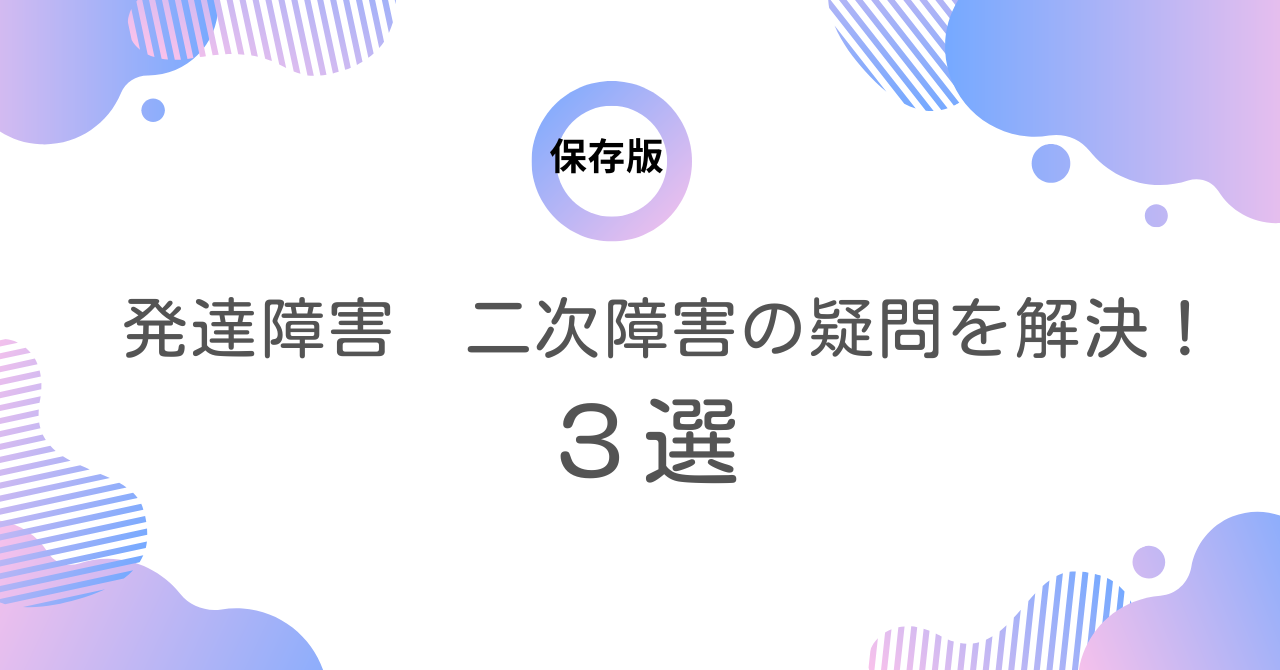
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/45f4aaf0.2ef1a49b.45f4aaf1.3931090f/?me_id=1213310&item_id=20265454&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8452%2F9784791628452.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)