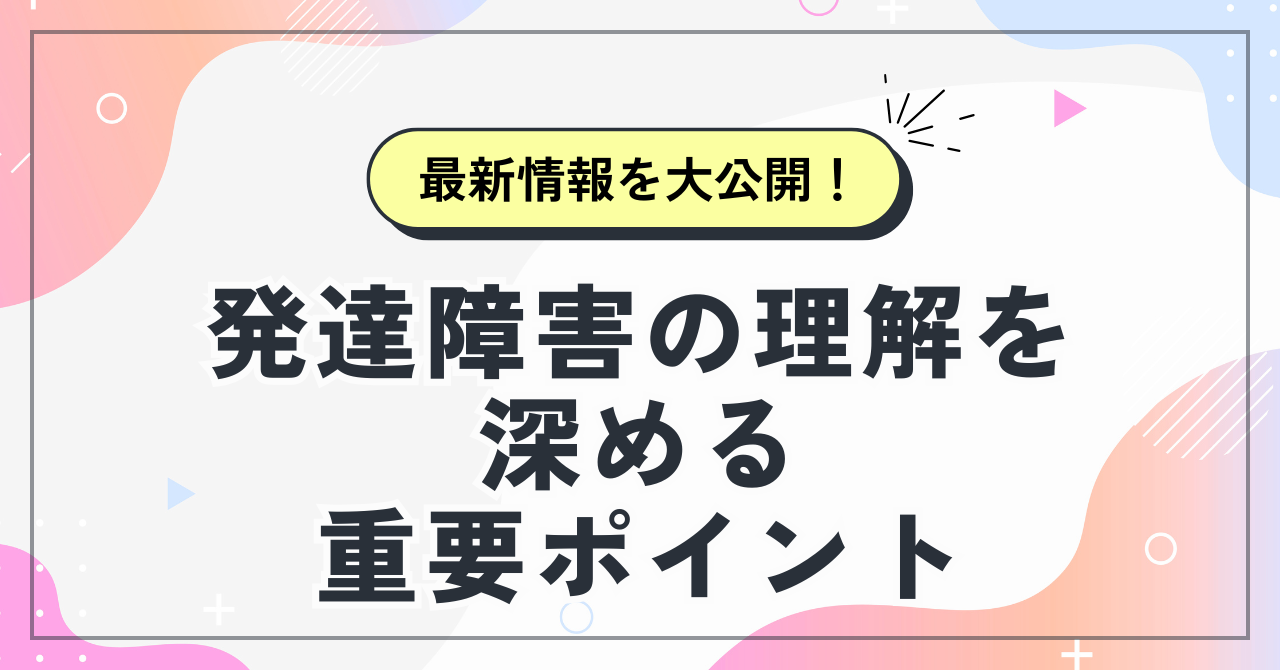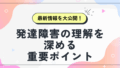こんにちは、おかーちゃんです!「このまま二次障害になったら…」そんな不安、ありませんか?
2025年4月から発達障害者支援法の改正が施行され、家族・学校・地域が協力して“二次障害を未然に防ぐ”ための体制が一気に強化されます。
本記事では、法改正の要点と家庭・学校・地域でできる具体的なサポート術を、実体験も交えて分かりやすく解説します!
「明日から何をすればいい?」が見つかる内容になっています。
発達障害の二次障害と改正支援法2025の要点
二次障害とは、発達障害そのものではなく、ストレス・不安・失敗体験の蓄積から「うつ」「不登校」「自己肯定感の低下」などを引き起こす状態のことです。
なぜ起きるのか?
例えば、感覚過敏で教室がまぶしい場合に無理して適応しようとすると、どんどんストレスが溜まります。でも「暗い場所で休憩」などの工夫でストレスは大きく減り、二次障害のリスクも下がります。
ポイントは「原因を知って早めに対処」。これだけで二次障害はグッと防げます。
関連記事▶二次障害の詳細・症状の例
参考リンク▶「くるみ」/自律神経失調症とうつの違いを症状・原因・診断治療で徹底解説
改正支援法2025年の新ポイント(表で解説)
| ポイント | 2024年まで | 2025年4月から |
|---|---|---|
| 基幹相談支援センター | 設置は一部自治体のみ | 全国で設置が努力義務化!相談体制が拡充 |
| 地域生活支援拠点 | 未整備の自治体も | 整備の推進で誰でも利用しやすく |
| 相談・支援のつながり | 一部途切れることも | 切れ目なく福祉・医療・教育が連携 |
家庭でできる!二次障害予防のサポート術
ストレスサインを早めにキャッチ
「寝つきが悪い」「好きな遊びをしなくなった」「朝、支度に時間がかかる」などの変化は要注意サイン。日記アプリやシールカレンダーでお子さんの気分を“見える化”して、ご家族みんなで情報共有を!
ルーティンと視覚支援で安心感を演出【実体験エピソード】
うちではタイムタイマーを導入し、ゲームやYouTubeの時間を「見てわかる形」に決めています。だらだら続けると気持ちの切り替えが難しくなり、イライラしやすいので、時間を区切ることで本人もストレスなく過ごせるようになりました。
「見通しが立てられないこと」が強い不安やストレスの元になるため、早い時期から視覚的なツールを活用してきました。今ではモチ男も自然にタイマーを使いこなし、家庭の雰囲気も落ち着いています。
同じ悩みがある方はぜひ一度タイムタイマーなど視覚支援ツールを使ってみてください。
参考:Amazon|タイムタイマー
改正支援法を活用!相談支援の手続きガイド
相談支援専門員の活用ポイント:
- 市町村の福祉課に予約
- ヒアリングシート提出
- サービス等利用計画の作成支援を受ける
専門員が福祉・医療・教育の調整役として一緒に動いてくれるので、「どこに相談したらいい?」と迷わずOK。
詳細:発達障害と診断されたら~行政の相談・手続きまとめ
地域生活支援拠点のメリット
短期入所・緊急受け入れ・家族支援のワンストップ拠点として機能します。夜間や休日の相談窓口も増えるため、保護者も安心!
学校と連携して二次障害を防ぐ方法
学校では個別の教育支援計画(IEP)や合理的配慮が重要。例えば授業中にイヤーマフOK、暗い場所で休憩OKなど、「本人が理解されている」と感じられる環境が二次障害の予防につながります。
保護者面談では「うちでの成功事例」や「困りごと」を具体的に共有し、先生と共通認識を作りましょう。
地域支援&制度をフル活用するコツ
基幹相談支援センターを徹底活用!市町村をまたぐ支援もスムーズ。登録後は医療・福祉・教育が一体となったサポートプランがもらえます。
公式情報:e-Gov|発達障害者支援法
またピアサポート(同じ悩みを持つ家族同士の交流)やLINE・チャットなどのオンライン相談窓口も増えています。「孤独になりやすい」子育てを一緒に乗り越えましょう!
まとめ:最新制度と連携で二次障害を防ごう!
改正支援法2025年で相談体制が大幅アップ!家庭・学校・地域が連携することで二次障害は大きく防げます。「困ったら早めに相談」が合言葉!タイムタイマーや視覚支援はすぐ使える実践術です。
公式情報&実体験エピソードを参考に、今すぐできる工夫から始めよう!
最後までご覧いただきありがとうございます!
参考リンク あわせて読みたい関連記事
- 幼児の二次障害・グレーゾーン関連記事/発達障害・グレーゾーン児の就学前手続き完全ガイド|放デイ・学童・IEPの準備リスト/IEP(個別支援計画)とは?意味・目的・メリット/【就学前検診とは?】基礎・流れ・チェックポイント/就学前がカギ!合理的配慮の意味と今すぐできる支援・チェックリスト