こんにちは!おかーちゃんです。
今回は家庭で出来る療育、スケジュール管理の実体験・おススメアイテムをご紹介していきます。ぜひご覧ください。
発達障害の子どもにスケジュール管理が必要な理由
発達障害の子どもにとって、時間の流れを理解することは簡単ではありません。急な予定変更が苦手だったり、何をすればよいか分からず不安になったりすることが多いです。
そのため、スケジュールを目で見て分かる形にすることが大切です。
発達障害の特性と時間の感覚
発達障害の子どもは、時間の流れを感じることが難しい場合があります。
このような特性があるため、予定が決まっていないと不安を感じることが多いです。スケジュールを決めておくことで「次に何をするのか」が分かり安心して過ごせます。
実際に時間管理は難しいです。時計が読めるまでは5分はこのぐらい!という体感を覚えさせるのには苦労しました。このタイマーは目で決められた時間を見ながら、あと5分はこれぐらい?という感覚も身につけられたのでおススメです!
スケジュール管理で生活が安定する理由
スケジュールを管理すると以下のような効果があります。
スケジュールを決めておくことで、子どもが安心して過ごせる環境を作れます。
家庭でできるスケジュール管理の基本
家庭でスケジュール管理を取り入れることで、子どもの生活がスムーズになります。
シンプルで分かりやすいスケジュールの作り方
子どもが理解しやすいスケジュールを作るには以下のポイントを意識しましょう。
- 文字よりも絵や写真を使う:視覚的に分かりやすくする
- シンプルな表にする:情報が多すぎると混乱しやすい
- やることの順番を決める:何を先にするかを明確にする
例えば「朝起きる」「顔を洗う」「朝ごはんを食べる」など順番をイラストで示すと分かりやすくなります。
子どもが自分で確認できる工夫
スケジュールを親が管理するだけでなく、子どもが自分で確認できるようにすると主体的に行動しやすくなります。
- 見やすい場所に貼る:冷蔵庫や部屋の壁などすぐに見られる場所にする
- できたことをチェックできるようにする:シールやマグネットで進み具合を確認できると達成感が生まれる
- 一緒に作る:自分で作ったスケジュールなら興味を持ちやすい
このような工夫をすると、子どもが自分で予定を確認する習慣がつきます。
前回もご紹介しましたが、文字+絵になっているので使いやすいです!
発達障害の子どもに合ったスケジュールの具体例
実際にどのようなスケジュールを作ればよいのか、具体例を紹介します。
1日の流れを見える化する方法
一つずつ流れを示すことで「次に何をするのか」がはっきりします。うちでは画用紙に書いて見やすい位置に張り付けています!
⇒朝ver.帰宅後ver.長期休暇ver.などその時その時で必要なものを作成しています!
ポイントは細かく決めない!やる事(やる事必須)だけを書く。細かく決めると後ほどでも説明しますが逆に整理できずズレが生じたときにパニックになりやすいです…
予定変更があるときの伝え方
発達障害の子どもは予定が変わると戸惑うことがあります。事前に伝える工夫をするとスムーズに対応できます。
- 変更が分かった時点で伝える(突然の変更は避ける)
- 理由を説明する(「今日は雨だから、外遊びはお休み」など)
- 変更後の予定を具体的に示す(「外遊びの代わりに、お絵かきをしよう」)
家族と一緒に取り組むスケジュール管理
スケジュール管理は子ども一人だけでなく家族みんなで共有するとより効果的です。
家族と協力しながら取り組むと子どもも安心して生活できます。我が家はカレンダーに全員の予定や園・学校行事を分かりやすく記載していました。ポイントはシンプルかつ見やすいもの!です。
スケジュール管理の効果を高めるコツ
スケジュール管理を長く続けるためにはいくつかのコツがあります。
無理なく続けるためのポイント
- 最初から完璧を目指さない(少しずつ調整する)
- 子どもが飽きないように工夫する(好きなキャラクターを使うなど)
- やりすぎない(細かすぎるスケジュールは逆効果)
ごほうびを活用してやる気を引き出す
楽しみながら続けることで、スケジュール管理が習慣になります。
スケジュール管理を試してみた!体験談と変化
実際にスケジュール管理を取り入れた体験談を紹介します。
実際にやってみた結果と気づき
- 朝の準備がスムーズになった
- 子どもが自分から行動できるようになった
- 親子のストレスが減った
⇒モチ男にとって良かったと感じるのは、見通しが立てられるようになり予定変更時のパニックが減った事です。
それによって私も癇癪のストレスが減りお互い精神的に余裕ができました。また自分から行動することによって、できる事が増えたからこそ自信に繋がっていました。
うまくいかなかったときの対処法
- 子どもに合った方法に調整する
- 無理なくできる範囲から始める
- 試行錯誤しながら改善する
⇒最初から全部は上手くいかなかったです!色々試して工夫して何回かやっている内に『あ、これが合っている!』とわかる事が多かったです。
なので最初から無理のない範囲でできる事からやってみましょう!
まとめ|スケジュール管理で発達障害の子どもをサポートしよう
スケジュール管理は発達障害の子どもが安心して過ごすために役立ちます。無理のない範囲で、楽しみながら取り入れてみましょう!
最後までご覧いただきありがとうございます。

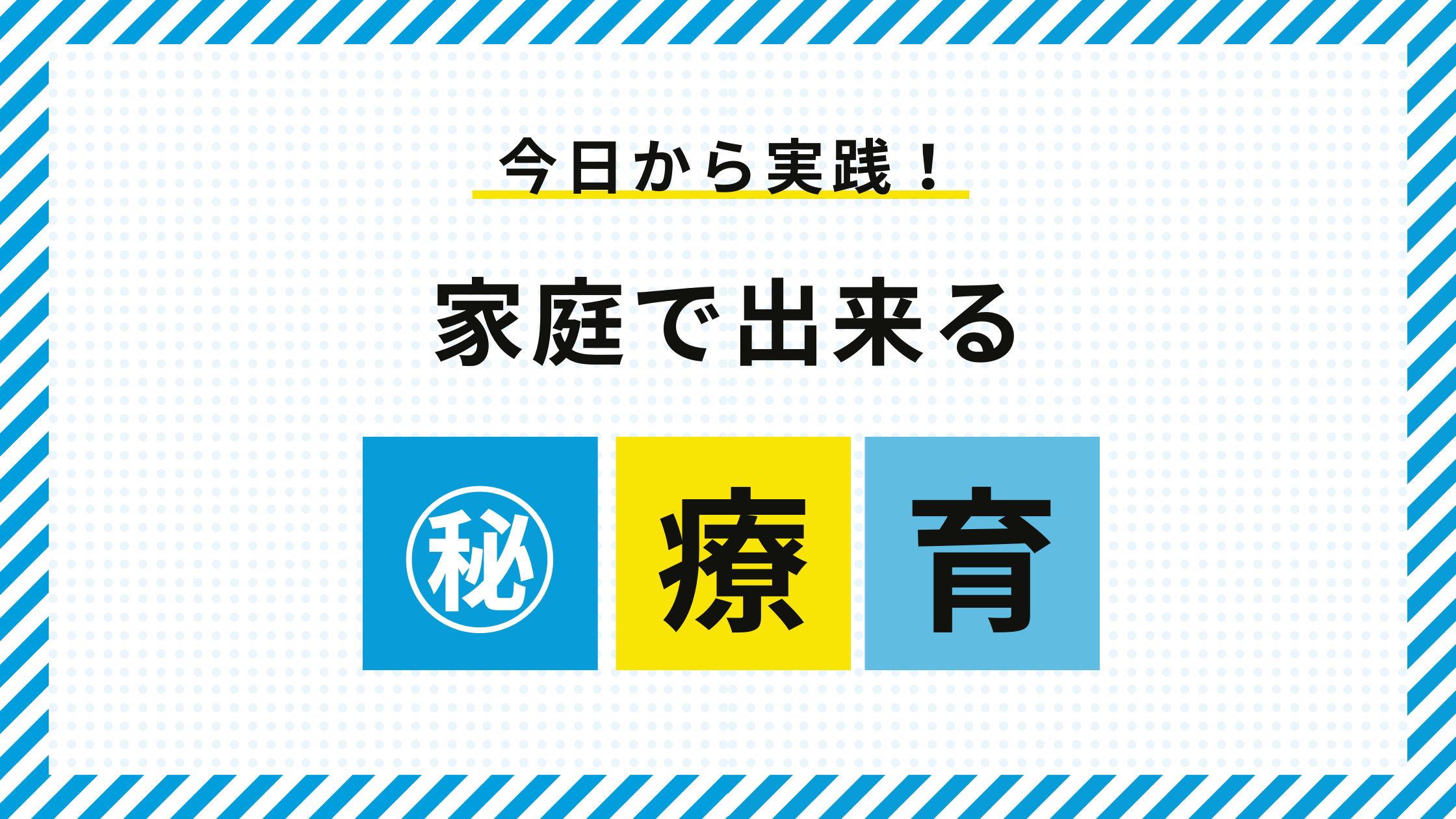
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/45f4aaf0.2ef1a49b.45f4aaf1.3931090f/?me_id=1213310&item_id=21311756&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F7080%2F9784418247080_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4689223a.e2691c08.4689223b.bb0f1949/?me_id=1314291&item_id=10000059&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fenishido%2Fcabinet%2F10837193%2F10857682%2Fimgrc0127133432.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
