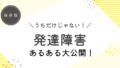こんにちは!おかーちゃんです。
「癇癪(かんしゃく)がひどくて毎日くたくた…」──そんなお悩みを抱える親御さんに向けて、発達障害のある子がなぜ感情を爆発させるのか、そしてどう付き合えばよいのかを分かりやすくまとめました。記事の最後に公的支援・相談窓口へのリンクも掲載していますので、ぜひご活用ください。
癇癪とは?発達障害の子どもの特徴
癇癪とは、怒り・不安・混乱などの強い情動が一気に噴き出す状態を指します。発達障害のある子どもは次のような特性から癇癪を起こしやすい傾向があります。
癇癪を引き起こす5つの主な原因
思い通りにいかないとき
「こうなるはず!」というこだわりが崩れるとパニックになりやすい子が多いです。スケジュールがずれたり、他者の行動が予測外だったりする場面で爆発が起こりがちです。
音や光など環境刺激が強いとき
掃除機の低周波音や蛍光灯のちらつきなど、周囲が気にしない刺激でも本人には強烈。刺激が蓄積すると「もう無理!」と叫ぶように癇癪が出ることもあります。
要求を言葉にできないとき
語彙が少ない年齢ほど言語化のハードルが高く、要求不満がイライラへ直結します。AAC(絵カードやジェスチャーなど代替コミュニケーション)の導入が有効です。
予定変更でびっくりしたとき
「公園に行くはずが雨で中止」などの急な予定変更は大きな不安を呼びます。事前に「雨だったらお家で○○しよう」と複数シナリオを共有すると安心感が高まります。
疲労や空腹で我慢できないとき
学校や園でエネルギーを使い果たし、帰宅後に燃料切れで爆発するケース。血糖値の低下や睡眠不足も引き金になるため、休息と栄養を意識しましょう。
癇癪が起きたときの正しい対応ステップ
- 安全確保 … 周囲に割れ物や危険物がないか確認。
- クールダウン … 強制せず、静かな場所で見守る。
- 共感の言語化 … 落ち着いたら「○○が嫌だったね」と気持ちの翻訳をする。
- 振り返り … 図や絵カードで「どうすれば良かった?」を一緒に整理。
- 次に活かす … 成功体験を作り「できた!」を褒める。
※ 国立特別支援教育総合研究所は「気持ちを十分に受け止め、落ち着くまで冷静に待つ」ことの重要性を提唱しています。
家庭でできる癇癪の予防策
関連記事▶療育アイテム5選 効果抜群!実際に使ってよかった厳選グッズ
親がつらいときの相談先・リフレッシュ方法
癇癪が続くと親御さんも心身ともに疲れてしまいます。ひとりで抱え込まないことが何より大切です。
公的な相談窓口
同じ立場の親とつながる
ペアレントトレーニングや親の会に参加すると、「わかってくれる仲間」に出会え、最新の支援情報も得られます。たとえば発達障害専門の家庭教師サービス キズキ家学 では無料相談を実施しています。
リフレッシュの具体例
「子どもの癇癪は親のせいではありません」あなたはもう十分に頑張っています。困ったら早めに相談し、安心できるサポート網を作りましょう。
最後までご覧いただきありがとうございます。
参考リンク あわせて読みたい関連記事
- 国立特別支援教育総合研究所|かんしゃくを起こすのですが…
- キズキ家学|発達障害による小学生の癇癪 親ができる7つの対応
- LITALICO発達ナビ|癇癪と発達障害の関連性
- 発達障害者支援センター(全国一覧・厚生労働省)
- 国立特別支援教育総合研究所(NISE)
- 最新おすすめ支援ツール&アプリ5選【効果・使い方も解説】/発達障害の子どもが謝れない理由と親のサポート完全ガイド/こども誰でも通園制度を徹底解説

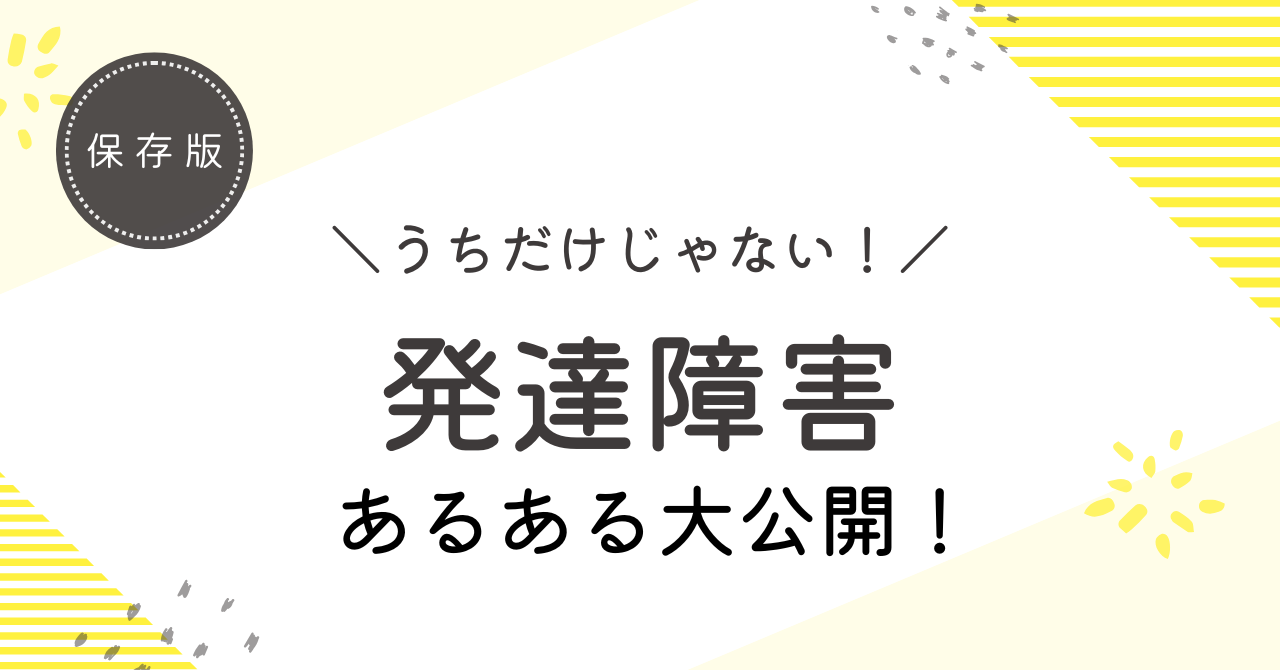
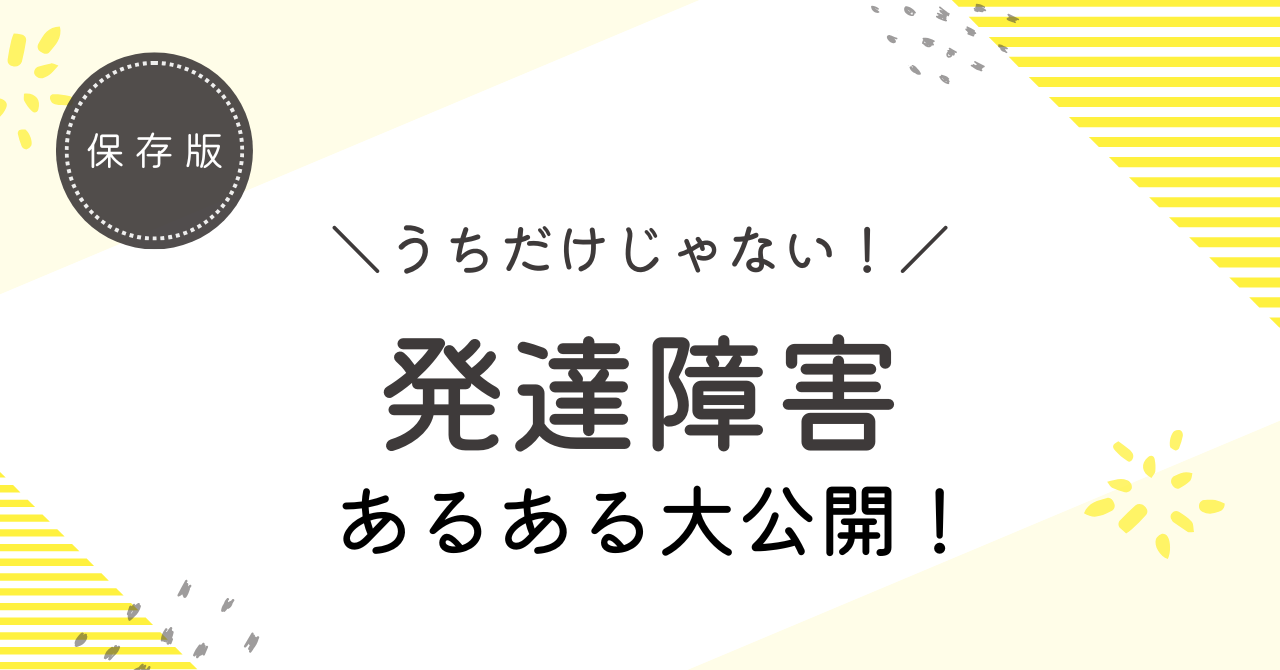
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e40c1ac.b1a5e20c.4e40c1ad.cae804f7/?me_id=1378452&item_id=10000005&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_gold%2Fproe-shop%2Fcommon%2Fimg%2Fjumpy%2Fi01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)