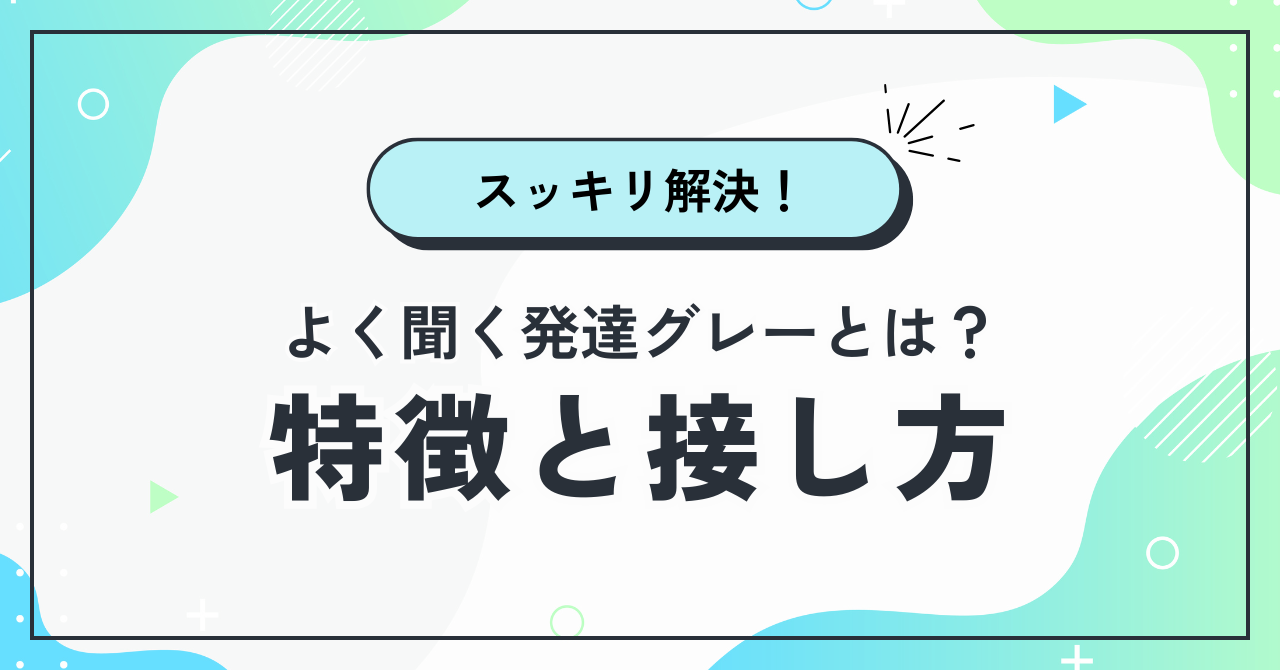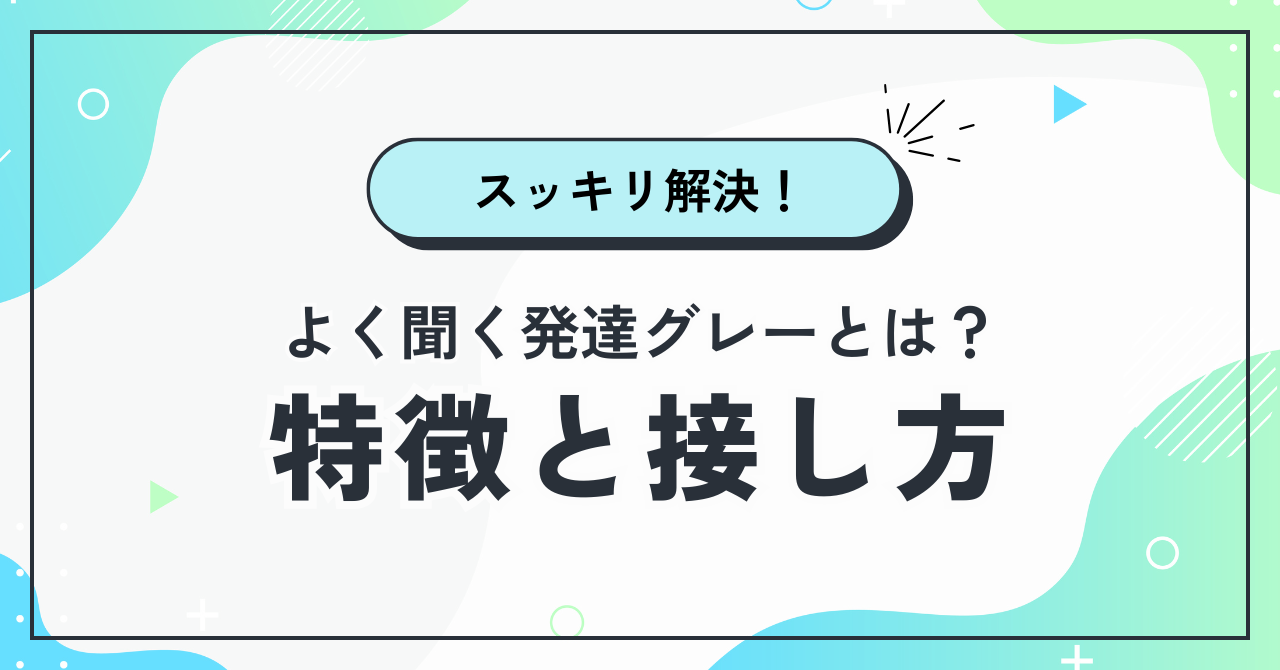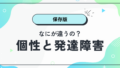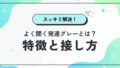こんにちは!おかーちゃんです。
「発達グレーって何?」「診断がつかないのに困ってる…」
そんな悩みを感じている方へ、発達障害グレーゾーンの意味・特徴・困りごと・親のサポートまで実体験つきでやさしく解説します。
発達障害グレーゾーンとは?意味と特徴をやさしく解説
発達障害グレーゾーンは、発達障害の診断基準には達しないけれど、特性が強く日常で困りごとが多い子どもを指します。
いわゆる「あと一歩で診断」「検査でボーダー」というケースも多いです。
| 項目 | グレーゾーン | 発達障害(診断済) |
|---|---|---|
| 診断基準 | 基準未満(あと一歩で基準) | 基準を満たす |
| 支援の受けやすさ | 支援が受けにくいことも | 支援・制度が利用しやすい |
| 困りごと | 日常や学校生活で出やすい | 日常や学校生活で出やすい |
例えば、発達検査で「あと1点で診断」という場合も該当します。
モチ男もまさにあと1点足りず“発達グレー”の診断に。
診断が出なくても日常や集団で困ることがあるのが最大の特徴です。
▶関連記事/初めての発達検査体験談
発達障害グレーゾーンの主な特徴・よくあるサイン
サイン別チェックリスト
| シーン | よくある困りごと |
|---|---|
| 学校・集団 | 授業や活動についていけない、集中が続かない、注意されやすい |
| 家庭 | こだわりが強い、予定が変わると混乱、身支度や片付けに時間がかかる |
| 友人関係 | 気持ちがわかりにくい、ケンカやトラブルになりやすい |
なぜ診断がつかない?グレーゾーンの理由と注意点
発達障害はDSM-5などの診断基準を満たした場合に診断されますが、
グレーゾーンは「あと少し」で診断に届かないため、支援が受けづらく、困りごとが放置されやすい現状があります。
【体験談】モチ男も“発達グレー”でした
うちのモチ男も検査で「あと1点…」でグレーゾーン判定に。
診断がないと支援の枠に入りにくく、保護者も「どうして?」と悩みました。
でも、困っているのは子ども本人。
「できない」を責めるより、どうすればラクになるか一緒に考え、安心できる環境づくりを大事にしました。
グレーゾーンの子どもへの上手な接し方・親ができるサポート
子どもの気持ちを大切にする
まずは、「困っているのは子ども自身だ」という気持ちを忘れずに寄り添いましょう。
このような対応で、子どもは「わかってもらえた」と感じることができます。
気持ちを言葉にする事が苦手な子も多いです。(モチ男も苦手です。それが原因でストレスになり癇癪に繋がる事も多々あります。)
安心できる環境を作る
グレーゾーンの子どもたちと関わるときは、ちょっとした工夫で安心を与えることができます。日常の中で安心できるルールや工夫を取り入れてみましょう。
親子ともに「困りごとを責めない」子どもの「できた!」を増やしていく雰囲気を大切にしましょう。
支援やサポートが必要な場合は、自治体や専門機関にも早めに相談できます。
【困ったら相談】外部リンク・頼れるサポート
困った時は一人で抱えず、早めに相談しましょう。
厚生労働省|発達障害情報・支援センター
まとめ|グレーゾーンでも安心して育つために
理解とサポートがあれば、グレーゾーンの子も自分らしく成長できます。
最後までご覧いただきありがとうございます。
参考リンク あわせて読みたい関連記事
- 厚生労働省|発達障害情報・支援センター
- 「個性」と「発達障害」の違い
- 初めての発達検査体験談
- 【2025最新】5歳児健診とは?発達・成長のポイント・流れ・Q&Aを徹底解説
- 発達障害の子どもが癇癪を起こす理由と対処法【保存版】
- 発達障害の個別支援6つの方法|家庭でできる療育