こんにちは!おかーちゃんです。
5歳児健診で「再検査です」「発達で気になる点があります」と言われると、びっくりして不安になる方がとても多いです。でも、5歳というのは個人差が大きい時期で、指摘されたからといって“問題がある”とは限りません。
この記事では、再検査になった時にまず確認したいこと・相談できる場所・家庭でできる準備をわかりやすくまとめました。今できることを整理しておけば、次のステップが見えやすくなります。無理なく進めていきましょう。
5歳児健診で再検査になる理由とは?
再検査の理由はさまざまですが、5歳は成長差が特に大きい時期です。次のような理由で“念のため”確認される場合もあります。
再検査と言われた時にまず確認すること
健診直後は不安になりやすいので、まずは状況を整理するのがおすすめです。
健診で聞いておくと安心なこと(言いにくいけど大事)
- 園ではどんな配慮がされていますか?
- 家ではどんな場面で困りやすいですか?
- 支援サービスを使う場合の流れは?
- 様子見の期間はどれくらいですか?
再検査後の流れ|どんなパターンがある?
結果を聞いたあと、次の3つのルートに分かれることが多いです。
- 様子見 → 数ヶ月〜半年後に再チェック
- 発達支援の利用(ST/OT/心理)
- 医療機関で精査(必要に応じて)
「要観察」「要受診」とは?その意味と基準
健診で「要観察」や「要受診」と判定される理由はさまざまですが、「深刻な問題」と限らず、“成長の個性や少し気になる点”にも出る場合が多いです。
医師や保健師は、子どもの成長を見守るために“念のため”チェックを勧めることも。
「うちの子だけ?」と悩みすぎず、専門家の目で再確認するチャンスと前向きに受け止めてOK!
気になる子の特徴|具体例があると伝わりやすい
健診では「普段の様子」を伝えることがとても大切です。
二次健診・発達相談までの流れとポイント
- 自治体・市区町村から「二次健診」「個別相談」「発達支援センター紹介」などの案内が届く
- 再度、子どもの行動や発達の様子を家庭・園でもメモしておく(健診シートや日記が役立つ)
- 指定された会場や専門機関で二次健診を受ける
(医師・心理士・保健師などが丁寧に対応してくれる) - 必要に応じて、療育・発達支援・特別な指導への案内や手続きが始まる
相談先|どこに相談すればいい?
専門家と話すことで、モヤモヤがスッキリして安心できます。相談先は次の通りです。
- 市町村の発達相談(心理師・保健師)
- 子ども発達支援センター
- 児童精神科・小児科(要予約)
- 園の担任・加配の先生
親ができるチェックリスト&不安解消のヒント
【親の声】
「健診で“個性の範囲”と言われたけど、様子見ではなく支援につながって良かった」
「必要ならセカンドオピニオンや他の相談窓口も利用してみて」
家庭でできる「次回までの準備」
無理に練習させる必要はありません。日常の様子を少し整理するだけでOKです。
よくある悩み・SNS体験談集
💡 発達が気になる子に役立ったアイテム
👉 気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。
まとめ|「再検査」でも焦らない。5つのステップで前に進もう
5歳児健診で「要観察・再検査・発達の指摘」があっても、深呼吸。2025年の最新体制では、保護者が相談しやすく、次の支援へつながりやすい仕組みが整いつつあります。
大切なのは、感情だけで動かずに5つのステップで落ち着いて進めること。必要ならセカンドオピニオンや自治体の窓口も積極的に活用しましょう。
「今できる小さな一歩」を積み重ねることが不安解消の近道。ひとりで抱えず、専門職・自治体・学校とつながりながら、子どもに合うサポートを一緒に探していきましょう。
最後までご覧いただきありがとうございます。
【公式・外部リンク/相談窓口まとめ】
関連記事・就学・支援につなげる情報
- 発達グレーの進路選び|迷ったとき親がやるべきこと/発達障害の年齢別発達目安表【完全版】/発達グレーって何?診断される前に知りたい特徴と相談の流れ/【第1弾】5歳児健診の基本と最新情報|流れ・チェック項目/合理的配慮の義務化でどう変わる?2025年最新解説/5歳児健診で「発達が気になる」と言われたら?

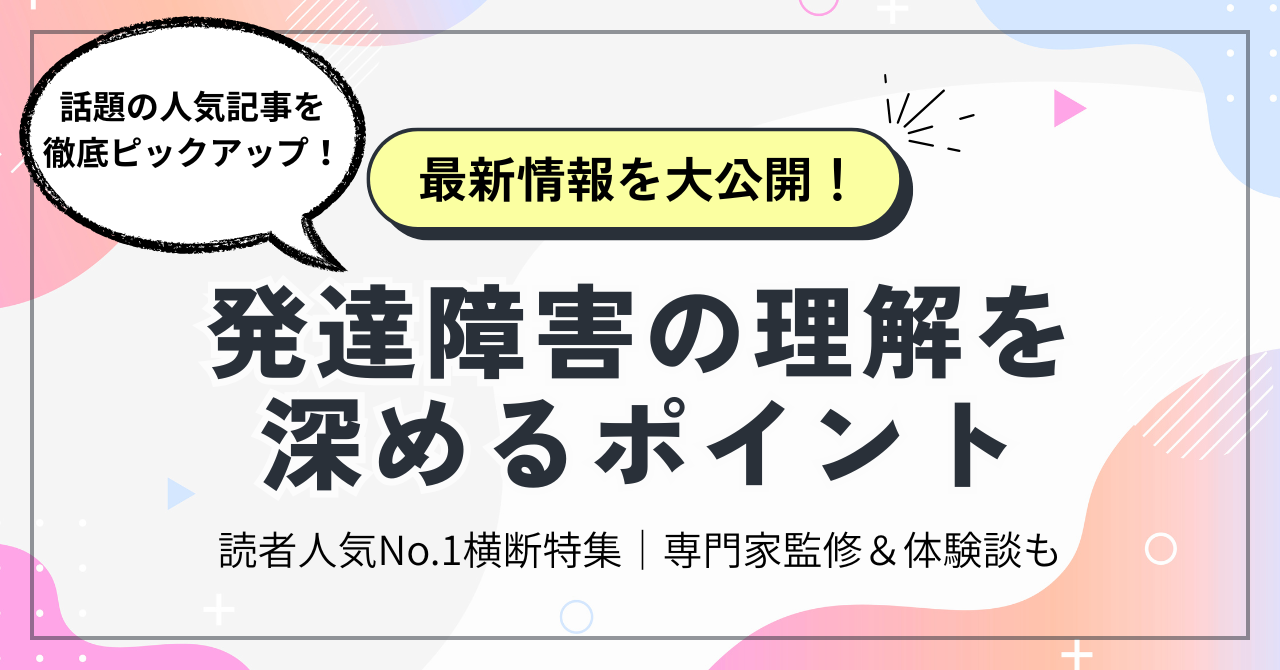
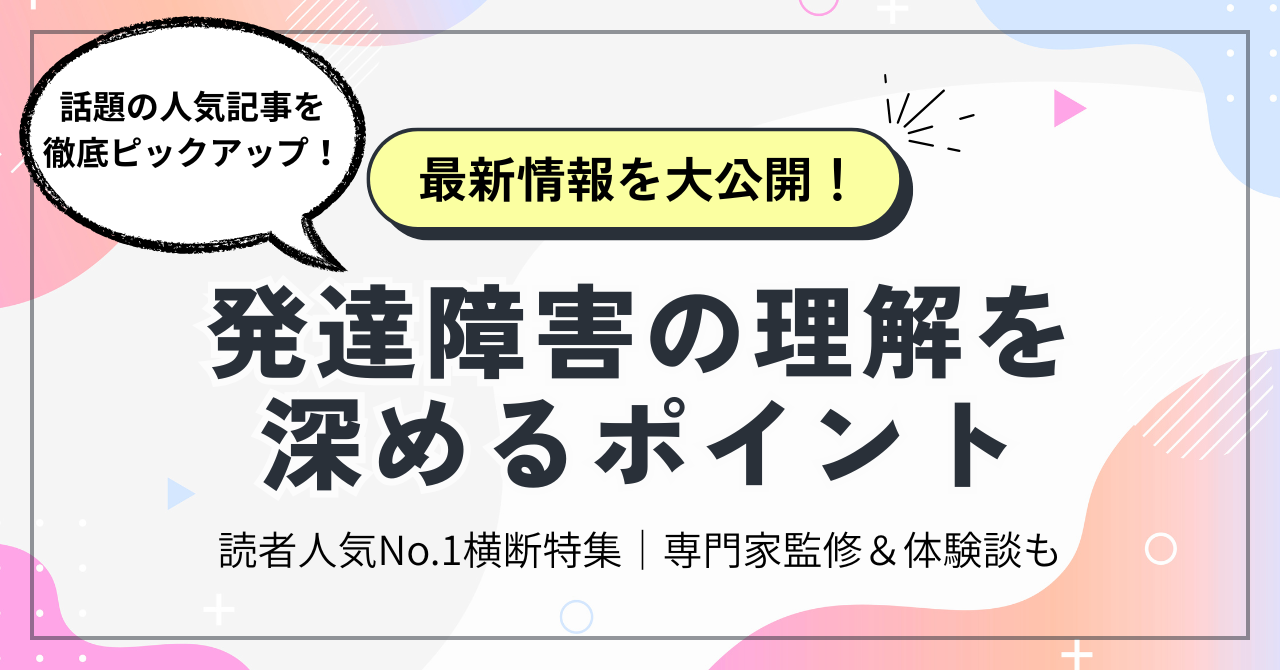
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4ab6ce69.3882e241.4ab6ce6a.a4337954/?me_id=1422375&item_id=10000097&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Flumeland%2Fcabinet%2Ftrip%2Ftrip_020%2Ftrip-0202_00.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)


【体験談】
「再検査と聞いて不安だったけど、保健師さんが“よくあるケースですよ”と教えてくれて気持ちが楽になった」
「相談の場で“兄弟の時もこうだった”と話したら、“個性として見守りましょう”と言われて安心できた」