こんにちは!おかーちゃんです。
「5歳児健診だけで十分?発達検査も受けた方がいいの?」
保護者からよくあるこの疑問。
この記事では5歳児健診と発達検査の違い・併用のメリット、それぞれの流れや費用、就学・支援への活かし方まで2025年最新情報で分かりやすく解説します!
モンテッソーリ教育・レッジョ・エミリア教育を知り尽くした オックスフォード児童発達学博士が語る 自分でできる子に育つ ほめ方 叱り方 3歳 〜 12歳 の子ども対象 | 島村 華子 |本 | 通販 | Amazon
Amazonで島村 華子のモンテッソーリ教育・レッジョ・エミリア教育を知り尽くした オックスフォード児童発達学博士が語る 自分でできる子に育つ ほめ方 叱り方 3歳 〜 12歳 の子ども対象。アマゾンならポイント還元本が多数。島村 華子作品...
5歳児健診と発達検査はどう違う?
| 5歳児健診 | 発達検査 |
|---|---|
| ・自治体が全員に行う“スクリーニング” ・保健師・小児科医が発達・健康の全体像をチェック ・所要時間は30分前後、無料 | ・気になる場合に希望・紹介で受ける“専門検査” ・心理士や専門医が個別に評価(WISC、田中ビネー等) ・1~2時間かけて詳細に診断/自治体や医療機関で実施 |
POINT! 健診=全員の「発見」「入口」/発達検査=「個別」「深掘り」が大きな違い!
両方受けるメリット・デメリット
発達検査の主な種類・流れ・費用
| 検査名 | 主な内容 | 対象年齢 | 費用 |
|---|---|---|---|
| WISC(ウィスク) | 知的・言語・動作・記憶など多角的評価 | 5歳半~16歳 | 無料~数万円(自治体・医療機関による) |
| 新版K式発達検査 | 認知・言語・社会性・運動など | 0歳~成人 | 同上 |
| 田中ビネー知能検査 | 知的発達の総合評価 | 2歳~成人 | 同上 |
POINT! 自治体の紹介・保健所・発達支援センター経由だと“無料”で受けられることも多い。迷ったら窓口に確認を!
検査結果の活かし方|進路・支援級・通級につなげるために
【保護者の声】
「検査を受けたことで“苦手なだけじゃない”部分に気づけて、本人への接し方も前向きに変わった」
まとめ|5歳児健診と発達検査、両方の視点で安心の就学準備を
5歳児健診は「スクリーニング(ふるい分け)」、発達検査は「詳細な評価」という違いがあります。
健診では気づきにくい発達特性を拾い上げ、発達検査では具体的な強み・課題・必要な配慮が数値や指標で明らかになります。
両方を組み合わせて受けることで、就学前に子どもに合った支援や環境を整える準備がしやすくなります。
とくに2025年からは合理的配慮の義務化やインクルーシブ教育の推進により、検査結果は学校との話し合いの根拠にもなりやすくなっています。
「うちの子は大丈夫かな?」と不安に感じたら、まずは自治体の健診を受け、必要に応じて発達検査を追加。
それが子どもにとっての最適なスタートラインを引く大切なステップとなります。
最後までご覧いただきありがとうございます。
【強め外部リンク・実例コラム】
関連記事・体験談リンク
- 5歳児健診とは?流れ・ポイントまとめ
- 年齢別 発達障害の発達目安表
- 【発達障害とは?】特徴・症状を3分で理解!学べる基礎ガイド④検査の種類
- 5歳児健診で「発達が気になる」と言われたら?
- 【就学前検診とは?】基礎・流れ・チェックポイントを専門家レベルでわかりやすく解説!
- 就学進路の決め方|支援級・通級・通常級の比較ポイント
- 合理的配慮の義務化でどう変わる?2025年最新解説

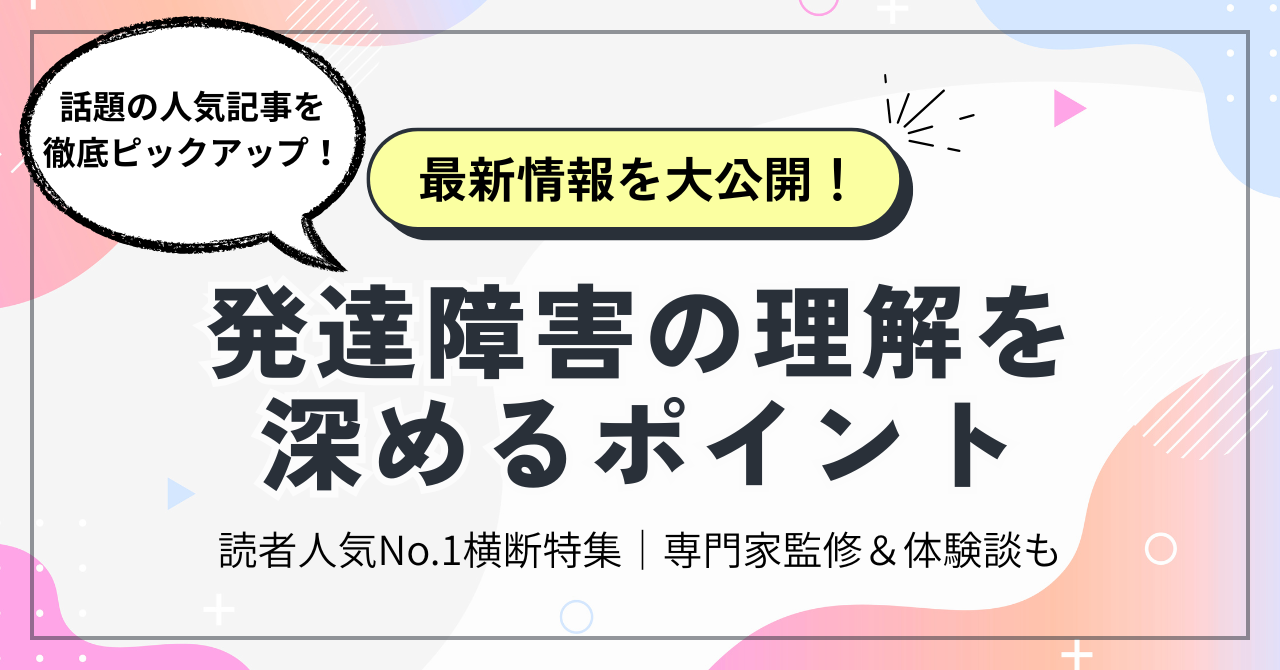
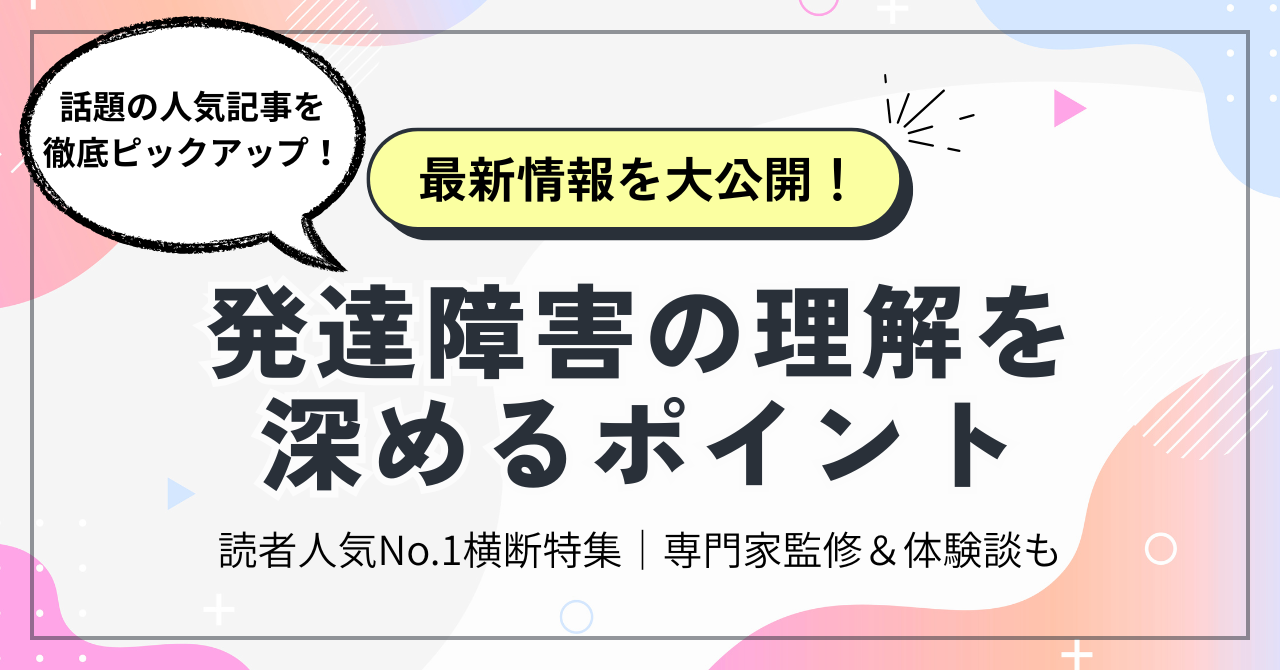
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4ab6ce69.3882e241.4ab6ce6a.a4337954/?me_id=1422375&item_id=10000097&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Flumeland%2Fcabinet%2Ftrip%2Ftrip_020%2Ftrip-0202_00.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)


【体験談】
「健診で“もう少し見てみましょう”と言われ、発達検査を受けたら“得意・苦手”が明確に。進路決定のヒントになりました」