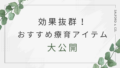こんにちは!おかーちゃんです。
発達障害やグレーゾーンのお子さんのために「本当に役立つ療育アイテムが知りたい」「療育教室で実際に使われているグッズを知りたい」という方へ。この記事では、療育教室で実際に使われていたおすすめアイテムを5つ厳選!効果や使い方、家庭での取り入れ方まで、初心者にも分かりやすく紹介します。お子さんの成長をサポートしたいパパママ必見です!ぜひ参考にしてください。
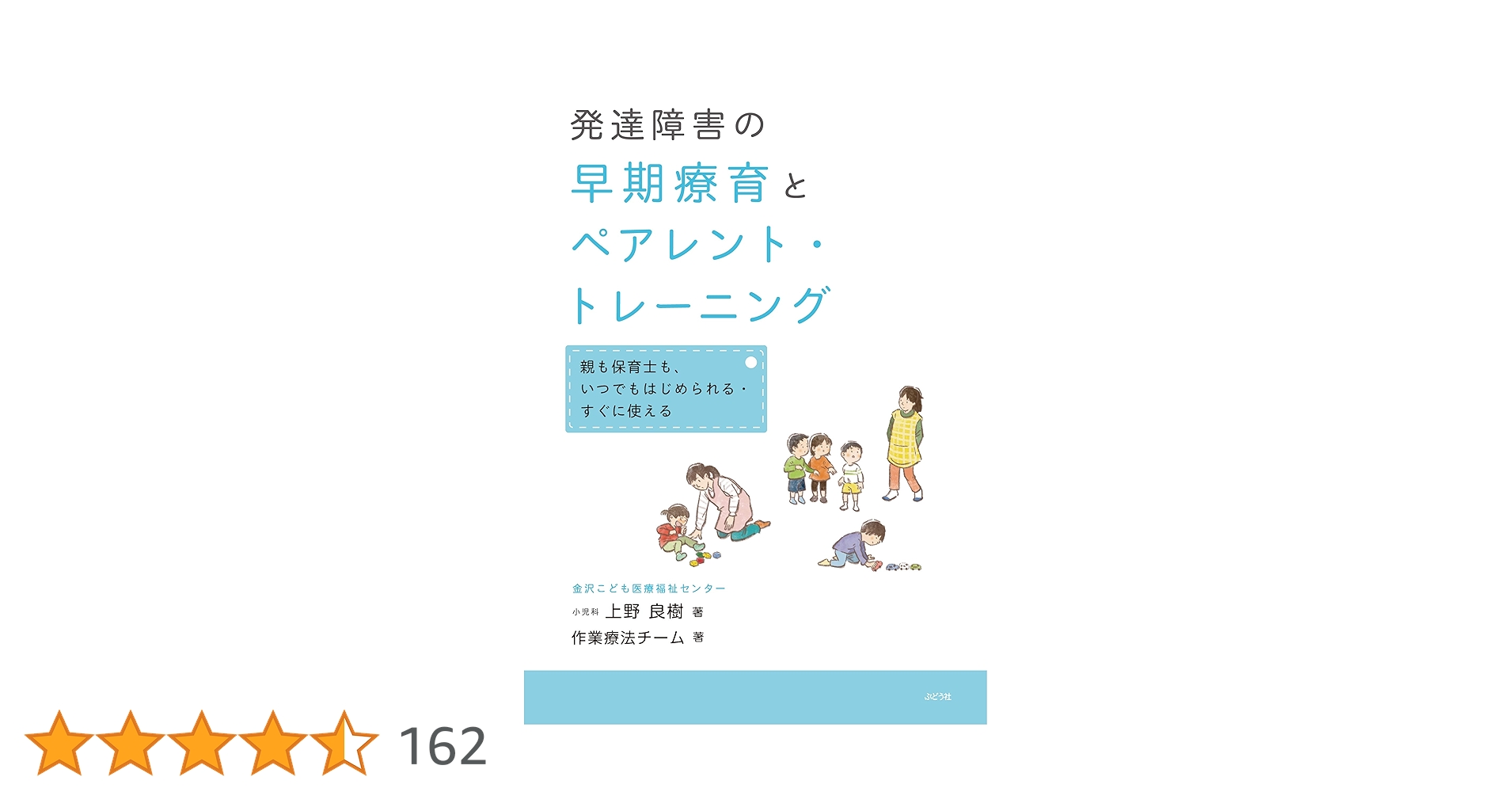
療育アイテムとは?目的と使い方を解説
療育アイテムとは発達に特性のあるお子さんが、生活や学びをスムーズにできるように助けてくれる道具のことです。療育教室などでよく使われており、おうちでも取り入れやすいのが特徴です。
使い方のポイント
- 子どもの「できた!」を増やすために使う
- 無理なく楽しく取り組める工夫がされている
- 使う時間や場面を決めて、習慣化しやすい
道具に頼りすぎるのではなく、子どもと一緒に使いながら「楽しい」「できる」の経験を重ねることが大切です。
療育教室で使用したアイテム5選
ここでは実際に療育教室で使って「これは良い!」と感じたアイテムを5つ紹介します。どれも手に入りやすく、おうちでも使えるものばかりです。
| アイテム名 | おすすめポイント | 主な効果 |
|---|---|---|
| バランスボール | 体幹・バランス感覚を鍛える | 落ち着き、姿勢・集中力アップ |
| 知育玩具 | 手先・関節運動、飽きずに取り組める | 手先の力加減、集中力UP |
| タイムタイマー | 見通し・時間感覚が身につく | 安心感、支度や勉強のスムーズ化 |
| 塗り絵・シール貼り・パズル | 楽しく手と目の協調運動 | 達成感、考える力、視覚・触覚の発達 |
| トランポリン・キャタピラー | 全身運動、楽しみながら体幹強化 | 運動能力UP、方向感覚、バランス感覚 |
感覚統合に効く「バランスボール」
バランスボールは、体のバランス感覚を養うのにぴったりなアイテムです。椅子の代わりに使ったり、ボールに乗って揺れるだけでも体に良い刺激を与えてくれます。
実際に使って感じた効果
感覚統合に悩んでいるお子さんには、まず試してほしいグッズです。
手先・関節運動の練習に「知育玩具」
以前の投稿で、発達障害の子は関節や手先の動かし方が上手にできない事を紹介しましたが、知育玩具は手の動かし方や関節を使う練習できるおもちゃです。自然と手先や関節を使う練習ができます。
またペットボトルの蓋を開ける練習・ビーズ通しは手軽に始めやすいのでおすすめです!
おすすめポイント
このねじ回しも手首を使って回す運動になります。
集中力アップに「タイムタイマー」
タイムタイマーは、残り時間が色で見える時計です。「あとどれくらい?」が目でわかるので、見通しが立ちやすくなります。
こんな子におすすめ
- 途中で飽きてしまう子
- 時間の感覚がつかめない子
- 勉強や支度をスムーズにしたい子
使うことで「終わりが見える」安心感が生まれます。
遊びながら学べる「塗り絵・シールはり・パズル」
パズルは、形を見て、ぴったり合う場所にはめる、どこからはめたらスムーズにできるか?と見通しを立てる訓練になります。
シール貼りや塗り絵は、ただ貼る・塗るのではなく簡単なルールを設定します(例:時間内に綺麗に塗るのか?→綺麗にぬるのは隙間なくクレヨンのカスなど出さないように、など詳しく説明して)
楽しみながら「考える力」や「目と手の協調」を育ててくれます。
ルールを決めるポイント
- 手と目を一緒に使う練習になるように最初の説明で手順やポイントを簡潔に説明する
- 最初は達成感が味わえるようにできる範囲のルールを設定する。
どれも100円shopでも購入可能なので手軽に始めやすいです。パズルはまずはピース数を少ない物から始めて徐々にピース数を増やしていくといいですね。
簡単な全身運動と体幹強化アイテム「トランポリン・キャタピラー」
トランポリンは全身の筋肉や関節運動になります。発達障害の子は体幹や筋肉が弱い傾向があるのでトランポリンの全身運動は効果的です。
キャタピラーは段ボールなどで作成し中に入って前進運動をします。方向感覚の強化、手足の関節でバランスをとる体勢をとるためおススメです。(ハイハイの運動でもいいですね!)
実際に使って感じた効果とは?
実際に療育アイテムを使ってみて、「これはすごい!」と思ったことはたくさんありました。特に感じたのは以下のような点です。
- 遊びながら力がつく
- 苦手だったことにチャレンジできるようになる
- 自信がついて、笑顔が増える
どの子にも合うとは限りませんが、合うアイテムが見つかれば、子どもの成長をグンと後押ししてくれます。
療育アイテムを選ぶときのポイント
療育アイテムを選ぶときに大切なのは、「その子に合っているかどうか」です。選び方のコツをまとめました。
試してみて合わないと感じたら、無理に続ける必要はありません。いろいろ試して、「これなら!」という道具に出会いましょう。
まとめ:療育アイテムでできること
今回紹介したアイテムをうまく活用すれば、
といった変化が感じられるはずです。療育アイテムは、お子さんの「できた!」を増やし、毎日の成長をグッと後押ししてくれる頼もしい存在です。療育教室で実際に使われていたアイテムを家庭でもうまく取り入れることで、親子で笑顔になれる瞬間がきっと増えていきます。お子さんに合ったグッズを見つけながら、無理なく楽しく療育を続けていきましょう!
最後までご覧いただきありがとうございます。

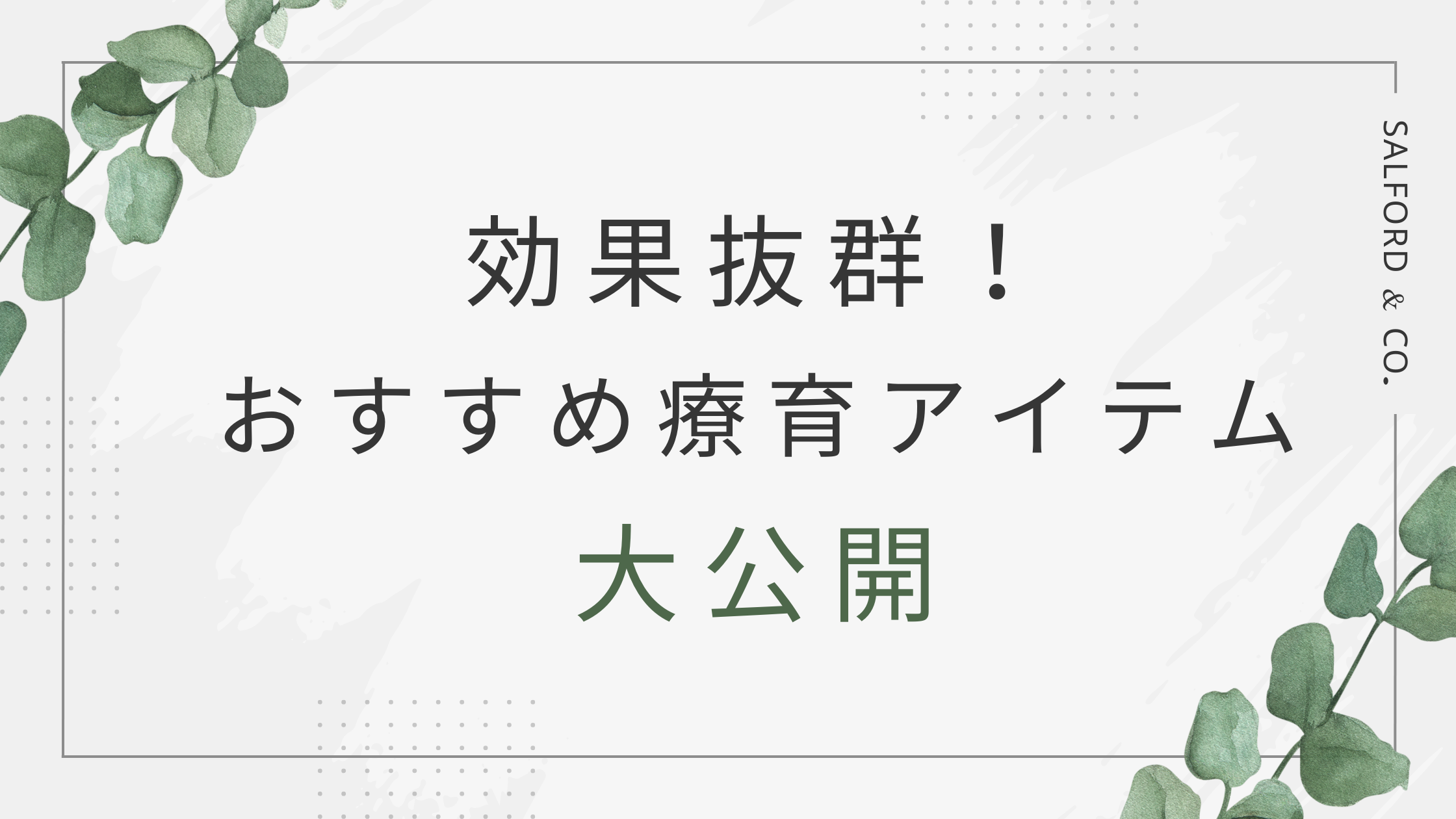
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46ca7671.d60c6c37.46ca7674.8cea2bd8/?me_id=1297917&item_id=10002193&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbaby-hoppe%2Fcabinet%2Fjordan%2Fjrpk0160-1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46cea939.65818aa6.46cea93b.cd92bf08/?me_id=1278501&item_id=10000777&pc=https%3A%2F%2Fimage.rakuten.co.jp%2Fdabada%2Fcabinet%2Ftrampoline%2Ftrampoline_tmb3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)