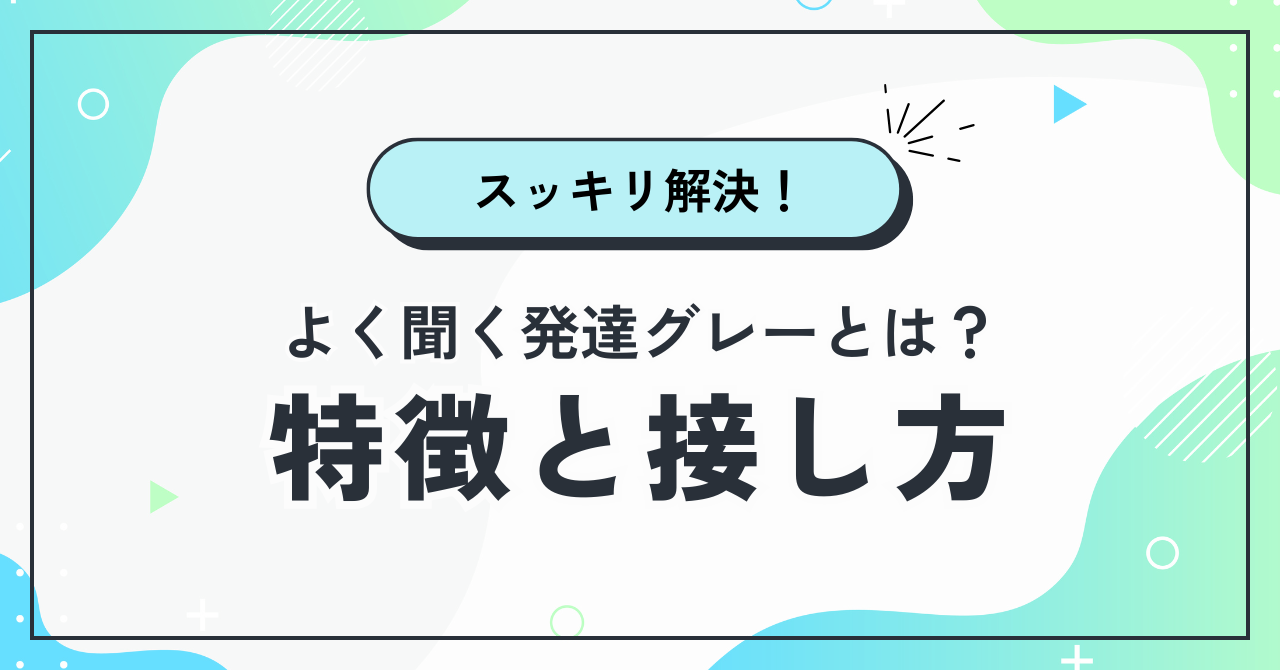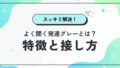こんにちは!おかーちゃんです。
「発達グレーって何?」「うちの子も当てはまる?」
そんな疑問を持つ方に向けて、グレーゾーンの意味・特徴・親ができるサポートまで、最新情報と実体験つきで分かりやすく解説します。
マンガでわかる 発達障害の子どもたち 自閉スペクトラムの不可解な行動には理由がある | 本田秀夫, フクチマミ |本 | 通販 | Amazon
Amazonで本田秀夫, フクチマミのマンガでわかる 発達障害の子どもたち 自閉スペクトラムの不可解な行動には理由がある。アマゾンならポイント還元本が多数。本田秀夫, フクチマミ作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。またマンガでわか...
発達グレーとは?—基準と分かりやすい説明
発達グレー(発達障害グレーゾーン)とは、発達障害の特徴が一部当てはまるけれど診断基準には届かない子どものことを指します。
見た目は普通に見えても、集団や学校生活で困りごとが起こりやすいのが特徴です。
やさしい説明(お子さん向けにも◎)
人には「得意なこと」「苦手なこと」があるよね。
発達グレーの子は、その“差”がちょっと大きいだけ。
たとえば音に敏感だったり、先生の話が聞き取りづらいことがあるよ。
「できない」はサインかもしれないから、一緒に考えていこうね!
発達グレーの子に多い特徴・チェックリスト
| サイン・特徴 | 具体例 |
|---|---|
| 感覚の過敏・鈍感 | 大きな音でパニック、衣服のタグを嫌がる、触感にこだわり |
| コミュニケーションの困り | 友達とうまく遊べない、一人遊びが多い、会話が続かない |
| 行動・こだわり | 同じ遊びやルーティンに固執、予定の変更で混乱 |
実体験:モチ男のおうちサポート事例
うちのモチ男も見通しが立たないと不安になりやすいタイプ。
わが家で意識しているサポートを紹介します。
- 毎朝「今日のスケジュール」を一緒に確認する
- 前日に準備が必要な物・予定を一緒にリストアップする
- 困った時や予定変更があった場合、「分からない」「困った」時は先生や友達に伝える言葉(例:「教えてください」「助けてください」)の練習をしておく
- できなかったことより「できたこと」をしっかり褒める
- 怒りそうな時も、まず「どうすればうまくいくか?」を一緒に考える
この繰り返しで、モチ男も予定変更や新しいことに安心してチャレンジできるようになりました。
失敗や「できないこと」も一緒に振り返ることで、初めてのことへの挑戦も増えています!
家庭でできる発達グレーの子へのサポートガイド
学校での支援・先生との連携
- 担任や支援員の先生に特性を伝えておく
- 「通級指導」や「特別支援員」などサポート制度を活用(地域によって利用できる支援が違います)
- 困っていること・安心できる工夫を学校と共有する
▶文部科学省|特別支援教育
▶【発達障害診断後】就学後に受けられる支援と手続き徹底ガイド②
「もしかして…」と思った時の相談先
- 市区町村の子育て支援課
- 発達障害者支援センター
- 児童精神科・発達専門クリニック
- 学校のスクールカウンセラー
診断=レッテルではありません。 サポートのきっかけ・安心の入り口になります。困りごとが続く時は早めに相談を。
まとめ:できること・好きなことに目を向けて
参考リンク あわせて読みたい関連記事
- 厚生労働省|発達障害支援のページ
- 国立障害者リハビリテーションセンター|発達障害情報
- 文部科学省|特別支援教育
- 発達グレーゾーンの息子|年齢別の特徴と対応まとめ【体験談】
- 発達障害の個別支援6つの方法|家庭でできる療育
- 【発達障害とは?】特徴・症状を3分で理解!学べる基礎ガイド①基礎編
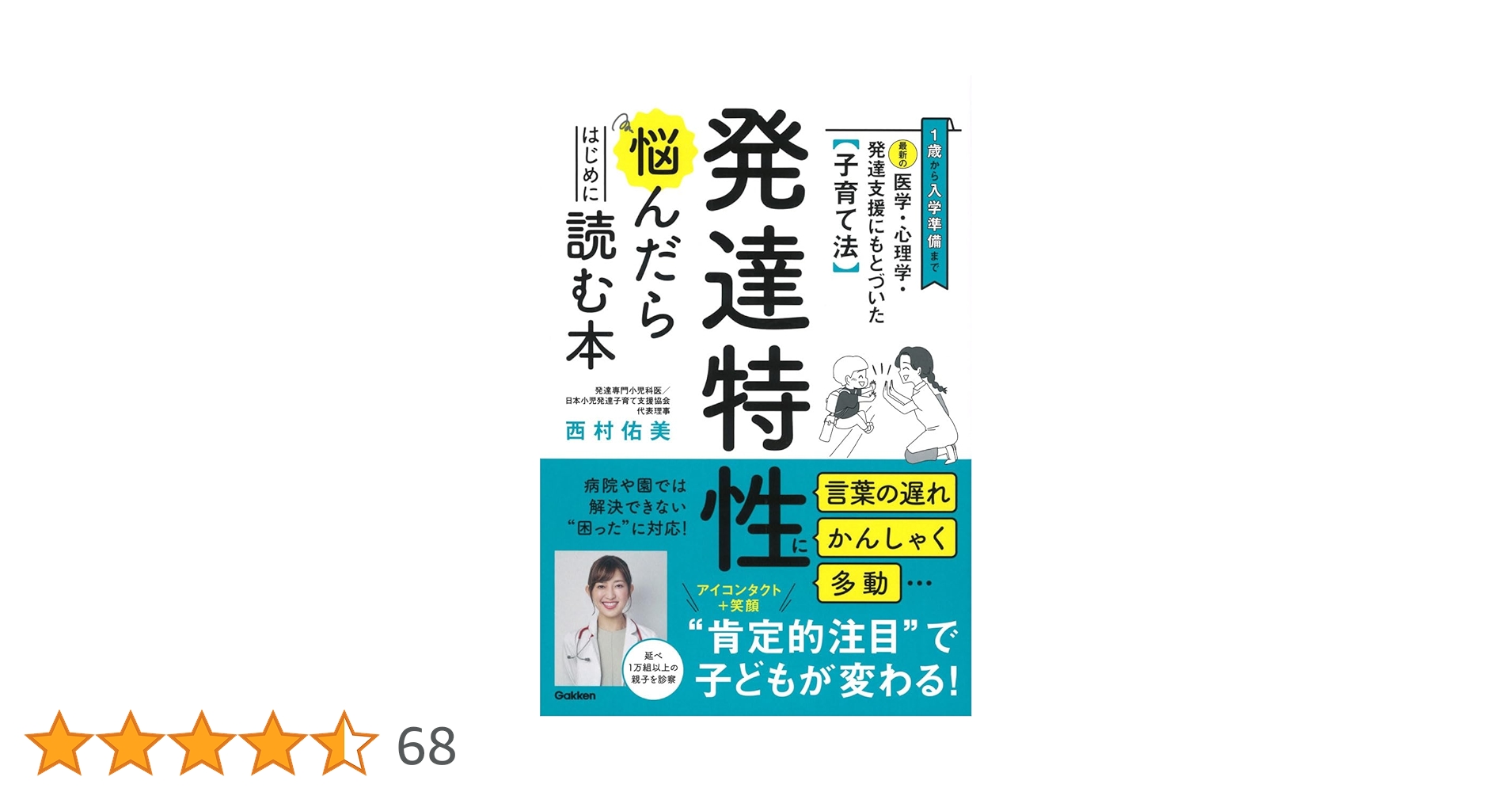
最新の医学・心理学・発達支援にもとづいた子育て法 発達特性に悩んだらはじめに読む本: 1歳から入学準備まで 言葉の遅れ かんしゃく 多動…病院や園では解決できない“困った”に対応
一般の小児科での診察や発達専門外来で、のべ1万組以上の親子を診た臨床経験、特性のある子の子育ての実体験をもとにした、医師&ママ目線でのアドバイス、指導を強みとした、西村佑美医師初の著書!◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇...