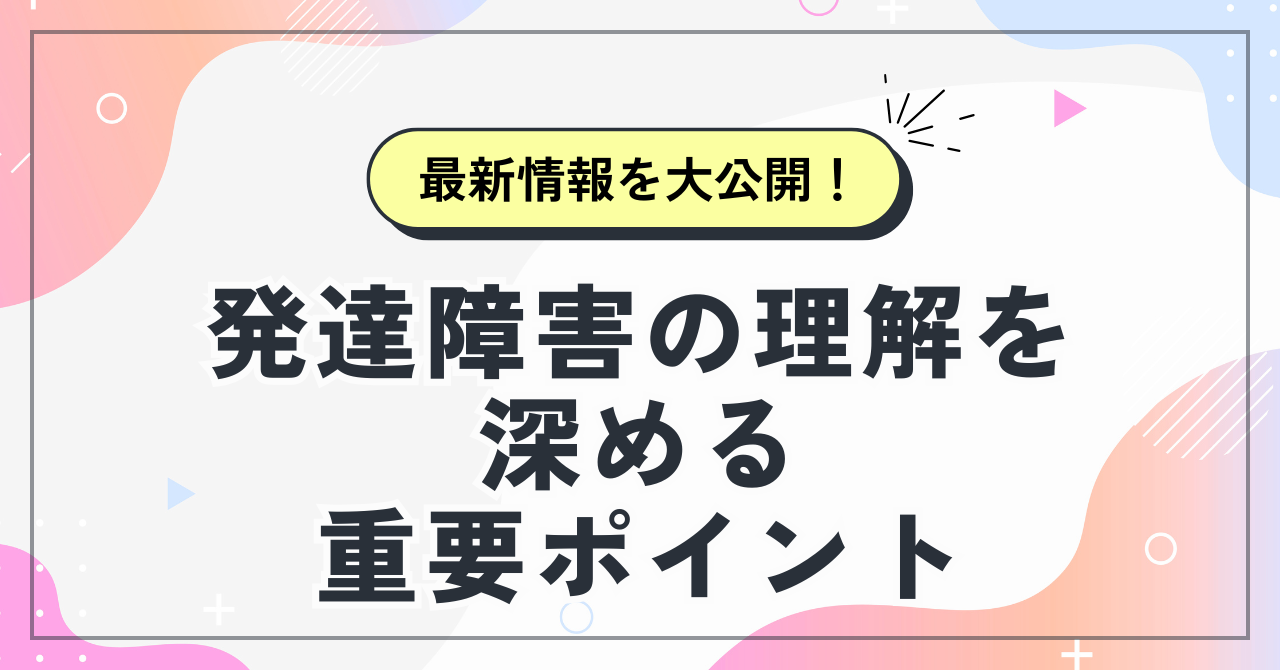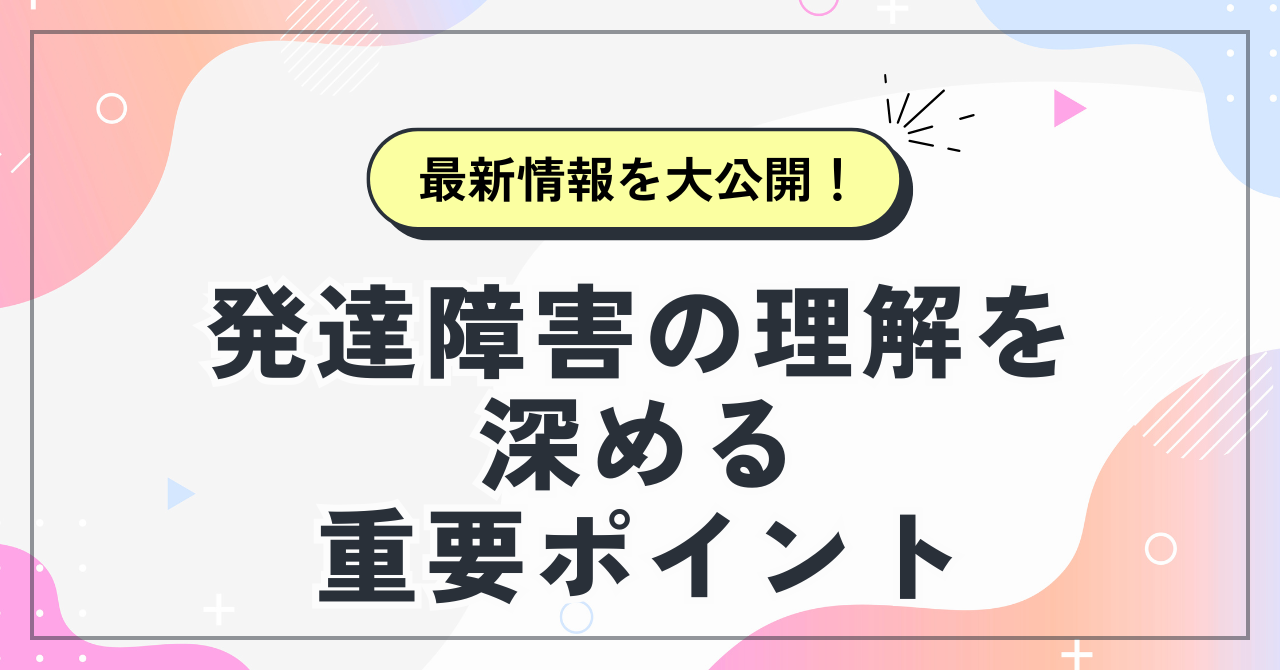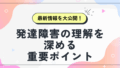こんにちは!おかーちゃんです。
5歳ごろは、「できること」と「まだ難しいこと」の差が大きく出やすい時期です。そのため、園や健診で「少し気になる点があります」「グレーゾーンかもしれません」と言われることも珍しくありません。
この記事では、5歳のグレーゾーンでよく見られる特徴や、家庭で気づきやすいサイン、相談できる場所についてわかりやすくまとめました。
“診断名がつく/つかない”よりも、お子さんが安心して過ごせる環境づくりのヒントになれば幸いです。
5歳の「グレーゾーン」とは?
グレーゾーンとは「診断名はつかないが、発達の凸凹が見られる状態」を指します。5歳は成長差が大きく、得意・不得意が強く出やすい時期です。
【5歳児健診】発達障害グレーゾーンとは?
発達障害グレーゾーンとは、発達障害の診断基準には当てはまらないものの、まわりの子どもと比べて行動や反応に気になる点が見られる状態のことです。明確な診断が出ないため、気づきにくい特徴があります。
このような状態を早く発見することが、子どもに合った支援につながります。詳しくは厚生労働省の発達障害支援ページも参考にしてください。
発達障害グレーゾーンの特徴チェックリスト
お子さんの行動に気になる点がある場合、以下のような特徴が当てはまるかチェックしてみましょう。
チェックリストに複数当てはまる場合は、無理に判断せず、まずは専門家に相談することが大切です。親御さんの気づきが、早期支援への第一歩です。
5歳で見られやすい特徴(グレーゾーンのサイン)
必ずしも“発達障害”というわけではありませんが、特徴としては次のような傾向が見られることがあります。
園で見られやすい様子(先生が気付きやすいポイント)
家庭では気づきにくくても、集団の中だと見えやすい特徴があります。
家庭で見られるサイン
次のような様子が続く場合、「困りやすい場面があるのかも?」と整理すると見通しがつきます。
家庭で気になる場面のメモ例
家庭でできるサポート
診断名ではなく、「その子が困っている場面」に注目するとサポートがしやすくなります。
おススメアイテム Amazon(タイムタイマー) (スケジュールボード)/楽天(マスク)
5歳児健診で気をつけるポイント
5歳児健診は、体の健康だけでなく心や発達の成長も確認する重要な機会です。以下の点を意識することで、発達グレーゾーンのサインを見逃しにくくなります。
健診は「問題の有無」を決める場所ではありません。子どもの個性や育ちのペースを理解し、必要な支援を見つける場として活用しましょう。
発達障害が疑われた時の合理的配慮とは
発達障害グレーゾーンとわかった場合、無理に周囲に合わせようとする必要はありません。子どもが安心して過ごせるよう、次のような「合理的配慮」が役立ちます。
こうした対応で、子どもが安心できる環境を整えることができます。保育園や幼稚園、学校とも協力し合うことが大切です。文部科学省の合理的配慮についてのページも参考になります。
相談先・支援機関の活用方法
「もしかして発達障害かも?」と思ったら、一人で抱え込まずに相談機関を活用しましょう。相談は無料のことが多く、専門家のアドバイスが受けられます。
- 市区町村の発達相談窓口
- 児童発達支援センター
- 保健所の子育て相談
支援機関では、発達の評価や療育の紹介、専門医の案内などを受けることができます。早めの相談が、子どもの可能性を広げる一歩です。
グレーゾーンと言われても心配しすぎなくて大丈夫
5歳は急成長する時期なので、半年でガラッと変わることもあります。「困りごとをどう減らすか?」の視点が大事です。
まとめ:早期発見で子どもの未来を守る
発達障害グレーゾーンは、診断がつきにくいぶん対応が遅れがちです。しかし、5歳児健診などで早期に気づけば、適切なサポートを受けることができます。
無理せず、子どもに合った育て方を大切にしていきましょう。親御さんの行動ひとつひとつが、子どもの未来を大きく支える力になります。
最後までご覧いただきありがとうございます。
参考リンク あわせて読みたい関連記事
- 厚生労働省 発達障害支援ページ
- 文部科学省 合理的配慮について
- 行政支援3大ステップ|療育手帳・手当・サービス/5歳児健診とは?発達・成長のポイント・流れ/“できない”から“できた!”へ ペアレントトレーニング成功のコツ/合理的配慮義務化でどう変わる?/5歳児健診で再検査・発達指摘…どうする/発達障害グレーゾーンとは?特徴・サイン・親のサポート/【発達障害とは?】特徴・症状を3分で理解!