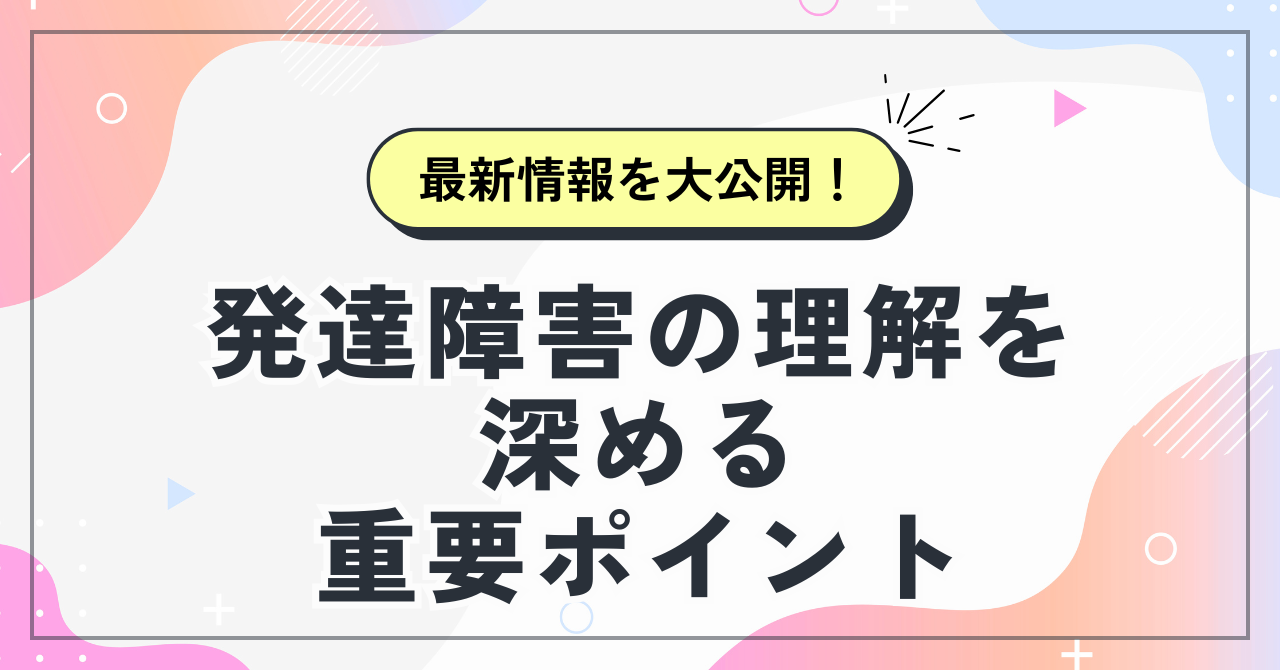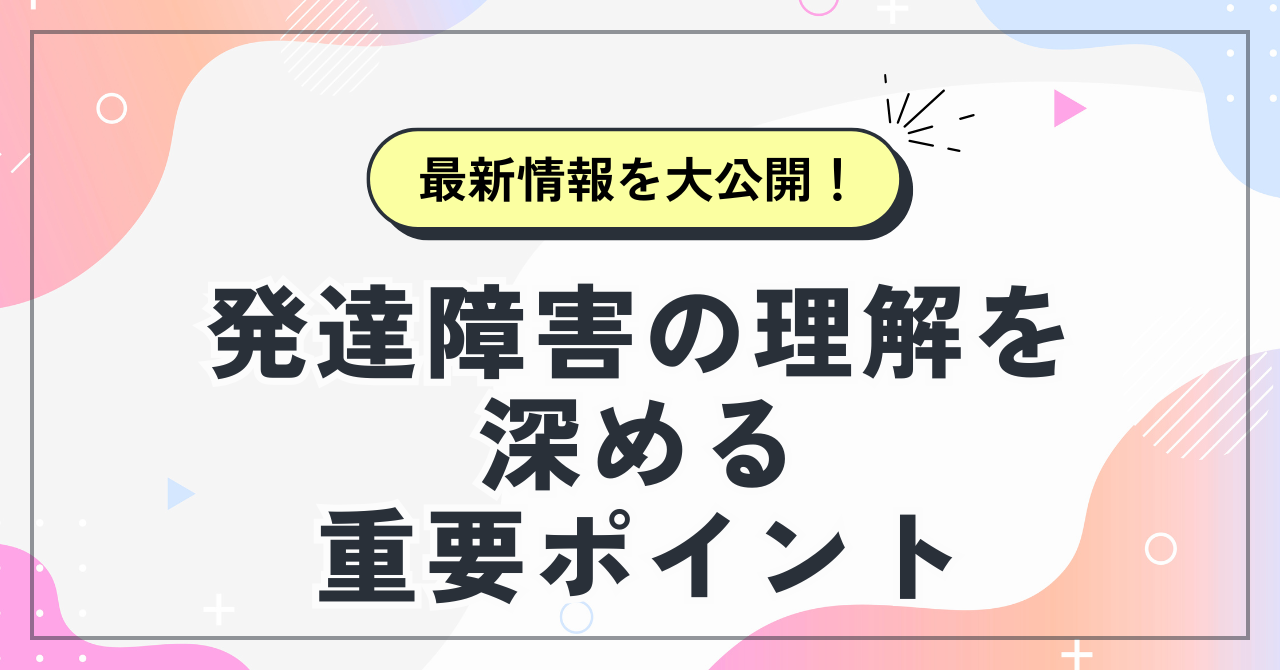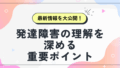こんにちは!おかーちゃんです。
前回は「合理的配慮」について基本を紹介しましたが、今回はもう一歩深掘りして「なぜ今、就学前の支援が大事なのか?」を分かりやすく解説します。
「具体的に家庭で何ができる?」「どんなタイミングで相談すればいい?」と迷っている方にも役立つ内容です。
合理的配慮とは?意味をわかりやすく解説
合理的配慮=みんなが安心できる“ちょっとした工夫”
合理的配慮とは、障害のある人もない人も、同じように生活・学習できるように環境ややり方を工夫すること。
例えば、耳が聞こえにくい子にノートを見せてあげたり、集中しづらい子に静かな席を用意したりすることが該当します。
「特別扱い」ではなく、みんなが過ごしやすくなるための“あたりまえの工夫”がポイントです。
合理的配慮のポイントまとめ表
| シーン | 配慮の具体例 |
|---|---|
| 学校 | ・静かな席を用意 ・プリントの文字を大きく ・授業中の席移動OK |
| 家庭 | ・予定表やタイマーで見通しをつける ・家族で「得意・苦手」を共有 |
| 健診・就学前 | ・保護者・先生・専門家の三者で情報共有 ・クラウドシステムの活用 |
どうして合理的配慮が必要なのか?
困っている人が「助けて」と言いやすくなり、自分らしく過ごせる環境を作るためです。
特に発達障害の子どもは自分で困りごとを言語化しにくいので、周囲の気づき・理解・配慮が何よりの支えになります。
2024年からは学校でも合理的配慮が義務化!
今までは“努力義務”でしたが、今年から「必ず実施する」ことが法律で決まりました。すべての子どもが安心して学べる大きな転換点です。
なぜ今、就学前の支援が強化されるのか?
空白の2年間”を埋めるための対策
これまで1歳半・3歳健診のあと、小学校入学まで2年間は「特にチェックがない空白期間」でした。
実際、小1で「支援が必要」とされた子の約4割は、3歳健診時には特に指摘がなかったという調査結果もあります(文部科学省調査)。
この2年間を見逃さないために、国は“就学前支援”を強化!
【実体験MEMO】
私の友人の子が5歳を過ぎたころ「順番を待つのが苦手」「集団での遊びが難しい」と気づき、早めに保健センターへ相談。
専門家とつながり、就学前に家庭・園・小学校の先生が連携できたことで、不安なく入学できた!と言ってました。早めの相談・対応が安心に繋がります。
関連記事▶5歳児健診で「発達が気になる」と言われたら?グレーゾーンと親のための全対策【保存版】
発達の特性が分かるタイミングは「5歳前後」
5歳は言葉・社会性・集団活動の伸びが大きい時期。
園生活の中で「お友達と話せない」「じっと座るのが苦手」「こだわりが強い」など、ちょっとした困りごとが見えやすくなります。
こうした様子があれば、できるだけ早く専門家や園の先生に相談しましょう。
早期支援で防げる二次障害とは
支援が遅れると「自分はできない」と感じ、不登校やメンタル不調(二次障害)につながることも。
文科省調査では、就学前に支援を始めた自治体で二次障害が約3割減った実績も。早期支援は子どもの未来を大きく変えます。
5歳児健診の導入で期待される効果
経済的にもメリット!
支援が遅れると1人あたり約200万円の追加コスト。
5歳からの支援で、社会全体の負担も約半分にできるという研究報告もあります。
モデル地域の成功事例
北九州市など“5歳児健診先行地域”では早期発見&支援の効果がはっきり。
こうした成功モデルが全国へ広がっています。
合理的配慮義務化と学校現場の対応
2024年からはすべての学校に合理的配慮が義務化されました。
主な配慮例:
ICTを使った支援も進化!
健診結果や個別支援計画がクラウドシステムで連携され、保護者・先生・専門職がスムーズに情報共有できるようになりました。
また、先生向けの研修も国費で実施され、現場のサポート体制がどんどん強化されています。
今後のスケジュールと保護者ができること
2025年から政府が進める具体策は:
保護者が知っておくべき3つのポイント
【困ったときは相談を!】
- お住まいの「子ども家庭センター」
- 発達障害者支援センター
- 保健センター・小児科・園の先生
まずは身近な窓口に連絡してみましょう。
参考リンク あわせて読みたい関連記事
- 内閣府:合理的配慮に関するガイドライン
- 厚生労働省:発達障害支援施策
- 文部科学省:特別支援教育の推進
- 発達障害グレーゾーンと5歳児健診まとめ/発達障害の子どもの二次障害とは?
- 小学校入学準備で本当に役立った!子ども向けグッズ5選
- 発達障害の就学前支援級・通級完全ガイド/家庭でできる合理的配慮
- 発達障害の子の就学準備はここから!親が最初に読むべき用語&手続き入門
- 個別支援計画(IEP)の作り方|失敗しないポイントと親の工夫
まとめ:早期発見・早期支援が未来を変える
子どもたち一人ひとりが自分らしく成長できるように、家族・学校・地域が一緒になって支えることが求められています。政府の新しい取り組みを活用しながら、みんなで未来を明るくしていきましょう。
最後までご覧いただきありがとうございます。