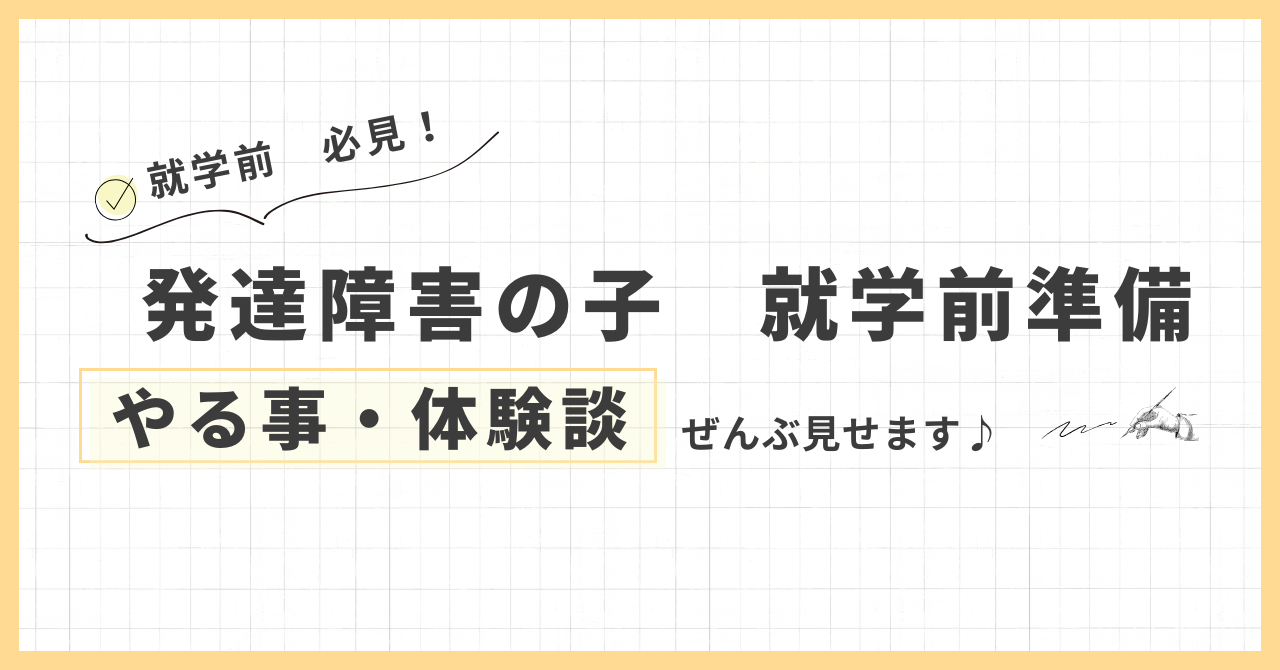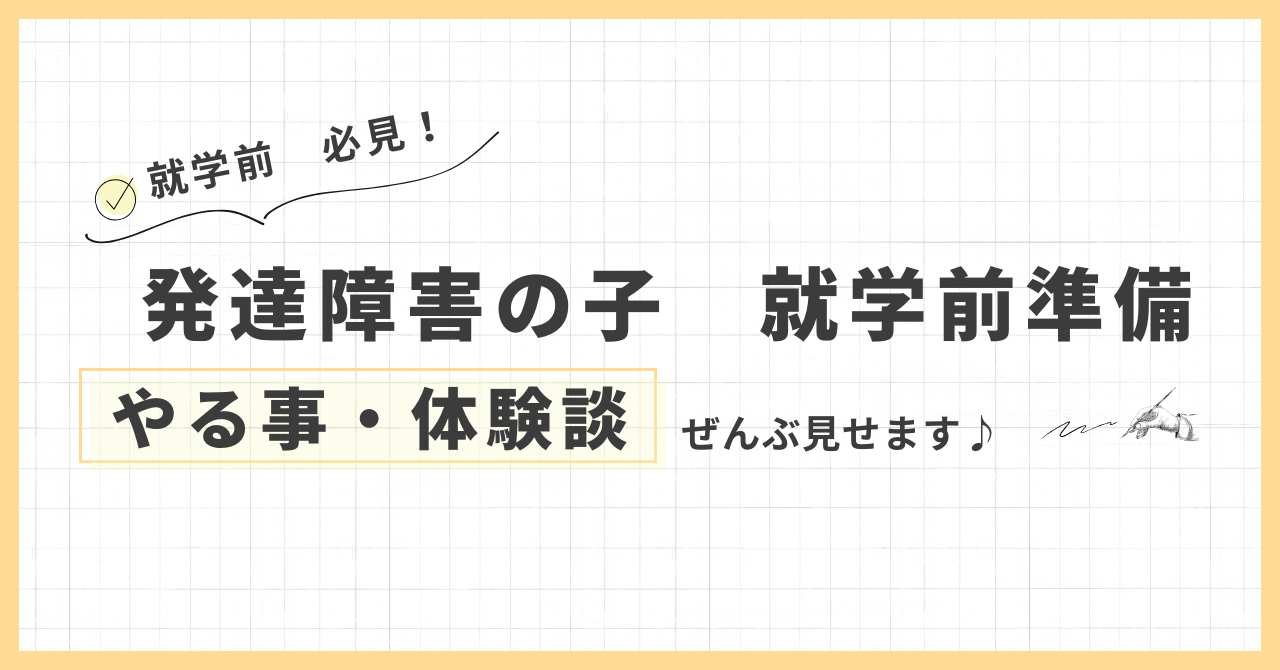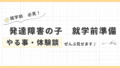こんにちは!おかーちゃんです。
「IEP(個別支援計画)って聞いたことあるけど、実際どんなもの?
何を書けばいいの?うちの子も対象?」「どう伝えたらいい?」「何を決めればいい?」――初めてでも迷わないように、IEPの基本から実践までをやさしく整理しました。
この記事でわかること
先に結論:IEPは「子どもの学び方を見える化する設計図」
IEPは、子ども本人・保護者・学校(担任・支援員・専門職)が同じゴールに向かうための「共有ドキュメント」です。学期や年度の区切りで見直し、うまくいった支援や新しい課題を反映させることで、日々の学び方がブレなくなります。
IEP(個別支援計画)とは?
定義
IEP(Individualized Education Program)=個別支援計画は、子ども一人ひとりの「学びやすさ」や「得意・苦手」「サポートが必要な場面」→一人ひとりの特性・得意/苦手・学習目標・必要な支援や配慮を整理するための“子ども専用プラン”です。
保育園・幼稚園・小学校などで、本人・保護者・先生・専門家が一緒に考えて作成します。学校内の指導だけでなく、家庭と連携して実行できる形に落とし込みます。
難しく感じるかもしれませんが、「うちの子らしさ」をみんなで守るための“安心ノート”のようなものです。
文部科学省|特別支援教
| Q | A |
|---|---|
| IEPって何のために作るの? | お子さん一人ひとりの「得意・苦手」や「必要な配慮」を整理し、学校・家庭・専門家が同じ目標でサポートできるようにするための“個別サポート計画”です。 |
| どんな人が対象? | 発達障害・特別な配慮が必要な子どもだけでなく、「支援が必要かも」と思った時はどなたでも相談OK。園・学校・療育など場面ごとに作成されます。 |
| IEPを作ると、どんな良いことが? | 先生・保護者・専門家の支援が“ブレない” 子どもの成長や困りごとが“見える化” 配慮や支援の記録・振り返りがしやすい |
IEPで得られるメリット
たとえば「初めての場所が苦手」「音に敏感」な場合も、IEPがあれば先生や周囲も気づきやすく、無理なく配慮できます。
IEPは「みんなちがって、みんないい」を実現する具体的ツールなんです。
| IEPがある場合 | IEPがない場合 | |
|---|---|---|
| 子どもの特性伝達 | 苦手・得意が全員に共有されやすい | 先生によって理解に差が出る |
| 配慮・支援の一貫性 | 家庭・学校・専門家が同じ目標で連携 | サポートや配慮がバラバラになりやすい |
| 成長・変化の記録 | 目標や達成が見える化できる | 課題や改善点があいまいになりがち |
| 相談・フォロー体制 | “悩みの孤立”を防げる | 相談しづらく、保護者が孤立しやすい |
IEP「準備が10分で整う」セット
IEP準備の相棒|比較表
| アイテム | こんな場面に | 使いどころ(実例) |
|---|---|---|
| A4バインダー 立ち書き/資料固定 | 面談室で席が狭い/机がない | 左:議題/右:到達目標・支援案を可視化 |
| クリアファイル 「学習/行動/感覚/連絡」などで分類 | 配布資料・評価表が多い | 議事録・配布物・次回宿題を分けて迷子ゼロ |
| インデックス付箋 後で戻りやすい | 優先論点/要確認事項が多い | 「目標」「配慮」「評価」「次回」で色を固定 |
| 静音タイマー 無音/バイブ | 議題が多く時間オーバーしがち | 1議題10分で区切り→全体を終わらせる |
IEPの作成ステップ(はじめてでも迷わない手順)
Step1:事前準備(材料集め)
Step2:学校と話し合い(チームで合意をつくる)
Step3:計画書の確認・更新(PDCA)
IEPの内容と具体例|項目と記入例
| 主な項目 | 記入例 |
|---|---|
| 目標 | 「朝のあいさつを自分からできるようになる」 |
| できていること(強み) | 「動物が好き」「ひとり遊びが得意」 |
| 苦手なこと・支援が必要なこと | 「大きな音が苦手」「集団行動が不安」 |
| サポート方法 | 「大きな音のとき耳栓を使う」「席替え前に声かけ」 |
こうした具体例を参考に、お子さんの「強み」「困りごと」「目標」「サポート法」を書き出してみましょう。
IEPは誰がどうやって作る?作成の流れ
- まずは家庭で普段の様子や気になることを書き出す
- 園や学校の先生と情報を共有・相談する
- 必要なら療育の先生・専門家とも話し合い
- 目標や支援方法をみんなで決めて、IEPとしてまとめる
- 年度ごと・状況ごとに見直してアップデート
ポイントは「1人で悩まず、みんなで一緒に」作ること。
【保護者の安心】IEP作成チェックリスト
面談で失敗しない伝え方(NG→OKの言い換え例)
| NG例 | OK例(通りやすい言い方) |
|---|---|
| 「配慮を増やしてください」 | 「授業中の音刺激に反応しやすいので、前方の壁側に席を置いてもらえますか?」 |
| 「落ち着きがないので何とかしてほしい」 | 「15分集中→2分休憩のサイクルを提案します。タイマー使用の許可は可能でしょうか?」 |
| 「全部先生にお任せします」 | 「家庭では視覚スケジュールを使います。学校でも同じ絵カードを掲示いただけると統一できます」 |
個別支援計画チェックリスト(打合せ前に最終確認)
- 目標は行動で測定可能な文になっている(例:回数・時間・割合)。
- 優先度の高い支援項目を3つ以内に絞っている。
- 授業・休み時間・行事など場面別の配慮が書かれている。
- 席の位置・環境調整(音・光・動線)が具体的。
- 視覚支援の種類と運用ルール(誰が・いつ提示)が明記。
- クールダウンの場所・合図・時間が決まっている。
- 家庭での協力内容(宿題の工夫・声かけ)が一致している。
- 評価方法(観察記録・シール表・タイム計測など)が決まっている。
- 見直し時期(学期ごと等)と担当が明記されている。
- 同意できない点の代替案を準備済み。
★PDFなどの配布用チェックリストにしたい場合は、この項目をそのまま表にして印刷すればOKです。
面談メモの型(要点だけ書けるテンプレ)
- 到達目標(SMART):_______________
- 支援・配慮(教室/行事/連絡):_______________
- 評価方法(頻度/指標/誰が):_______________
- 家庭と学校の役割分担:_______________
- 次回までの宿題:_______________
※録音は必ず許可を。許可NGなら要点メモ+無音タイマーで時間管理。
体験談|IEPを初めて作ってみて…
私は「IEP」や「支援計画」という言葉も知らず、最初は戸惑いと不安でいっぱいでした。
でも療育の先生から「まず家で様子や困りごとを書き出してみて」とアドバイスされ、書き出して先生に相談。
「ひとりじゃない、一緒に考えてくれる人がいる」だけで安心感が生まれ、子どもの強みや困りごとを整理できました。今はIEPが“親子を支える心強い味方”になっています!
よくある質問(FAQ)
Q1. 途中で計画を変更できますか?
A. できます。状況が変わったら臨時の見直しを学校に相談しましょう。更新履歴を残すと引き継ぎがスムーズです。
Q2. 合意できない場合はどうすれば?
A. 事実ベースで再整理し、代替案を複数提示します。優先順位を再確認し、達成可能な範囲から合意を積み上げます。
関連記事▶合理的配慮とは?
Q3. 学校外の専門機関は関われますか?
A. 可能です。療育や医療の専門職のアセスメントや助言を計画に反映できると、より実行性が増します。
参考リンク あわせて読みたい関連記事
- 文部科学省|特別支援教育の推進
- 就学準備ガイド/進路選びで迷う保護者へ|普通級でも就学支援ファイルは意味がある?
- 【学校見学の持ち物・服装・マナー完全版】/就学前手続き完全ガイド|放デイ・学童・IEP
- 【支援級・通級・通常級 徹底比較】迷った親が知るべき判断基準&失敗しない進路選び
- 合理的配慮の伝え方:要望書テンプレと面談のコツ
- ペアレントトレーニング:家庭でできる実践5選
- 小学校生活で役立つABA声かけ実例集|発達グレーの子も“できる!”が増える
- 小学校入学前に本当に役立った!親が準備しておいて良かったグッズ5選
まとめ:IEPは「いまの困り」と「明日のできた」をつなぐ橋
完璧な計画から始めなくて大丈夫。小さな合意と改善を積み重ねるほど、お子さんの「できた!」は増えていきます。IEP(個別支援計画)は、子ども一人ひとりの「学びやすさ」をみんなで支える大切な計画「よくわからない」からでも大丈夫。まずは良いところ・好きなこと・苦手なことを書き出してみましょう。
分からないときは先生や専門家に相談OK!IEP作成法・実例は次回記事でも紹介します 。
最後までご覧いただきありがとうございます。