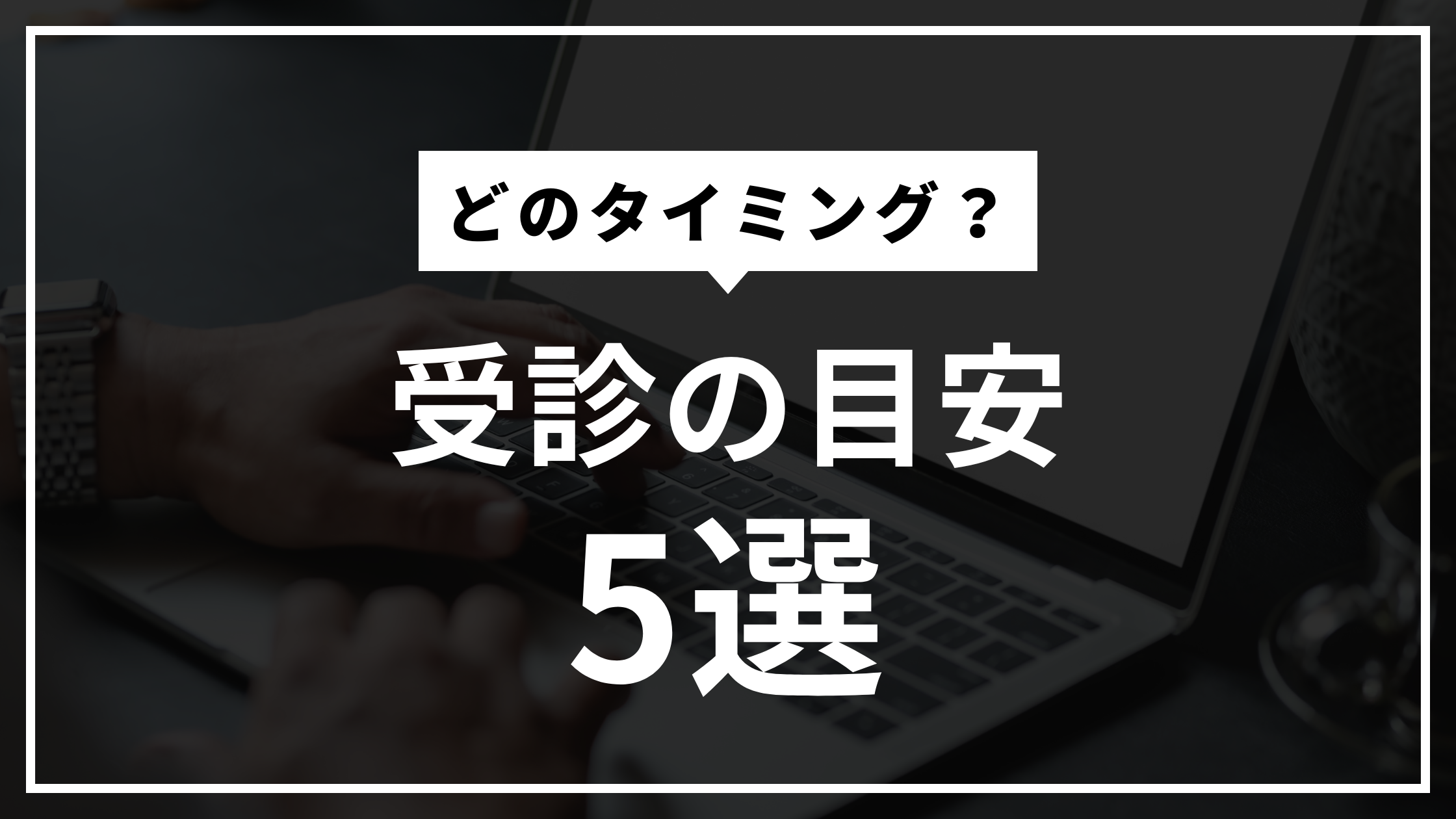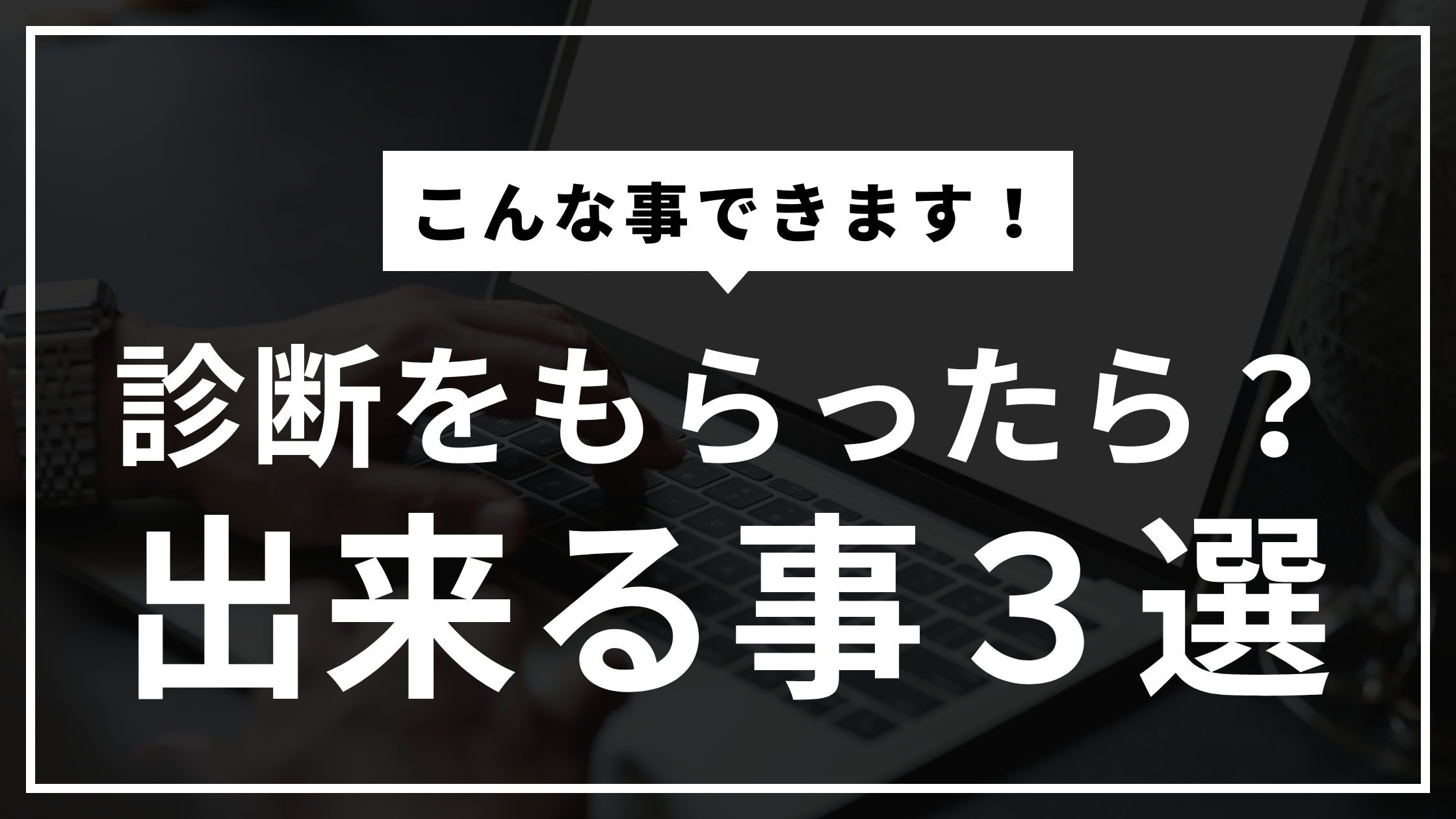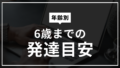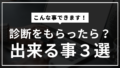こんにちは!おかーちゃんです。
「うちの子、もしかして発達障害かも…?」
そう感じたとき、いつ・どこで・どんなタイミングで受診すべきか迷う方も多いのではないでしょうか。私自身、日々の育児の中で「これは個性?それとも発達の特性?」と悩んだ経験があります。
この記事では、発達障害の受診の目安について5つの視点から分かりやすく解説します。
判断に迷ったときの参考にしていただければ幸いです。
Amazon.co.jp
言葉・コミュニケーションの発達が気になる
集団生活で困りごとが多い
Amazon.co.jp
感覚の敏感さやこだわりが強い
生活リズムや切り替えが難しい
周囲からの指摘・家庭での違和感
受診の目安チェック表
| 受診の目安カテゴリ | 主なサイン |
|---|---|
| 言葉・コミュニケーションの発達 | 発語の遅れ、会話が成り立たない、共感が薄い |
| 集団行動・社会性の困りごと | 順番が守れない、友達とのトラブルが多い、授業中に立ち歩く |
| 感覚過敏・こだわりの強さ | 特定の音・匂い・触感に敏感、決まった服しか着られない |
| 生活習慣の乱れや困りごと | 寝つきが悪い、切り替えが苦手、食事や着替えに苦労している |
| 周囲からの指摘や違和感 | 保育士や先生から指摘を受けた、家庭内でも違和感がある |
相談・受診できる場所
継続して困りごとが見られる場合は、以下のような機関への相談がおすすめです。
▶ 医療機関
- 小児科・児童精神科:診断・医療的支援
- 小児神経科:行動や発達の専門医が対応
▶ 支援機関
- 発達障害支援センター:地域の相談窓口
- 児童発達支援センター:未就学児の療育支援
- 教育相談センター:学校との連携・支援の相談
あわせて読みたい・参考リンク
- 【発達障害とは?】特徴・症状を3分で理解!学べる基礎ガイド②ASD
- 発達障害の個別支援6つの方法|家庭でできる療育【実体験】②スケジュール管理
- 【5歳児健診】発達グレーって何?診断される前に知りたい特徴と相談の流れ
- 「個性」と「発達障害」の違い—どこから支援が必要?【保存版】
- 5分で落ち着く!発達障害児の癇癪・パニック“神対応”マニュアル
- 5歳児健診とは?発達・成長のポイント・流れ・Q&Aを徹底解説
- 家庭と学校でできるABA的サポート―親も先生もすぐできるポイント
- “できない”から“できた!”へ ペアレントトレーニング成功のコツと親のサポート例
まとめ|迷ったら相談を
発達障害の可能性があると感じたとき、早期の受診はお子さんが生きやすくなるための第一歩です。
「困っていることは何か?」「どう支援できるか?」を一緒に見つけてくれる専門家はたくさんいます。不安な気持ちを抱えすぎず、気軽な気持ちで相談からはじめてみてください。
次回は、実際に診断を受けた「モチ男」のエピソードと福祉サービスの使い方についてご紹介予定です。
最後までご覧いただきありがとうございます。