こんにちは!おかーちゃんです。
前回までで「インクルーシブ教育」の定義や世界と日本の制度について解説しました。
今回は「実際に現場ではどんな多様性サポートが行われているのか?」にフォーカスし、通常級・支援級・通級それぞれの実践例や現場の課題、保護者・先生のリアルな声までお届けします。
発達障害のある子へのやさしい「個別の指導計画」作成ガイド (特別支援教育サポートBOOKS) | 喜多 好一, 齊藤 代一, 山下 公司 |本 | 通販 | Amazon
Amazonで喜多 好一, 齊藤 代一, 山下 公司の発達障害のある子へのやさしい「個別の指導計画」作成ガイド (特別支援教育サポートBOOKS)。アマゾンならポイント還元本が多数。喜多 好一, 齊藤 代一, 山下 公司作品ほか、お急ぎ便対...
通常級でのインクルーシブ教育:サポート実例と課題
支援級でのインクルーシブ教育:実践例とポイント
【保護者の声】
「支援級にいるけど“お客さん扱い”で終わらず、みんなと一緒に行事や係活動に入れてもらえたのが良かった」
「担任同士の連携が良いと、本人も兄弟も安心できる」
通級指導教室でのインクルーシブ教育:ハイブリッド支援の実例
【現場の声】
「通級の先生が毎週通常級の先生と打合せして“見えない配慮”も強化している」(支援員)
「保護者が“通級の記録”を自分でノート化して担任と共有するようになり、配慮の精度が上がった」
現場の課題と今後への期待
【保護者の本音】
「“先生だけ”に負担をかけず、家庭も学校も一緒に“より良い配慮”を育てていける関係が理想です」
まとめ|インクルーシブ教育の“現場で効く”支援と課題を3タイプ別に整理
本記事では、インクルーシブ教育を「通常級・支援級・通級」の3タイプで比較しながら、合理的配慮の具体例と現場の声、そして乗り越えるべき課題を整理しました。要点は、一貫した配慮・情報共有(IEPの活用)・ピアサポート・家庭と学校の協働の4本柱です。
「うちの子だけ…?」にならないために、学校全体での理解促進と教員研修の充実、そして家庭と学校が一緒に配慮を育てる関係づくりが鍵。保護者は配慮の目的を言語化/通級・支援の記録をノート化し担任と共有、学校は校内で配慮ルールを可視化・IEPで情報一元化を進めると、子どもの自己肯定感と学びの参加が加速します。
最後までご覧いただきありがとうございます。
参考リンク あわせて読みたい関連記事
次回は「家庭でできる合理的配慮と子どもの自己肯定感アップのコツ」をノウハウ付きで徹底解説!
- LITALICO発達ナビ|インクルーシブ教育の現場レポ
- 文科省|インクルーシブ教育Q&A
- 【人気記事】学校見学のポイント・体験談まとめ
- 【支援級・通級・通常級 徹底比較】迷った親が知るべき判断基準&失敗しない進路選び
- IEP(個別支援計画)とは?図解&チェックリストで意味・目的・メリットが丸わかり
- 小学校入学後に効く!ペアレントトレーニングの基本と家庭での活かし方
- 放課後等デイサービス(放デイ)見学と探し方
- 合理的配慮・インクルーシブ教育よくあるQ&Aと2025年最新トピックまとめ

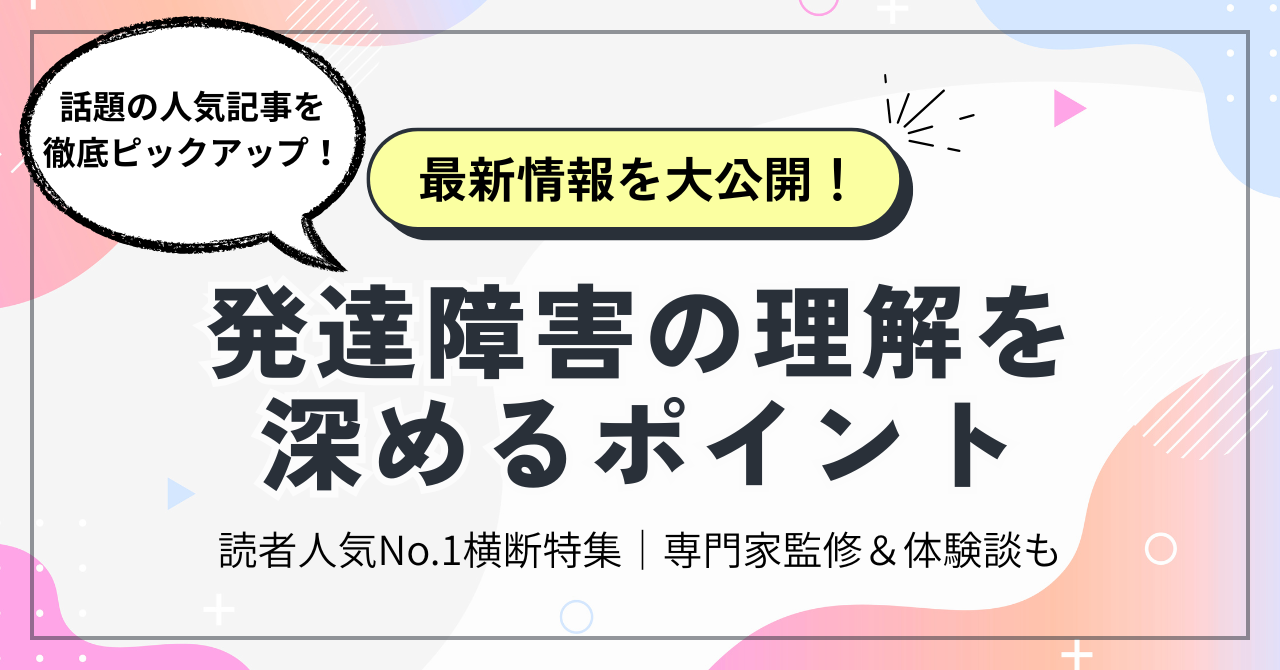
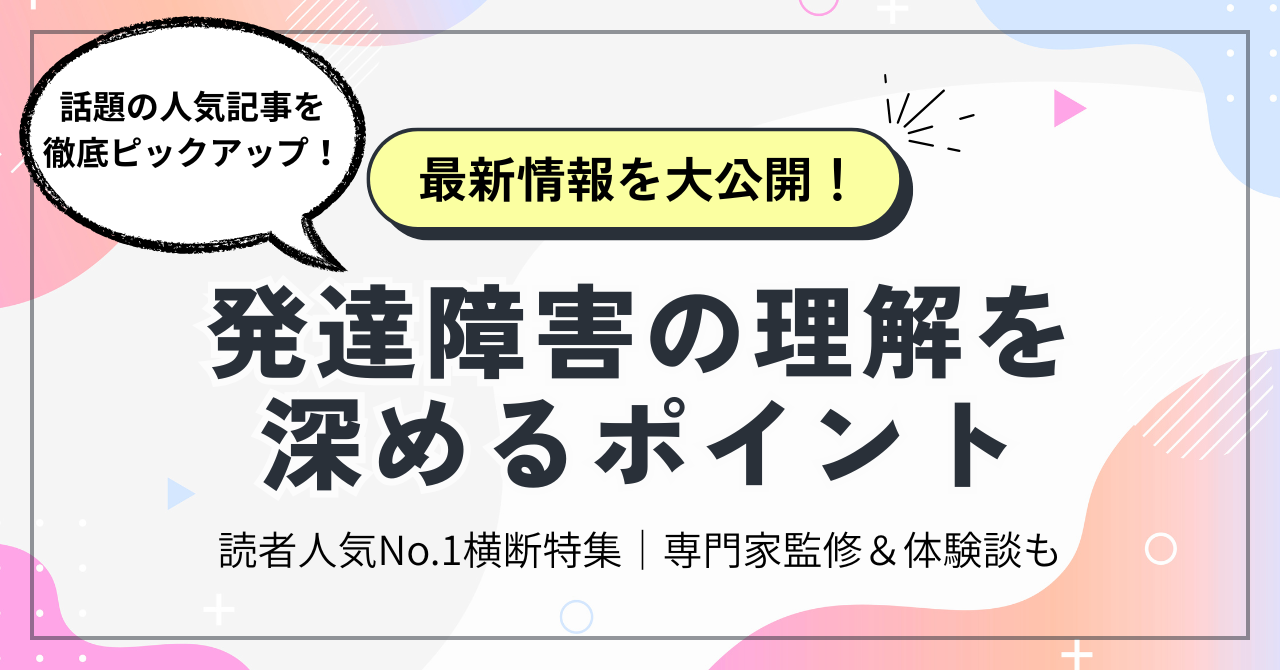

【現場の声】
「クラスで“みんな違っていい”という雰囲気作りを大切にしている」(担任)
「保護者会で配慮の意義を説明したら、協力的になってもらえた」(副校長)