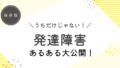こんにちは!おかーちゃんです。
「急に大声で泣き叫ぶ」「スイッチが入ると止まらない」…発達障害の子どもの癇癪、本当に毎日つらいですよね。
私も“なんでこんなに怒るの?”と悩み、つい感情的に叱って自己嫌悪…その繰り返しでした。
でも大丈夫。癇癪は“わがまま”でも“親のせい”でもありません!
この記事では、癇癪の原因別・効果的な対応、やってはいけないNG対応、現役ママの体験談、Q&Aまで徹底解説します。
読むだけで「今日から癇癪の対処に自信が持てる」“解決ガイド”です。ぜひ最後までご覧ください。
癇癪(かんしゃく)とは?~発達障害児の特徴と行動パターン~
癇癪は強い怒りや不安が爆発し、大きな声を出したり、物を投げたりする行動です。
発達障害のある子どもは、気持ちをうまく言葉で伝えることが苦手なため、行動で感情を表現するケースが多くみられます。
【体験談】うちの子(モチ男)の癇癪エピソード
モチ男は癇癪が出た後の切り替えが苦手で、泣き止むまで20分かかることもありました。
気持ちを言葉で説明できないので、泣くことでしか表現できず…。
新しいことへの不安感や、慣れない匂いなどの刺激が強いと、癇癪が長引くことが多かったです。
(親としてはつい「どうして泣きやまないの!?」と焦ってしまうことも…)
癇癪の主な原因&“5大きっかけ”表
| 原因 | 具体例 |
|---|---|
| ①気持ちが言葉にできない | 「遊びたい」「疲れた」と伝えられず泣く |
| ②環境の変化・予定変更 | 突然の来客やスケジュール変更にパニック |
| ③感覚過敏(音・光・匂いなど) | 花火の音や新しい服のタグで癇癪 |
| ④こだわりが強い | いつもの順番やルールが崩れると怒る |
| ⑤疲れ・空腹・眠気 | お腹が空いた、眠い時に怒りやすい |
癇癪を防ぐための“先回り対策”
癇癪が起きたときの“NG対応”と“神対応”
| やりがちNG対応 | 効果的な対応 |
|---|---|
| 「静かにしなさい!」と怒鳴る すぐに注意・否定する | まずは見守り、落ち着くまで待つ 「気持ち分かるよ」と共感ワード |
| 無理やり止める、ひきずる | そっと距離をとる 環境を静かにする |
| 泣き止まない子を責める | 泣きやんだらすぐ褒める 落ち着いたあと気持ちを聞く |
Q&A|親が知りたい癇癪サポート
Q. どうしても怒ってしまう時は?
親だって感情的になる時があります。大切なのは「怒ってしまった後のフォロー」。
しっかり子どもに寄り添い、「ごめんね」「つらかったよね」と声をかけてあげましょう。
Q. 泣き止まない時はどうする?
まずは危険がないよう見守りつつ、落ち着くまで無理に止めません。
「落ち着いたら教えてね」「ここにいるから大丈夫だよ」と伝えましょう。
まとめ|“できること1つ”から始めよう!
癇癪は親のせいでも、わがままでもありません。
「今日からできる先回り」「共感の声かけ」「怒ってしまった自分も責めない」この3つで、親子のストレスは必ず減らせます!
家族みんなで“ゆっくり一歩ずつ”自分たちに合った癇癪対策を見つけていきましょう。
みなさん毎日本当に頑張っています。
自分もお子さんも、しっかり褒めてあげてくださいね。最後までご覧いただきありがとうございます。
あわせて読みたい関連記事
- 発達障害の子どもが独り言を言う理由とは?/発達障害の子どものサイン|早期発見のポイント/発達障害の子どもが癇癪を起こす理由と対処法/【発達障害とは?】特徴・症状を3分で理解!発達グレーの子ができる子に変わる!ABA式“自分でできる”力の育て方/家庭でできる療育【実体験】②スケジュール管理/5歳児健診で再検査・発達指摘

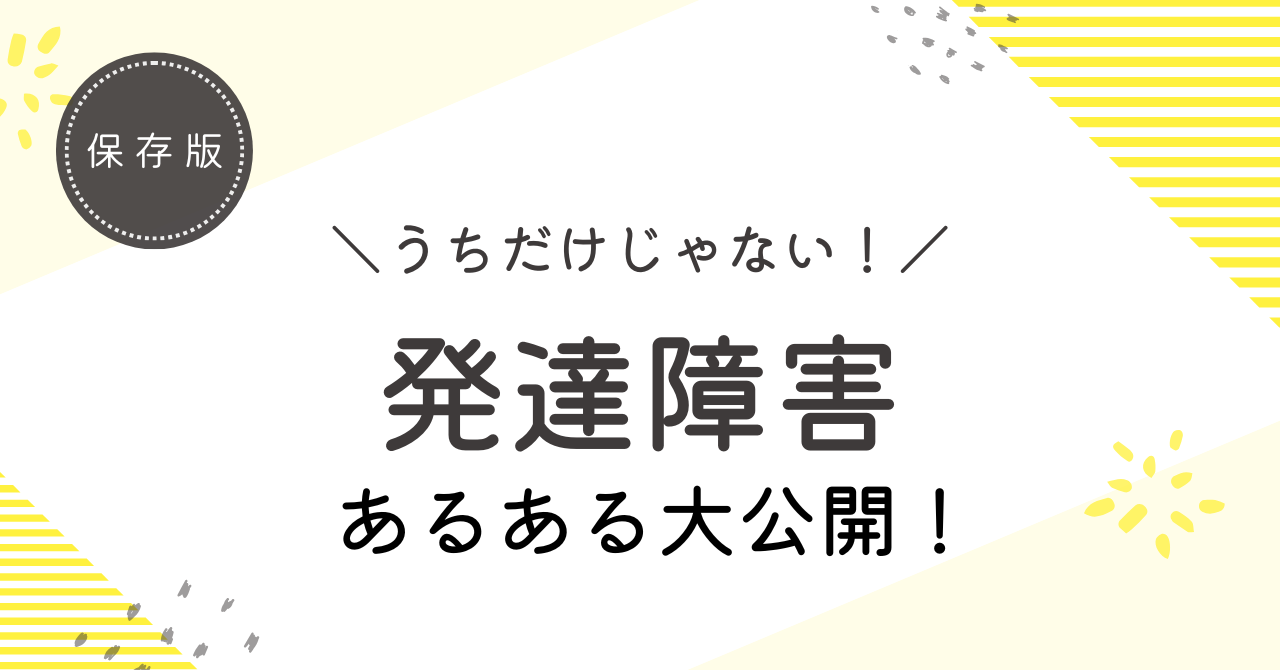
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4734a63a.e6829a88.4734a63b.c0e7bd3f/?me_id=1380587&item_id=10000001&pc=https%3A%2F%2Fimage.rakuten.co.jp%2Fregalo-online-shop%2Fcabinet%2F006.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)