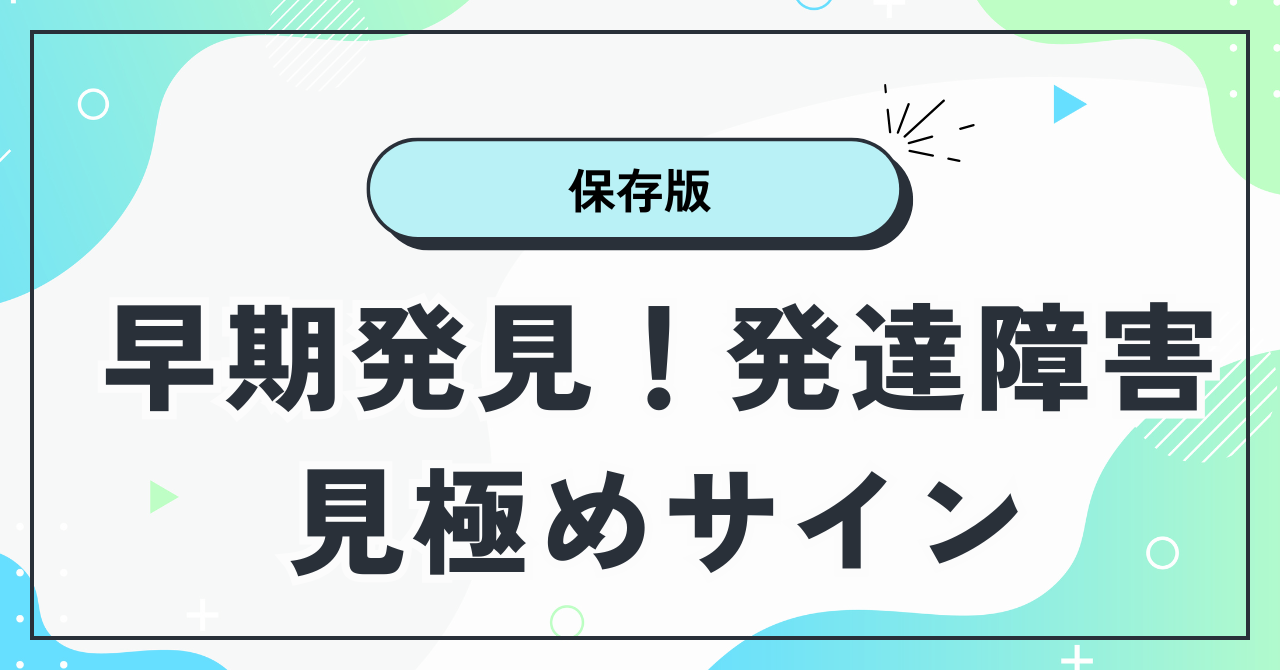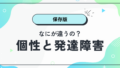こんにちは!おかーちゃんです。
発達障害の子供には、幼いころから特有のサインが見られることがあります。
しかし、それが個性の範囲なのか?専門的な支援が必要なのか?を判断するのはとても難しいものです。
この記事では「発達障害の可能性があるサイン」を表や実体験を交えて解説し、親や周囲ができる対応策をまとめました。
早期発見のポイントを知ることで、子供の成長をよりサポートしやすくなります。 ▶ 実体験ストーリーはこちらもチェック!
発達障害の子供に見られる“サイン”とは?【特徴一覧表】
| チェックポイント | よく見られるサイン |
|---|---|
| 言葉の発達 | ・発語が少ない ・会話が成り立ちにくい ・独特な言い回し |
| コミュニケーション | ・他者への興味が少ない ・友達とうまく遊べない ・一人遊びが多い |
| 行動・こだわり | ・お気に入りの物・順番・場所などへの強いこだわり ・決まった行動の繰り返し ・予定変更が苦手 |
| 感情・反応 | ・気持ちの切り替えが苦手 ・かんしゃくを起こすと泣き止むまで時間がかかる ・感覚過敏(大きな音や光が苦手) |
※ これらは全ての子供に当てはまるわけではありませんが、いくつかのサインが強く見られる場合は注意しましょう。
発達障害の子供のサイン3選
発達障害の子供に見られるサインを3つ紹介します。これらのサインが必ず発達障害と結びつくわけではありませんが、複数当てはまる場合は注意が必要です。
言葉の発達が遅い・話し方が独特
言葉の発達がゆっくりだったり、話し方に特徴があったりするのは、発達障害の子供によく見られるサインのひとつです。
具体的な特徴
言葉の発達が遅い場合、子供は思っていることをうまく伝えられず、イライラすることがあります。
その結果、かんしゃくを起こすこともあります。親は焦らず、子供のペースに合わせながら言葉を引き出す工夫をするとよいでしょう。
友達とうまく遊べない・会話が苦手
発達障害の子供は、同年代の子供と遊ぶことや会話をすることが苦手な場合があります。
よくある様子
友達とうまく遊べないことが続くと、子供は「自分はダメなんだ」と感じてしまうことがあります。
そのため、親や先生が間に入り遊び方を教えたり、少人数で遊べる機会を作ったりすることが大切です。
こだわりが強く、同じ行動を繰り返す
発達障害の子供は、自分なりのルールやこだわりを大切にすることが多いです。
よく見られる行動
こだわりが強い子供に無理に変化を求めると、ストレスを感じてしまいます。
そのため、少しずつ慣れさせたり、安心できる代替手段を考えていきましょう!
【体験談】わが家が気づいた“最初のサイン”と親の気持ち
けれど、この頃はちょうどコロナ禍で、半年近く家族以外とほとんど関わらずに過ごしていました。
いざ保育園が始まり、たくさんのお友達や先生と接するようになると、「あれ?うちの子、他の子と違う?」と感じる場面が徐々に増えてきました。
- 発語が少ない
- 他者への興味が少ない、1人で遊ぶことが多い
- 泣いた時、火がついたように泣く・泣いている時間が長い
- 気に入ったモノ・コトへの執着
実は、この4点は当時の担任の先生にも共通認識として伝わっていました。
また、気持ちの切り替えが苦手で、一度泣くと長時間泣き止まなかったことを「これが普通かな?」と思っていましたが、友達の子と比べてみて「やっぱり何かが違う」と違和感を持ち始めました。
ネットの情報にある典型的な自閉行動には当てはまらず、その違和感に答えが出せないまま悩んでいました。
▶【発達障害グレーゾーン】受診を決めた3年間の葛藤と気づき―息子と私の成長実録①
なぜ“早期発見”が大切なのか?【メリットまとめ】
発達障害のサインに気づいたとき、「うちの子は大丈夫かな?」と不安になるかもしれませんが、
大切なのは「どうサポートすれば、この子が安心して過ごせるか」を考えることです。
【対応策】サインを見つけたらどうすればいい?
- 専門家・支援機関に相談
小児科、発達支援センター、自治体の相談窓口、園や学校の先生など、身近なプロに相談しましょう。
文部科学省|発達障害支援について - 困っていることをメモ・記録する
日々の気になる行動や困りごとを記録しておくと、相談時に役立ちます。 - 焦らず、子供の気持ちに寄り添う
無理に変えようとせず、特性に合わせて接し方を工夫しましょう。
【まとめ】発達障害のサインに早く気づくポイント
私自身も「これでいいのかな?」と悩む日々が続きましたが、
早く気づき行動することで「もっとラクに過ごせる方法」が見つかりました。
あなたも一人で悩まず、一緒に進んでいきましょう。
最後までご覧いただきありがとうございます。
参考リンク あわせて読みたい関連記事
- 行政支援3大ステップ|療育手帳・手当・サービス完全ガイド①
- “できない”から“できた!”へ ペアレントトレーニング成功のコツと親のサポート例
- うちの子が“やる気になる”ABA的ごほうびリスト|発達障害・グレーゾーンにも効果的
- 【発達障害とは?】特徴・症状を3分で理解!学べる基礎ガイド③ADHD・LD
- 【発達障害グレーゾーン】受診を決めた3年間の葛藤と気づき―息子と私の成長実録②
- 【保存版】療育とは?意味・種類・メリット・受け方まで体験談で徹底解説!
- 【保存版】発達障害かも?受診すべきサイン5選+相談先まとめ
- 厚生労働省|発達障害情報・支援